| 日光街道21次 No.03 越谷駅-(約17km)-東武動物公園駅 |
|
| 2013年10月11日(金)09:30 晴 |
|
 |
 |
東武鉄道・越谷駅から東へ進む。52号線を左折して、旧日光街道を北へ進む。古民家が残る宿場通りを10分ほど進むと、右手に正徳3年(1713年)創建の市神神明社がある。 |
| 古商店 |
市神神明社 |
|
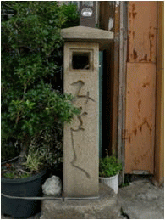 |
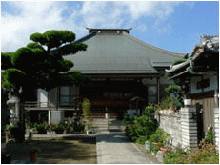 |
市神社からすぐに元荒川に架かる大沢橋を渡る。5分ほどすると、右手に道標を兼ねた常夜燈、さらに5分ほどすると左手に照光院がある。 |
| 常夜燈 |
照光院 |
|
 |
 |
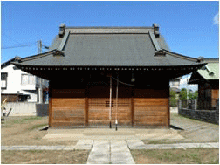 |
| 石仏石塔群 |
庚申塔 |
稲荷神社 |
|
|
照光院からすぐの交差点を左折すると、東武鉄道・北越谷駅がある。旧日光街道を北へ進む。5分ほどの交差点を左折して、東武鉄道の高架を潜る。道なりに北へ曲がるすぐ左手に、台座に三猿の青面金剛と不明の石塔が2基ある。10分ほどすると、右手に宝永7年(1710年)造立の台座に三猿の庚申塔がある。すぐの東武鉄道の踏切を渡り、5分ほどの4号線の大袋駅入口交差点を直進する。渡り終えて右へ下間久里交差点方面に進むと、すぐ左手に稲荷神社がある。
|
|
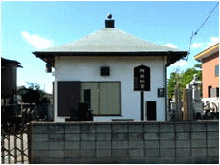 |
日光街道に戻り、北へ進む。5分ほどすると、左手に平成14年(2002年)建立の阿弥陀堂がある。 |
| 阿弥陀堂 |
|
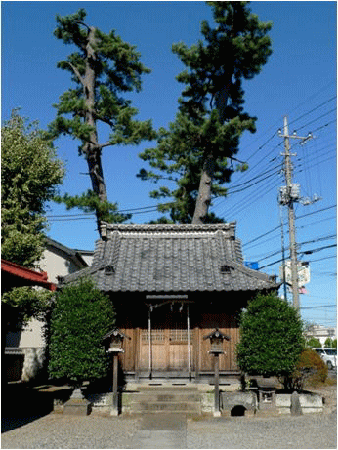 |
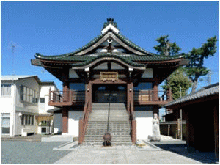 |
| 大枝香取神社 |
歓喜院 |
|
| 阿弥陀堂から15分ほどの陸橋入口交差点で、4号線に合流する。20分ほどの武里駅入口交差点手前左手に、大枝香取神社 / 歓喜院 がある。大枝香取神社は歓喜院の鎮守
/ 村の鎮守であったが、明治の神仏分離で別れた。大枝香取神社本殿は、文化12年(1814年)再建されたもの。大枝香取神社境内にある松の大木は、松並木の名残りと云う。 |
|
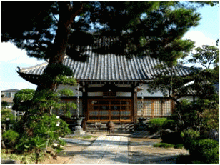 |
旧日光街道は、大枝香取神社からすぐの武里駅入口交差点を直進する。武里駅入口交差点を左折すると、すぐ右手に西光寺がある。 |
| 西光寺 |
|
 |
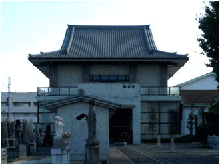 |
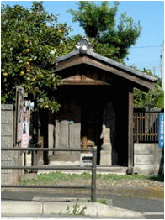 |
| 健御雷神社 |
稱名寺 |
地蔵の祠 |
|
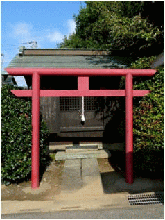 |
武里駅入口交差点まで戻り、旧日光街道を北へ進む。10分ほどの正善小入口交差点を過ぎると、右手に健御雷神社がある。すぐの備後交差点の手前右手に称名寺
/ 備後交差点を過ぎると右手に地蔵の祠 と続く。すぐの小路を右折すると、すぐ左手に社がある。 |
| 社 |
|
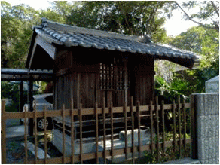 |
 |
 |
| 社 |
備後一里塚跡 |
善巧寺 |
|
| 旧日光街道に戻り、北へ進む。5分ほどすると、右手に社 / 備後(北)交差点右手に備後一里塚跡 / 右手に善巧寺 と続く。 |
|
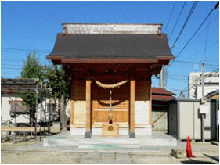 |
 |
 |
| 八坂神社 |
東八幡神社参道 |
|
| 善巧寺からすぐに一の割駅入口交差点がある。15分ほどすると、東武鉄道・野田線を潜る。10分ほどすると、右手に八坂神社がある。境内左手に、神号碑(徳祐彦霊神)
/ 神号碑(猿田彦大神) / 不明の石塔 / 神苑記念碑 が並んでいる。すぐの一宮交差点右手に、東八幡神社の参道がある。 |
|
|
日光街道21次 4番 粕壁(かすかべ)宿
埼玉県春日部市
天保14年(1843年)宿村大概帳
家数:773 本陣:1 脇本陣:1 旅籠:45
|
|
|
宿場は五街道の整備に伴い、元和2年(1616年)に開かれた。古利根川で江戸との物資の集散地として賑わった。日本橋から1泊目となる宿場。4と9のつく日には、六斎市が開かれていた。南北朝時代(1336年〜1392年)新田義貞の家臣・春日部氏が当地を領地としたことから、「春日部」の地名が生まれたとされる。江戸時代の正保年間(1645年〜1648年)には糟壁
/ 糟ヶ辺、元禄年間(1688年〜1704年)には粕壁 / 糟壁 という表記が交互で使われていた。明治期に「粕壁」統一したと云われている。東武鉄道・春日部駅の開業時には、粕壁駅であった。昭和19年(1944年)粕壁町と内牧村が合併した際に、春日部町の表記となった。
|
|
 |
一宮交差点の北西側に東陽寺がある。芭蕉が宿泊したと云われている。本殿手前右手に、曽良の随行日記から「廿七日夜 カスカベニ泊ル 江戸ヨリ九里余」と彫られた石碑がある。元禄2年(1689年)深川を発った芭蕉は、その日の内にここまできた。日本橋より九里余り、およそ38kmの地点になる。
|
| 東陽寺 |
|
 |
 |
旧日光街道は、一宮交差点を左折して西へ進む。10分ほどすると、右手に天保5年(1835年)造立の道標がある。正面に「西南 いハつき」 / 右側面に「東
江戸」 / 裏側に「北 日光」 と彫られている。 |
| 商店 |
道標 |
|
 |
旧日光街道は、道標からすぐの公園橋(西)交差点を直進する。公園橋(西)交差点を左折すると、突き当りに東武鉄道・春日部駅がある。春日部駅に近い1本西側の通りに、天明年間(1781年〜1789年)創建と云われる粕壁神明社がある。
|
| 粕壁神明社 |
|
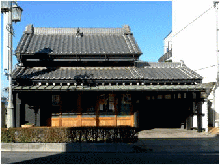 |
公園橋(西)交差点まで戻り、旧日光街道を西へ進む。すぐ右手に慶長年間(1596年〜1614年)創業の米屋、すぐに新町橋(西)交差点がある。 |
| 米屋 |
|
|
|
| [寄り道]最勝院〜春日部八幡神社 |
|
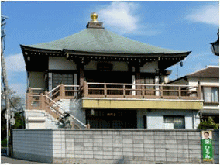 |
 |
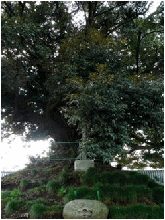 |
| 普門院 |
最勝院 |
春日部重行の墓 |
|
| 旧日光街道は、新町橋(西)交差点を右折して北へ進む。新町橋(西)交差点を直進して西へ進むと、すぐ右手に普門院 / 突き当りに最勝院 がある。普門院は慶長12年(1607年)創建と云われ、最勝院の末寺であった。最勝院の広い境内は、明治時代には小学校が開設されていた。本堂西側にある墳丘(ふんきゅう)は、春日部重行の墓と云われている。春日部重行は春日部実景の孫で、南北朝時代の延元元年(1336年)新田義貞の挙兵に従い戦功を挙げた。その活躍により、春日部郷と上総国山辺南郡の地頭職を安堵された。南北朝時代の観応年間(1350年〜1351年)における観応の擾乱(かんのうのじょうらん)で、京都で敗戦し自刃した 。遺骨は長男・家縄が春日部に持ち帰り、最勝院へ埋葬したと云われている。 |
|
 |
 |
 |
| 大日寺 |
妙楽院 |
地蔵の祠 |
|
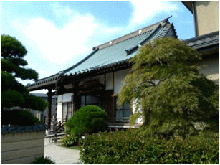 |
 |
最勝院から南西へ進むと、すぐ右手に大日寺 / 右手に妙楽院 と続く。すぐの十字路の南側に、地蔵の祠 / 左折するとすぐ右手に玉蔵院 がある。妙楽院は慶長6年(1607年)創建、最勝院の末寺であった。地蔵堂まで戻り、直進して北西へ進む。すぐ左手に社がある。 |
| 玉蔵院 |
社 |
|
 |
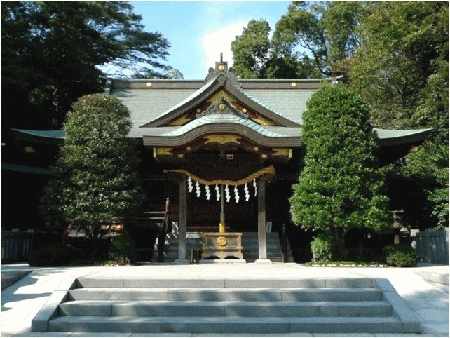 |
| 八幡神社参道入口道標 |
春日部八幡神社 |
|
 |
 |
 |
| 十二支絵馬 |
復興奥の院 |
春日部稲荷神社 |
|
| 社からすぐに十字路がある。次のT字路を左折して、東武鉄道の踏切を渡る。5分ほどの八幡公園交差点を右折すると、すぐ左手に八幡公園 / 元弘年間(1331年〜1334年)創建と云われる春日部八幡神社がある。鳥居の左手にある参道入口道標は、下総国より武蔵国へ繋がっていた鎌倉街道にあったもの。拝殿右側の壁に、十二支絵馬が掛けられている。起伏に富んだ広い境台には、天神社
/ 弁天社 / 氷川社 / 御嶽社 が点在する。 |
|
| 春日部八幡神社や八幡公園の辺りに、春日部氏の居館があったと云われている。春日部八幡神社背後の奥の院や、東側にある春日部稲荷神社などは高台にある。起伏に富んだ地形になっている。公園化に伴う一部発掘では、公園内の平地部分から堀跡や礎石などが検出されていると云う。館のあった場所や形態はを解っていない。 |
|
|
春日部氏は、紀氏一族(長谷雄流)・紀実直が12世紀始めに武蔵国に土着したのが始まり。子の実高は現在の埼玉県春日部市周辺を拠点とし、春日部氏を名乗った。春日部氏が最初に資料に登場するのは、文治3年(1187年)の吾妻鏡。実高の子・実平
/ 孫の実景の代には、鎌倉幕府で有力な武将となっていった。宝治元年(1247年)実景は宝治合戦に三浦氏側として参戦する。三浦泰村が敗戦し自害すると、実景も自害した。実景の孫・重行は、
南北朝時代の延元元年(1336年)新田義貞の挙兵に従い戦功を挙げた。その活躍により、春日部郷と上総国山辺南郡の地頭職を安堵された。南北朝時代の観応年間(1350年〜1351年)における観応の擾乱(かんのうのじょうらん)で、京都で敗戦し自刃した 。戦国時代末期になると岩槻太田氏に仕え、さらに後北条氏の支配下に置かれる。天正18年(1590年)豊臣秀吉による小田原征伐後、領地を没収された。
|
|
|
|
 |
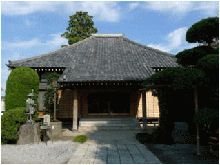 |
旧日光街道は、新町橋(西)交差点を右折して北へ進む。すぐの大落古利根(おおおちふるとね)川に架かる新町橋を渡る。すぐの交差点に319号線の標識があり、左へ進む。交差点を直進する。すぐに斜め左への小路を進むと、すぐ左手に八坂香取稲荷合社と
仲蔵院がある。 |
| 八坂香取稲荷合社 |
仲蔵院 |
|
 |
 |
 |
| 小渕一里塚跡 |
追分 |
道標 |
|
| 319号線の標識がある交差点まで戻る。319号線を北西方向へ進む。5分ほどすると、右手のT字路に小渕 一里塚跡がある。旧日光街道沿いではなく、右折したすぐの右手になる。前方に見えるY字路が追分で、道標が2基ある。左の宝暦4年(1754年)造立の道標には、正面に「青面金剛」/
左側面に「左 日光道」と彫られている。右の宝永6年(1709年)造立の道標には、左側面に「左方 あふしふ道」/ 右側面に「右方 せきやど道」と彫られているらしい。欠け落ちており、すべては判読できない。あふしふ道は、奥州道のこと。右へ進み4号線の小渕(南)交差点を直進するのが、旧関宿往還(319号線)。旧日光街道は左へ進む。 |
|
 |
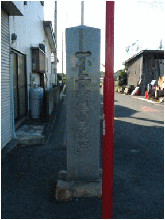 |
追分から左へ進むと、すぐに小渕交差点で4号線に合流する。5分ほどすると、左手に鎌倉時代中期創建と云われる観音院がある。芭蕉が宿泊したと云われている。元禄2年(1689年)建立と云われる仁王門を潜ると、左手に「ものいえば
唇さむし 秋の風」芭蕉句碑がある。5分ほどすると、左手に享禄2年(1529年)創建の浄春院石柱 と続く。 |
| 観音院仁王門 |
浄春院石柱 |
|
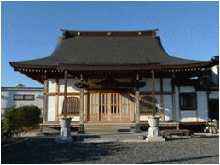 |
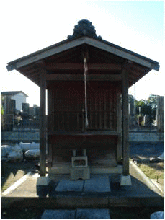 |
 |
| 九品寺 |
堂 |
堤根の道標 |
|
 |
地球儀モニュメントから10分ほどの分岐を、左へ進む。すぐ左手に九品寺がある。境台の堂の左手に、天明4年(1784年)造立の庚申塔を兼ねた堤根の道標がある。正面に「青面金剛
/ 左側面に「右江戸 武州葛飾郡幸手領堤根村」/ 右側面に「左日光」と彫られている。台座の左側側に、明治9年(1876年)から1年間掛けて東京・塩釜間の水準測量を実施した際の水準点が刻まれている。草加宿手前の浅間神社手洗石にもあったもの。すぐ左手に社がある。 |
| 社 |
|
日光街道21次 5番 杉戸(すぎと)宿
埼玉県北葛飾郡杉戸町
天保14年(1843年)宿村大概帳
人口:1663 家数:365 本陣:1 脇本陣:2 旅籠45 |
|
|
古くから利根川(現・古利根川)の渡し場があり、日本武尊が東征を行った際にこの付近に上陸したと云われている。杉の木が茂る港(水門)であったことから、杉門と呼ばれたことが由来と云われている。宿場は五街道の整備に伴い、元和2年(1616年)に開かれた。宿場は街道に沿って、新町
/ 下町 / 中町 / 上町から成り立っていた。下町に問屋場 / 中町に本陣と脇本陣 / 上町に高札場 が置かれていた。5と10のつく日には、六斎市が開かれていた。
|
|
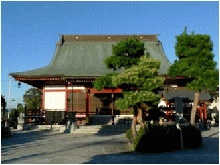 |
 |
 |
| 馬頭院 |
近津神社 |
神明神社 |
|
|
社からすぐの堤根(南)交差点で4号線と合流する。すぐ右手に馬頭院がある。5分ほどの堤根交差点から旧日光街道は左へ進む。15分ほどすると右手に杉戸町役場がある。5分ほどすると、右手に右手に近津神社
/ 右手に神明神社 と続く。近津神社の創建は不詳であるが、貞享元年(1684年)に社殿が建立された記録が残る。
|
|
| 旧日光街道は、神明神社からすぐの本陣跡前交差点を直進する。本陣跡前交差点を左折して南西へ進むと、5分ほどの突き当りに東武鉄道・東武動物公園駅がある。 |
|
 |