| 中山道69次 No.39 鳥居本駅-(約14km)-愛知川駅 |
|
| 2013年 3月13日(水)08:15 晴のち曇り |
|
| 鳥居本駅 |
→ |
専宗寺 |
→ |
小野小町塚 |
→ |
原八幡神社 |
→ |
石清水神社 |
→ |
多賀大社一の鳥居 |
→ |
むちんはし |
→ |
月通寺 |
→ |
唯念寺 |
→ |
豊郷小学校 |
→ |
金田池 |
→ |
千樹寺 |
→ |
歌詰橋石柱 |
→ |
愛知川駅 |
|
|
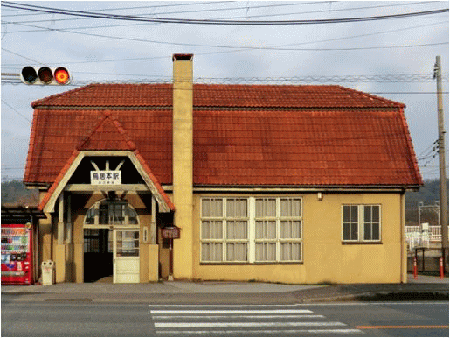 |
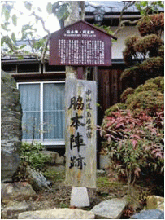 |
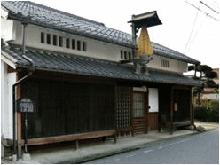 |
| 近江鉄道・鳥居本駅 |
脇本陣跡 |
松屋 |
|
 |
 |
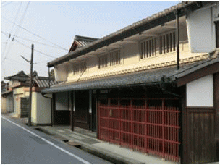 |
| 常夜燈 |
長池地蔵 |
古民家 |
|
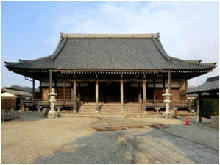 |
近江鉄道・鳥居本駅前の8号線を越え、東へ進む。すぐに旧中山道に突き当り、右折して南へ進む。すぐ左手に脇本陣跡 / 左手に文政8年(1825年)創業の松屋 と続く。建物は建て直されているが、屋根付の合羽形看板が掲げられている。鳥居本宿の名物に、雨合羽や腹薬の赤玉神教丸があった。和紙に紅殻を混ぜた柿渋を塗ることで防水性と保温性を高めた合羽は、旅人に人気があった。すぐの十字路を越えた右手角に常夜燈 / 右手に長池地蔵 / 右手に聖徳太子が創建したと云われる専宗寺 と続く。 |
| 専宗寺 |
|
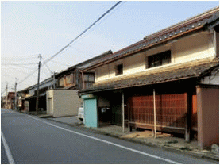 |
 |
 |
| 町並み |
道標 |
往来安全 |
|
 |
専宗寺から5分ほどすると、丁字路の右手角に文政10年(1827年)造立の「左中山道 京 いせ」「右 彦根道」道標 / 左手に往来安全石柱 /
左手に小野町古宿道標 と続く。彦根道は中山道と彦根城下を結ぶ約4kmの重要な道で、朝鮮人街道とも呼ばれていた。朝鮮通信使は中山道を通らず、ここから彦根城下を経て野洲まで回り道をさせていた。 |
| 小野町古宿道標 |
|
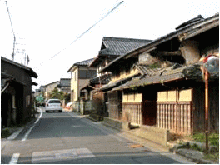 |
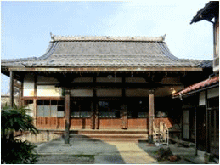 |
 |
| 町並み |
安立寺 |
地蔵の祠 |
|
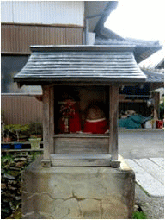 |
 |
 |
| 地蔵の祠 |
八幡神社石柱と常夜灯 |
石仏石塔群 |
|
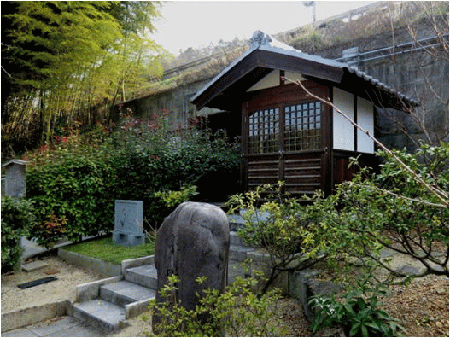 |
 |
| 小野小町塚 |
中山道小野町道標 |
|
|
小野町古宿道標から5分ほどすると、右手に安立寺 / 左手の祠に地蔵 / 左手の祠に地蔵2基 と続く。5分ほどすると、右手に八幡神社石柱と常夜灯がある。社殿は新幹線を越えたところにある。5分ほどすると左手に石仏石塔群 / 小野小町塚と中山道小野町道標 と続く。小野小町はこの付近で生まれたと云われている。出羽郡小野美実が奥州に下る途中、ここ小野に宿泊した。生後間もない可愛い女児を養女に貰い受け、出羽国にへ連れて行き育てたのが小野小町だと云われている。
|
|
 |
 |
| 祇川 白髪塚 芭蕉 昼寝塚 石柱 |
|
 |
| 不動明王 |
原八幡神社 |
|
 |
 |
 |
| 中山道原町道標 |
五百らかん道標 |
はらみち道標 |
|
| 新幹線ガードを潜り、道なりに進む。小野小町塚から10分ほどすると、右手に原八幡神社がある。入口左手に「祇川白髪塚 芭蕉昼寝塚」石柱がある。境内にある不動明王や拝殿に、神仏習合時代の名残りを留める。すぐ右手に、中山道原町道標 / 天保15年(1844年)造立の天寧寺「五百らかん七丁余」道標 / 陽刻で彫られている「はらみち」道標 が並んでいる。天寧寺はここより東北へ約1kmにあり、五百羅漢は井伊家11代藩主・直中が死罪にした腰元親子を弔うために作らせたもの。 |
|
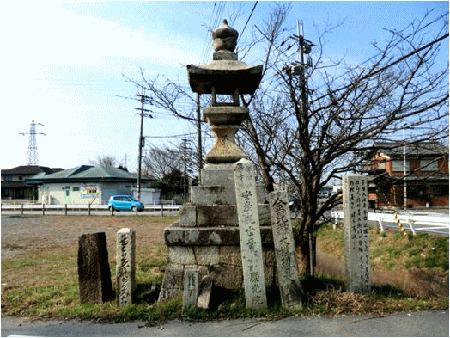 |
すぐの306号線の正法寺町交差点手前左手に、不動院と彫られている常夜燈と7基の石柱がある。左から、不明の石柱 / 「是より多賀ちかみち」道標
/ 上部が壊れて「ハ丁」のみ残る道標 / 上部が壊れて「多賀大社」のみ残る道標 / 「安産観世音 是より四丁 慶光院」道標 / 「金毘羅大権現
是より十一丁」道標 / 碑文が刻まれている多賀神社道標 が並んでいる。 |
| 常夜燈 / 石柱群 |
| |
 |
 |
 |
| 春日神社鳥居 |
勝満寺 |
金比羅道標 |
|
| 常夜燈 / 石柱群から5分ほどすると、右手に春日神社鳥居がある。さらに5分ほどすると 右手に勝満寺 / 左手に「金比羅大権現是ヨリ十丁」道標
と続く。 |
|
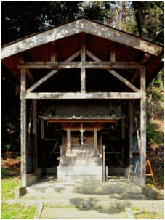 |
 |
 |
| 社 |
堂 |
「是より多賀みち」道標
|
|
 |
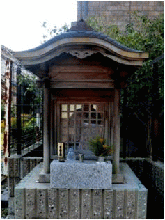 |
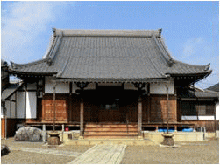 |
| 石清水神社 |
祠 |
唯稲寺 |
|
 |
 |
 |
| 町並み |
「左 彦根道 すぐ中山道」道標 |
祠 |
|
 |
 |
金比羅道標から5分ほどすると、右手の公園に社と堂 / 左手に「是より多賀みち」道標 / 右手に飛鳥時代より応神天皇とその母神功皇后を祭る石清水神社
/ 左手に堂 / 右手に唯稲(ゆいしょう)寺 / 左手に「左 彦根道すぐ中山道」道標 / 左手に社 / 右手に堂 と続く。「左 彦根道すぐ中山道」の「すぐ」は、真っ直ぐのこと。 |
| 町並み |
堂 |
|
|
中山道69次 64番 高宮(たかみや)宿
滋賀県彦根市高宮町
天保14年(1843年)中山道宿村大概帳
人口:3560人 家数:835 本陣:1 脇本陣:2 旅籠:23
|
|
| 多賀大社への最寄りの宿場で、多賀大社一の鳥居がある。多賀大社参道の門前町として、高宮布の集散地として賑わった。高宮布は細糸で織った質のよい高級麻布のことで、近江商人によって全国に売りさばかれた。彦根藩から将軍家への献上品にもなっていた。町並みは往時の面影を残している。 |
|
 |
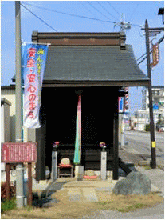 |
| 大北地蔵 |
|
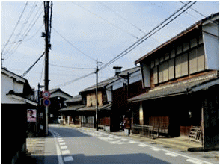 |
| 道標 / 多賀大社常夜燈 |
町並み |
|
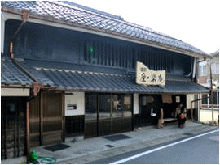 |
 |
 |
| 宿駅 座・楽庵 |
高宮神社鳥居 |
町並み |
|
|
唯稲寺から10分ほどすると、右手に「鳥居本宿→ ←高宮の街」道標と多賀大社常夜燈がある。すぐに近江鉄道の踏切を渡る。高宮町大北交差点を越えた右角に、明治33年(1900年)造立の眼病にご利益のあると云われている大北地蔵がある。5分ほどすると、右手に鎌倉時代末期創建の高宮神社鳥居がある。
|
|
 |
 |
| 常夜燈(南西側から撮影) |
|
 |
| 多賀大社一の鳥居(南西側から撮影) |
福々タヌキ |
|
|
高宮神社鳥居からすぐの高宮鳥居前交差点の左手に、寛永11年(1635年)に建替えられた高さ11m・柱間幅8mの多賀大社(たがたいしゃ)一の鳥居 / 鳥居の右手に高さ6m・底辺3.3m正方形の常夜燈 がある。ここから多賀大社までは約3kmの距離。交差点の右角に、福々タヌキがある。
|
|
|
|
| [参考]多賀大社 |
|
 |
 |
| 鳥居 |
|
 |
| そり橋 / 神門 |
社殿 |
|
 |
多賀大社は和銅5年(712年)編纂の古事記に記載がある古社で、式内社。伊勢神宮 / 熊野大社とともに参詣で賑わった。江戸時代は「お伊勢参らば
お多賀に参れ お伊勢お多賀の子でござる」「お伊勢へ七度 熊野へ三度 お多賀さまへは月参り」「お伊勢参らばお多賀へ参れ」と云われた。祭神の「伊邪那岐命」と「伊邪那美命」が伊勢神宮の天照大神の親であることから「お伊勢お多賀の子」と云われた。お守りとして杓子(しゃもじ)を授ける「お多賀杓子(おたがじゃくし)」は、「お玉杓子」や「オタマジャクシ」の名の由来とされている。そり橋は豊臣秀吉が寄進したもの。 |
| 絵馬 |
|
|
|
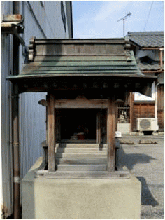 |
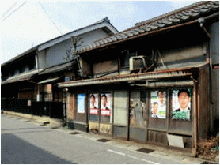 |
 |
| 社 |
古民家 / 小林家 |
俳聖芭蕉翁旧跡 紙子塚 |
|
 |
 |
 |
| 本陣跡 |
円照寺 |
町並み |
|
 |
 |
 |
| 祠 |
むちんはし石柱 |
むちん橋地蔵堂 |
|
|
多賀大社一の鳥居からすぐの右手に社 / 右手の小林家の柵内に「俳聖芭蕉翁旧跡 紙子塚」石柱 と続く。貞享元年(1684年)松尾芭蕉が3代目当主・小林意猪兵衛門忠淳宅に一泊したとき、自分が横になっている絵を描いて「たのむぞよ
寝酒なき夜の 古紙子」の句を詠んだ。紙子とは紙で作った衣服のことで、紙子塚は庭に古い紙子を納めた塚。すぐの左手に表門が残る本陣跡 / 右手に明応7年(1498年)仏堂を建立したのが始まりの円照寺
/ 犬上川に架かる高宮橋(むちん橋)と続く。高宮橋の手前右手に、天保3年(1832年)造立の「むちんばし」石柱 / むちん橋地蔵堂 がある。彦根藩は地元商人や一般人の浄財で橋を架けさせ、渡り賃を無料とした。当時川渡しや仮橋は有料であったので、この橋を「むちんばし」と呼ぶようになった。むちん橋地蔵は、昭和52年(1977年)むちん橋橋脚改修工事の際に脚下から発掘された2基の地蔵。宿場は高宮橋で終わる。
|
|
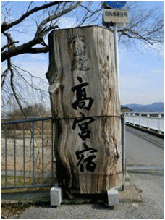 |
 |
 |
| 高宮宿道標 |
祠 |
法士一里塚跡 |
|
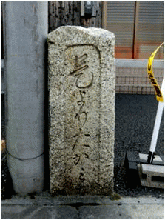 |
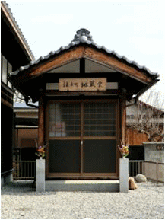 |
 |
| 道標 |
法士町地蔵堂 |
八幡神社 |
|
| 犬上川に架かる高宮橋(むちん橋)を渡ると、右手に高宮宿道標 / 左手に祠 と続く。すぐの新安田橋を渡ると、左手に法士一里塚跡 / 左手に「是よりたかミち」道標
/ 左手に法士町自治会館 と続く。法士町自治会館横に法士町地蔵堂 / 奥に八幡神社 がある。 |
|
 |
 |
 |
| 古民家 |
月通寺 |
不許酒肉五辛入門内 |
|
 |
 |
 |
| 若宮八幡宮 |
了法寺 |
還相寺 |
|
 |
 |
 |
| 堂の川地蔵 |
常夜燈 / 社 |
鹿嶋神社 |
|
|
法士町自治会館から5分ほどすると、右手に月通寺がある。山門前にある「不許酒肉五辛入門内(しゅにくごしんにゅうもんにいらず)」は、禅宗であったころの名残り。酒 / 肉 / 五辛(ごしん)を寺に持ち込むことを禁ずることで、五辛とは葫(にんにく) / 韮(にら) / 薤(らっきょう) / 葱(ねぎ) / 蘭葱(のびる) のこと。すぐ右手に、参道入口の建物に産の宮由緒が架かる若宮八幡宮がある。文和5年(1356年)室町幕府二代将軍・足利義詮の側室が、この地で男子を出産した。付人として家臣9名がこの地に残り保護したが、幼くして亡くなった。生母は髪を下して尼となり、この地に一庵(松寺)を結んで幼君を弔った。土着した家臣9人は竹と藤蔓で作った葛籠を作る様になり、松寺の北方に社を祀ったのが若宮八幡宮。すぐ右手に了法寺 / 道を挟んだ左手に還相寺 / 右手に堂の川地蔵 / T字路の右手に常夜燈と社 と続く。T字路を左折すると、すぐの左手に左手に鹿嶋神社がある。
|
|
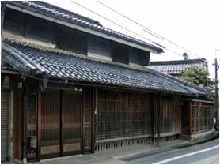 |
 |
| 古民家 |
松並木 |
|
 |
 |
旧中山道に戻り、南西へ進む。5分ほどすると松並木になる。すぐ左手に平成8年(1996年)造立の「またおいでやす」モニュメント / 左手に中山道葛籠町道標 と続き、5分ほどの松並木が終わる。 |
| またおいでやすモニュメント |
中山道葛籠町道標 |
|
 |
 |
 |
| 中山道出町道標 |
日枝神社 |
地蔵堂 |
|
 |
 |
 |
| 清□園 |
四阿の休憩所 |
中山道出町道標 |
|
|
中山道葛籠町道標からすぐ左手に中山道出町道標 / 左手に日枝神社 / 右手に地蔵堂 / 清□園 / 四阿の休憩所 / 右手に中山道出町道標 と続く。
|
|
 |
 |
中山道出町道標から10分ほどすると、右手にと阿自岐神社石柱と常夜燈 / 左手に不明の石塔 と続く。 |
| 阿自岐神社石柱 / 常夜燈 |
不明の石塔 |
|
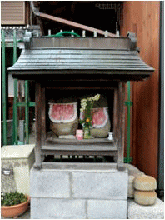 |
 |
 |
| 地蔵の祠 |
唯念寺 |
恵林寺 |
|
| 不明の石塔からすぐ左手の先人を偲ぶ館標識の手前を左折すると、左手に地蔵の祠 / 奥に唯念寺と恵林寺 がある。旧四十九院村の四十九院とは、行基が天平3年(731年)この地に四十九の寺を建立したことに由来する。唯念寺は四十九番目の寺で、行基作の阿弥陀如来像と弥勒菩薩像がある。先人を偲ぶ館前のベンチで昼食を摂る。先人を偲ぶ館は、豊郷に生まれて活躍した先人の業績などを紹介している施設。
|
|
 |
 |
 |
| 地蔵3基 / 不明の石柱3基 |
春日神社鳥居 |
豊郷小学校旧校舎 |
|
| 先人を偲ぶ館からすぐの左手に地蔵3基と不明の石柱3基 / 左手に春日神社鳥居 / 左手に豊郷小学校 と続く。豊郷小学校旧校舎は昭和12年(1937年)本校出身で伊藤忠商事および丸紅の前身にあたる伊藤忠兵衛商店専務・古川鉄治郎が、アメリカ人建築家ウィリアム・メレル・ヴォーリズに設計させた当時としては珍しいコンクリート校舎。ウィリアム・メレル・ヴォーリズ)は、日本で数多くの西洋建築を手懸けた建築家。近江兄弟社創立者の一人で、メンソレータムを日本に普及させた。 |
|
 |
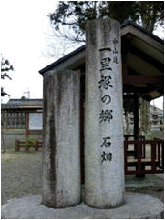 |
豊郷小学校からすぐの左手に、境内に「中山道 一里塚の郷 石畑」碑のある八幡神社 / 左手に敷地に一里塚があったとi云われている豊郷町役場 と続く。石畑は平安時代から続く地で、江戸時代後期には高宮宿と愛知川宿の間の宿として賑わった。 |
| 八幡神社 |
中山道 一里塚の郷 石畑 碑 |
|
 |
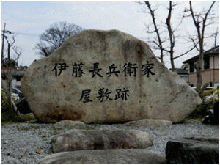 |
 |
| くれなゐ園 |
伊藤長兵衛家屋敷跡 |
伊藤長兵衛旧邸 |
|
|
豊郷町役場から豊郷町役場前交差点を越え5分ほどすると、T字路に「左 豊郷駅250m」標識 / 左手の「くれなゐ園」に伊藤長兵衛家屋敷跡 / 左手に伊藤長兵衛旧邸
と続く。安政4年(1858年)初代・伊藤忠兵衛が近江麻布類行商は始めたことが、伊藤忠や丸紅の創業としている。代々、伊藤忠兵衛を継承している。伊藤長兵衛旧邸は初代の住居住で、2代目が生まれた。
|
|
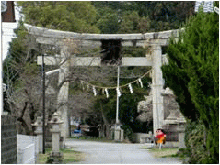 |
 |
 |
| 天稚彦神社鳥居 |
古民家 |
水の香る郷石柱 / 金田池案内板 |
|
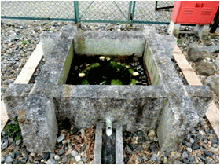 |
 |
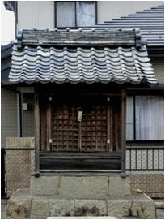 |
| 金田池 |
西沢新平家邸跡 |
堂 |
|
| くれなゐ園から5分ほどすると、右手に天稚彦神社鳥居 / 右手に復元された金田池 と続く。水の香る郷石柱 / 金田池案内板 / 金田池 / 西沢新平家邸跡石柱
と並び、奥に堂がある。湧水はが田畑の用水や中山道の旅人の喉を潤していたが、出水しなくなり埋立てられた。 |
|
 |
 |
 |
| 一里塚跡 |
豊会館 |
西還寺 |
|
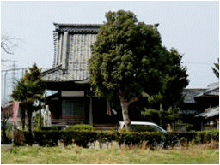 |
 |
 |
| 千樹寺 |
江州音頭発祥地モニュメント |
江州音頭発祥地石柱 |
|
 |
金田池から5分ほどすると、右手に一里塚跡 / 奥に豊会館(藤野家旧宅)がある。石畑一里塚跡であるが、豊郷町役場前交差点の南側にあった。藤野喜兵衛(屋号又十)は、北海道開拓で財をなした。すぐ左手に西還寺
/ 右手に千樹寺 / 江州音頭発祥地モニュメント / 江州音頭発祥地石柱 / 「扇踊り 日傘踊り 中仙道千枝の里」石柱 と続く。江州音頭は戦火で焼失した観音堂(千樹禅寺)を天正14年(1586年)再建したとき、余興に村人に経文を面白おかしく節をつけ身振り手振りで躍らせたのが始まり。今のようになったのは、再び焼失して弘化3年(1846年)再建されたときで、一般大衆向きの音頭を作らせ踊ったものが広まった。
|
| 中仙道千枝の里石柱 |
|
 |
中仙道千枝の里石柱から5分ほどの宇曾川に架かる歌詰橋を渡ると、右手に歌詰橋石柱 / 宇曾川と歌詰橋案内板がある。宇曾川は泰川山と押立山を水源として琵琶湖に注ぐ川で、水量が豊富で舟運が盛んであった。運槽川と呼ばれていたが、なまって宇曾川になったと云う。歌詰橋は940年(天慶3年)東国で平将門を殺し首級あげた藤原秀郷にまつわる伝説。藤原秀郷がこの橋まで戻ってきたとき、目を開いた将門の首が追いかけて来た。秀郷が将門の首に向かって「歌を一首」と言った。歌に詰った首は橋の上に落ち、以来歌詰橋と呼ばれる様になった。 |
| 歌詰橋石柱 |
|
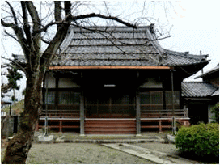 |
 |
 |
| 普門寺 |
堂 |
正光寺 |
|
 |
歌詰橋石柱からすぐの左手に愛知川宿2.1km標識 / 左手に普門寺 / 左手に堂 / 左手に正光寺 / 左手に石部神社鳥居 と続く。
|
| 石部神社鳥居 |
|
 |
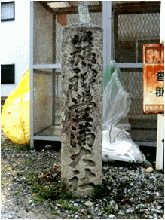 |
石部神社鳥居から5分ほどすると沓掛交差点、すぐに分岐がある。旧中仙道は右へ、近江鉄道・愛知川駅は左へ進む。三角地帯に旗神豊満大社道標がある。近江鉄道・愛知川駅の南にある神社で、神功皇后軍の軍旗を祀って創建されたと云われている。 |
| 分岐 |
旗神豊満大社道標 |
|
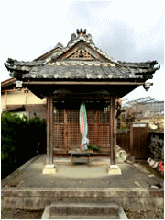 |
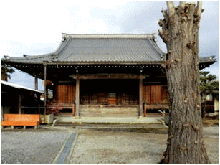 |
分岐を左へ進む。すぐ右手に堂 / すぐ右手に勝光寺 と続く。勝光寺前の分岐を左へ、十字路を右折すると、勝光寺から5分ほどで近江鉄道・愛知川駅に至る。 |
| 堂 |
勝光寺 |
|
 |
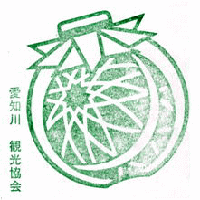 |
 |
| 瓶手鞠型ポスト |
愛知川駅スタンプ |
マンホール |
|
|
近江鉄道・愛知川駅前に、愛知川伝統工芸・瓶手毬の形をした郵便ポストがある。愛知川駅併設の物産館にある観光協会スタンプやマンホールにも、瓶手毬のデザインが見られる。江戸時代の終わりに遡り、愛知川町に残る最古の瓶手毬は天保年間(1840年頃)のもの。
|
|
 |