| 中山道69次 No.38 守山駅-(約1km)-守山銀座西交差点-(約6km)-草津追分 |
|
| 2013年 2月28日(木)08:30 晴 |
|
| 守山駅 |
→ |
守山銀座西交差点 |
→ |
樹下神社 |
→ |
今宿一里塚 |
→ |
十王寺 |
→ |
大宝神社 |
→ |
伊砂砂神社 |
→ |
草津川隧道 |
→ |
草津追分 |
|
|
 |
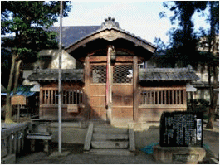 |
 |
| 土橋 |
樹下神社 |
停車場道道標 |
|
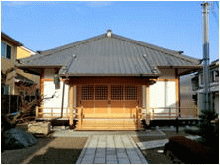 |
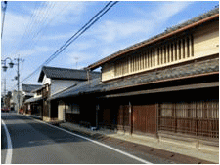 |
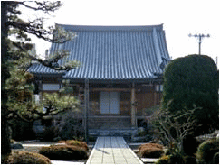 |
| 超勝寺 |
古民家 |
本像寺 |
|
|
JR東海道本線・守山駅から146号線を北西へ進む。10分ほどの守山銀座西交差点を左折、すぐに土橋を渡る。当時の守山宿と今宿村の境を流れる境川(吉川)に架かる橋で、幅2間(3.6m)
/ 長さ20間(36m)もあった。現在は長さ4.8mのコンクリート橋になっている。中山道の重要な橋として、瀬田唐橋の古材を使って架け替えられた公儀御普請橋であった。橋を渡り、守山宿の加宿として栄えた今宿の町並を進む。土橋からすぐの右手に、延久3年(1071年)創建の樹下神社がある。境内に今宿町交差点から移設された停車場道道標がある。明治45年(1912年)東海道本線・守山駅が開業、中山道と結ぶ守山停車場線道路が完成する。中山道今宿から勝部を通り守山駅に通じていた。すぐ右手に超勝寺
/ 左手に本像寺 と続く。
|
|
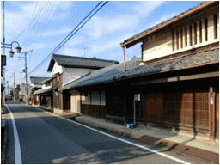 |
 |
| 町並み |
今宿一里塚 |
|
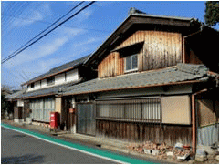 |
 |
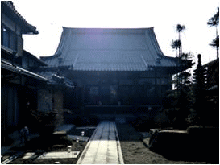 |
| 古民家 |
住連房母公墓石柱 |
徳栄寺 |
|
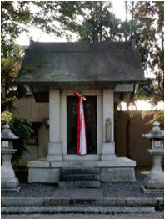 |
 |
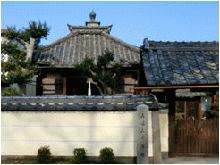 |
| 諏訪神社 |
稲荷神社 |
十王寺 |
|
|
本像寺からすぐに今宿町交差点を横断、5分ほどすると左手に南塚のみが残る今宿一里塚がある。5分ほどすると、左手小路入口に住連房母公墓石柱がある。住蓮坊が処刑されると聞き、馬淵を目指して中山道を急いだ。この地で既に首を討たれたとの報せを受け、絶望のあまり焔魔堂前の池(尼ヶ池)に身を投げた。すぐ左手に徳栄寺
/ 左手に諏訪神社 / 境内に稲荷神社 / 道の右手に十王寺 と続く。
|
|
 |
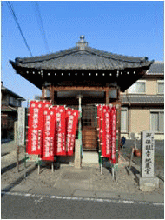 |
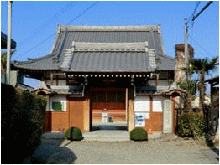 |
| 大宝神社鳥居 |
佛眼寺地蔵堂 |
佛眼寺 |
|
 |
 |
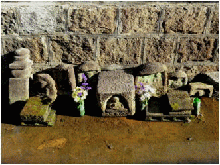 |
| 不明の石柱 |
古民家 |
石仏石塔群 |
|
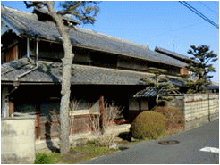 |
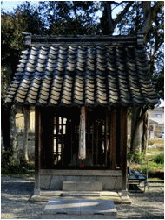 |
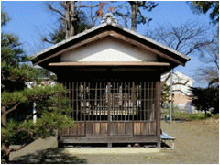 |
| 古民家 |
八幡宮 |
稲荷大明神 |
|
|
十王寺から10分ほどすると、左手に大宝神社鳥居 / 右手に佛眼寺地蔵堂 / 奥に佛眼寺 / 左手に不明の石柱 / 小川の左手に石仏石塔群 と続く。明治の神仏分離によって、仏眼寺と大宝神社になる。すぐの栗東駅西口交差点を左折すると、突き当りにJR東海道本線・栗東駅がある。栗東駅西口交差点を直進、10分ほどすると左手に八幡宮
/ 右手に稲荷大明神 と続く。
|
|
 |
 |
 |
| 草津宿案内地図 |
JR東海道本線トンネル |
町並み |
|
 |
 |
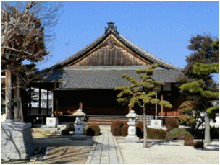 |
| 伊砂砂神社 |
行園寺 |
光明寺 |
|
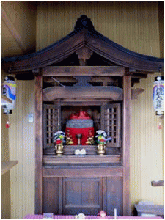 |
葉山川に架かる葉山川橋を渡る。稲荷大明神から5分ほどの葉山川橋交差点の先左手に草津宿案内地図がある。左折してJR東海道本線トンネルを潜る。トンネルを出ると中山道標識があり、右折しJR線路沿いの側溝上を進む。案内板や標識があり、道に迷う心配はない。JR東海道本線トンネルから10分ほどすると2号線高架架橋を潜る。すぐ左手に応仁2年(1468年)築の本殿が重文の伊砂砂神社
/ 右手に行園寺 / 右手に貞永元年(1232年)天台宗の道場が始まりの光明寺 / 左手に双体道祖神の祠 と続く。 |
| 双体道祖神 |
|
 |
 |
 |
| 覚善寺 |
大路井道標 |
小汐井神社 |
|
|
双体道祖神の祠からすぐの大路交差点付近に、中山道最後の一里塚があった。右折するとJR東海道本線 / 草津宣・草津駅がある。大路交差点直進する。すぐの交差点を越え、きたなかアーケード商店街を進む。すぐの十字路を左折すると、左手の覚善寺前に大路井(おちのい)道標 / すぐ左手に貞観5年(863年)創建の小汐井神社がある。明治19年(1886年)旧草津川隧道が開通すると、江戸時代260年余り続いた東海道のルートが変更される。旧草津川南側にあった東海道と中山道の分岐点は、当時は中山道に面していた覚善寺南西角に移ることになった。明治19年(1886年)大路井道標が新東海道と中山道の分岐点に建てられるが、現在は覚善寺門前に移築されている。
|
|
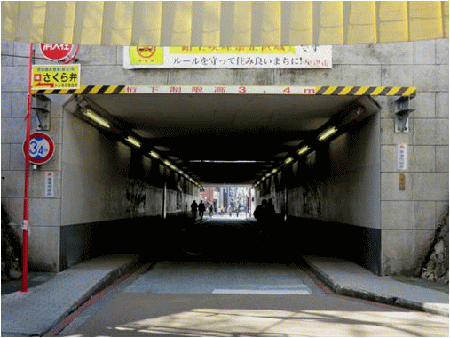 |
旧中山道に戻り、南西へ進む。すぐに草津川隧道(トンネル)がある。トンネルの両側に、当時の街道壁画が描かれている。明治19年(1886年)旧草津川隧道が開通するまでは、天井川の草津川を越えていた。 |
|
 |
| 草津川隧道 |
草津川隧道(追分側) |
|
|
中山道69次 68番 草津(くさつ)宿
滋賀県草津市
天保14年(1843年)中山道宿村大概帳
人口:2351人 家数:586 本陣:2 脇本陣:2 旅籠:72
|
|
| 宿の歴史は古く、平安時代からあった。江戸時代には江戸から68番目の中山道と52番目の東海道の宿として、両街道が合流・分岐する交通の要衝として栄えた。東海道は草津川を渡って出入りするが、草津川は通常は水がなく橋は架けられていなかった。中山道は明治19年(1886年)旧草津川隧道が開通するまでは、天井川の草津川を越えていた。江戸
/ 京 / 大阪との人や物の往来とともに情報や文化が集まり、すぐれた街道文化が育まれた。草津名物として「うばがもち」がある。草津宿には72軒もの旅籠があった。 |
|
 |
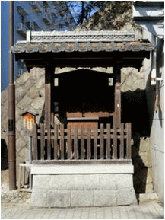 |
 |
| 道標を兼ねた常夜燈 |
高札場 |
延命地蔵 |
|
 |
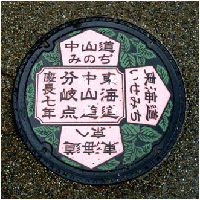 |
草津川隧道(トンネル)を出ると、東海道と中山道が分岐・合流する追分。左手の高台に文化13年(1816年)造立の道標を兼ねた常夜燈があり、「左 中仙道 美のじ」「右 東海道 いせみち」と彫られている。右手に高札場と延命地蔵 / 合流する路面にカラフルなマンホールがある。 |
|
マンホール |
|
 |
 |
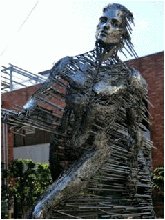 |
| 草津町道路元標 |
書状集箱 |
オブジェ |
|
|
南側角の草津公民館前に、草津町道路元標 / 明治4年(1871年)当時に復元された書状集箱(現役の郵便ポスト) / 「近江路や秋のくさつはなのみして
花咲くのべぞ何處ともなき」尭孝法師句碑 / 旅人が行き交う時間を表現したオブジェ がある。
|
|
 |