| 中山道69次 No.33 羽場駅-(約15km)-岐阜駅 |
|
| 2012年11月21日(水)08:30 晴 |
|
| 羽場駅 |
→ |
津島神社 |
→ |
長楽寺 |
→ |
竹林寺 |
→ |
浄慶寺 |
→ |
伊豆神社 |
→ |
誓賢寺 |
→ |
細畑一里塚 |
→ |
加納八幡神社 |
→ |
善徳寺 |
→ |
専福寺 |
→ |
旧加納町役場 |
→ |
加納天満宮 |
→ |
信浄寺 |
→ |
岐阜駅 |
|
|
 |
 |
 |
| 津島神社 |
不明の石柱 |
愛宕神社常夜燈 |
|
|
名鉄・羽場駅から北へ進む。JR高山本線を陸橋で越え、21号線を横断する。名鉄・羽場駅から5分ほどのところの交差点の北東側に、津島神社がある。交差点を左折して旧中山道を西へ進むと、すぐ右手に不明の石柱と明治32年(1899年)造立の愛宕神社常夜燈がある。
|
|
| 愛宕神社常夜燈からすぐの鵜沼羽場町交差点で、21号線と合流する。10分ほどの山の前町交差点の先に、JR高山本線を越える陸橋が見えてくる。すぐ左手に旅人道中安全の石塔
/ 後ろに明治24年(1891年)のM8濃美地震で2つに折れてしまった槍ヶ岳開祖の播隆上人碑がある。中央の上下に地蔵が置かれている。この辺りに、山の前一里塚があった。 |
 |
|
 |
| 旅人道中安全 |
播隆上人碑 |
|
 |
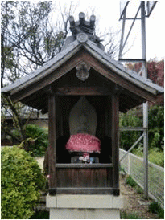 |
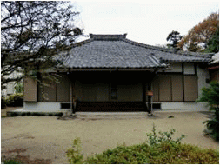 |
| 神明神社 |
馬頭観音 |
長楽寺 |
|
 |
 |
陸橋の側道に階段で登り、JR高山本線を越える。10分ほどすると、右手にJR各務原駅がある。15分ほどの三ツ池町交差点手前右手に神明神社がある。明治35年(1902年)再建の拝殿は、昭和34年(1959年)伊勢湾台風で倒壊した。三ツ池町交差点を渡ると、すぐ右手に馬頭観音
/ 右手に長楽寺 / 右手に馬頭観音 / 右手に地蔵堂 と続く。 |
| 馬頭観音 |
地蔵堂 |
|
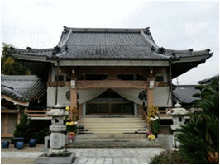 |
 |
 |
| 竹林寺 |
六軒一里塚跡 |
秋葉神社 |
|
 |
 |
 |
| 六軒の地蔵 |
神明神社 |
神号碑(山神) |
|
 |
地蔵堂から10分ほどすると、三柿野駅前交差点を横断する。陸橋下中央の階段を登り、途中で右へと登る。陸橋の側道を通り、名鉄線を越える。三柿野駅前交差点から10分ほどの分岐を右へ進む。5分ほどすると、左手に竹林寺
/ 右手に六軒一里塚跡 / 右手に秋葉神社 / 右手に六軒の地蔵 / 右手に神明神社 / 神号碑(山神)と馬頭観音 と続く。 |
| 馬頭観音 |
|
 |
神明神社から15分ほどすると、右手に各務原市役所がある。角の交差点を右折して飛行場通りを北へ進むと、すぐ左手に皇大神宮がある。すぐ左手の各務原市文化センターで昼食を摂る。 |
| 皇大神宮 |
|
 |
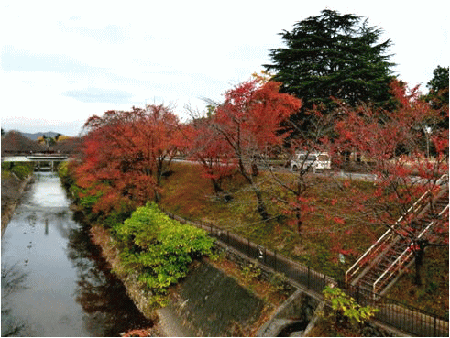 |
| 恐竜 |
|
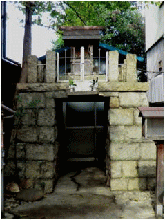 |
| 栄町秋葉神社 |
那加橋からの新境川 |
|
| 各務原市役所角の交差点まで戻り、旧中山道を西へ進む。5分ほどすると、右手の那珂交番に恐竜がある。市民公園脇を進み、那珂交番から5分ほどの新境川に架かる那加橋を渡る。すぐ右手に栄町秋葉神社がある。 |
|
|
新加納(しんかのう)宿は、鵜沼宿と加納宿の間に位置した間の宿(あいのしゅく)。現在の岐阜県各務原市那加新加納町。鵜沼宿と加納宿間は4里10町(約17km)あったために立場が設けられ、発展して間の宿となった。宿場の入口に枡形、高礼場
/ 旗本・坪内家の陣屋 / 茶屋などがあった。関ヶ原の戦いで功績を挙げた坪内利定は、美濃国羽栗郡と各務郡20村の6500石を治める旗本となる。拠点を松倉城から美濃国各務郡新加納村に移し、新加納陣屋を築いた。
|
|
 |
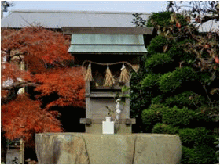 |
 |
| 西那加稲荷神社 |
秋葉神社 |
中山道道標 |
|
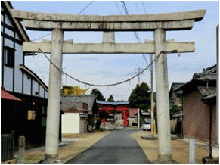 |
 |
| 日吉神社 |
|
 |
| 新加納一里塚跡 |
分岐 |
|
 |
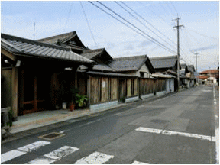 |
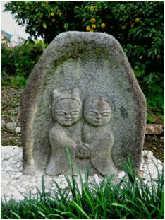 |
| 道標 |
町並み |
道祖神 |
|
|
栄町秋葉神社から10分ほどすると、右手に西那加稲荷神社がある。5分ほどの新加納交差点から右へ進む。さらに5分ほどすると、右手に秋葉神社 / 左手に中山道道標
/ 右手に日吉神社鳥居 と続く。すぐの分岐に、新加納一里塚跡 / 中山道新加納立場案内板 がある。分岐に中山道標識があり、左へ進む。すぐの突き当りに旗本坪内氏の御典医だった医院がある。突き当りの左手に「左
木曽路 右 京路 南 かさ松」道標がある。突き当りを右折、すぐの突当りを左折する。右からの道は、新加納立場案内板のところで分かれた道。すぐ左手に、道祖神と尾張徳川家の狩の際の宿泊所となったため葵の紋章が許された善休寺石柱がある。
|
|
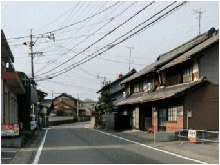 |
 |
 |
| 町並み |
手力雄神社参道と合流 |
手力雄神社鳥居 |
|
 |
 |
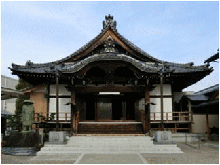 |
| 道標 |
手力雄神社鳥居 |
浄慶寺 |
|
 |
 |
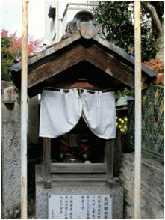 |
| 中山道道標 |
古民家 |
馬頭観音 |
|
 |
道祖神から15分ほどすると、東海北陸自動車道を潜る。さらに5分ほどすると、境川に架かる高田橋を渡る。20分ほどすると、左手からの手力雄神社参道と合流する。手力雄神社参道に鳥居と「左
木曽路」道標、さらに道路の片側に赤い鳥居がある。合流すると、すぐ右手に浄慶寺 / 右手に中山道道標と切通の由来案内板 と続く。切通は境川北岸に位置し、岩戸南方一帯の滞留水を境川に落としていたことによる。手力雄神社前から浄慶寺付近までは立場として、茶屋
/ 菓子屋 / 履物屋などが設けられ旅人で賑いがあった。5分ほどすると右手に馬頭観音 / 右手に伊豆神社 と続く。 |
| 伊豆神社 |
|
 |
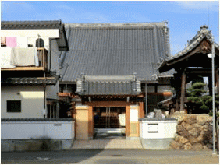 |
 |
| ゑ比寿神社 |
眞宗寺 |
誓賢寺 |
|
 |
伊豆神社から5分ほどすると、右手に参道が旧中山道に沿うゑ比寿神社 / 右手に眞宗寺 / 右手に誓賢寺 / 左手の“細畑火の見やぐら373バス停”前に秋葉神社
と続く。 |
| 秋葉神社 |
|
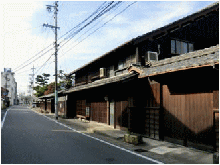 |
 |
 |
| 町並み |
細畑一里塚(北側) |
細畑一里塚(南側) |
|
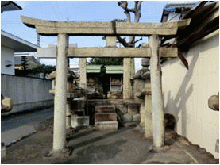 |
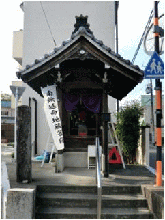 |
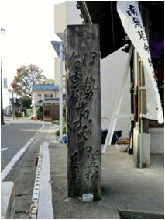 |
| 細畑一里塚(南側)の社 |
地蔵堂 |
道標 |
|
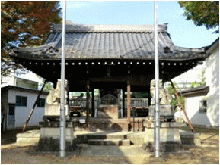 |
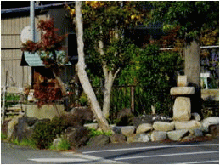 |
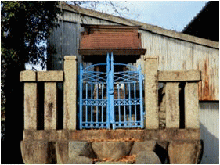 |
| 八幡宮 |
社 |
秋葉神社 |
|
|
秋葉神社からすぐに、長森細畑交差点で156号線を横断する。5分ほどすると復元された細畑一里塚 / 地蔵堂 と続く。南側の細畑一里塚の後ろに社がある。地蔵堂のあるところは伊勢道追分で、明治9年(1876年)造立の道標がある。正面に「伊勢
名古屋ちかみち 笠松兀一里」 左側面に「木曽路 せき 上有知 郡上 道」 右側面に「西京 加納兀八丁」と彫られている。右へ旧中山道を進むと、すぐ左手に八幡宮がある。5分ほどすると右手奥に社
/ 右手に秋葉神社 と続く。
|
|
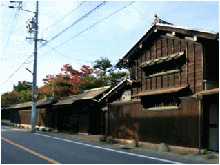 |
 |
秋葉神社から5分ほどすると、左手に名鉄・茶所駅がある。踏切を渡ると、すぐ左手に中山道加納宿 石柱がある。 |
| 町並み |
中山道加納宿 石柱 |
|
中山道69次 53番 加納(かのう)宿
所在地:岐阜県岐阜市
天保14年(1843年)中山道宿村大概帳
人口:2728人 家数:805 本陣:1 脇本陣:1 旅籠:35 |
|
| 古くより中山道の要衝として栄えてきた。慶長6年(1601年)岐阜城が廃城となり、天下普請として加納城が築城される。宿場は城下町としての役割も兼ね発展をした。宿場の東入口には6ヶ所の枡形道が設けられていた。文久元年(1861年)皇女和宮下向のとき宿泊、幕末には当分本陣(臨時本陣)が2ヶ所設置された。江戸時代は宿の町単位に秋葉神社が創建された。 |
|
 |
中山道加納宿 石柱からすぐ右手に、中山道加納宿 / 御鮨街道 石柱 がある。直進して西に進むのが旧中山道と旧岐阜街道(御鮨街道)の重複区間 /
左折して南に進むのが旧岐阜街道 になる。 |
| 中山道加納宿 / 御鮨街道 石柱 |
|
| [寄り道]ぶたれ坊 |
 |
中山道加納宿 / 御鮨街道 石柱 から左折して南へ進む。すぐ右手に、ぶたれ坊と茶所案内板 / 鏡岩濱之助造立の道標 / 鏡と彫られた円形石 がある。江戸時代の相撲力士二代目・鏡岩濱之助は土俵の外での素行が悪かったことを改心して、妙寿寺を創建した。ぶたれる為に等身大の木像を置いて、罪滅ぼしをした。また茶店を設けて旅人に茶を振舞ったと云われている。妙寿寺は廃寺となり、ぶたれ坊の像は岐阜駅南口に近い妙泉寺に移されている。道標には、正面に「東海道いせ路」
/ 右側面に「江戸木曽路」と彫られている。 |
| ぶたれ坊 |
|
| [参考]妙泉寺 |
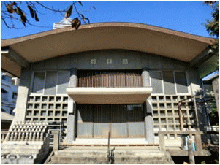 |
 |
 |
| 妙泉寺本堂 |
鬼子母神堂 |
由来の石柱 |
|
| 岐阜駅南口から187号線を南へ進む。岐阜駅南交差点の次の十字路を右折すると、右手に妙泉寺がある。岐阜駅南口から5分ほどのところである。本堂左手の鬼子母神堂前に“ぶたれ坊”由来の石柱がある。 |
|
 |
 |
 |
| 中山道加納宿 / 御鮨街道 石柱 |
中山道加納宿 石柱 |
「中山道 加納宿 八幡町」案内板 |
|
| 中山道加納宿 / 御鮨街道 石柱 まで戻り旧中山道に戻り西へ進むと、 すぐに十字路がある。北西側角に中山道加納宿 石柱 / 「中山道 加納宿 八幡町」案内板 がある。 |
|
| [寄り道]加納八幡神社 |
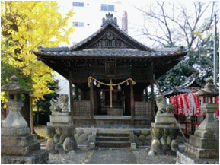 |
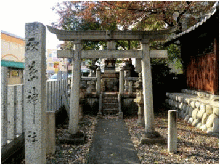 |
 |
| 加納八幡神社 |
秋葉神社 |
琴平神社 |
|
 |
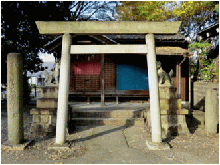 |
 |
| 厚見稲荷神社 |
厚見稲荷神社 |
塞神社 |
|
| 右折せずに直進すると、すぐ右手に加納八幡神社がある。文安2年(1445年)沓井城が築城されたとき、城の鬼門に位置する事から鬼門除けの神社として創建されたと云われている。天文7年(1538年)には既に廃城になったとされる。慶長6年(1601年)岐阜城は破却され、慶長7年(1602年)替わりに加納城が築城される。加納八幡神社は加納城の敷地にかかるため、加納城の鬼門除けとして現在地に移された。 境内社として、秋葉神社 / 琴平神社 / 厚見稲荷神社(2社) / 塞神社 がある。 |
|
 |
 |
 |
| 中山道加納宿 石柱 |
「中山道 加納宿 八幡町」案内板 |
道標 |
|
 |
 |
 |
| 側溝蓋 |
秋葉神社 |
中山道加納宿 石柱 |
|
 |
 |
 |
| 加納宿東番所跡 |
善徳寺 |
中山道加納宿 石柱 |
|
| 十字路まで戻り、旧中山道を北へ進む。ここから枡形道が始まり、すぐに新荒田川に架かる加納大橋を渡る。加納大橋の欄干に、大名行列のレリーフが埋め込まれている。すぐのT字路南西側に中山道加納宿
石柱 / 北東側に明治18年(1885年)造立の「右 谷汲 岐阜」「左 西京」道標 がある。左折すると、すぐ右手に秋葉神社がある。この辺りから側溝蓋に“中山道
御鮨街道”の刻印が見られる様になる。すぐの岐阜東通りを横断すると、すぐ右手に中山道加納宿 石柱 / 通行手形など見せて宿に入る加納宿東番所跡
がある。左折するとすぐの突き当りに善徳寺 / 門前に中山道加納宿 石柱 があり、右折する。さらに十字路手前右手に、中山道加納宿 石柱がある。 |
|
 |
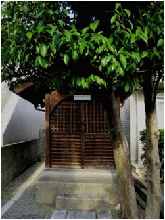 |
 |
| 中山道加納宿 石柱 |
柳町秋葉三尺坊 |
古民家 |
|
 |
 |
 |
| 専福寺 |
秋葉神社 |
道標 |
|
|
十字路を横断すると、右手に中山道加納宿 石柱と柳町秋葉三尺坊がある。この通りの側溝蓋には“中山道 御鮨街道”の刻印がある。すぐ左手に、織田信長朱印状 / 豊臣秀吉朱印状 / 池田輝政制令状など戦国期の文書が残っている専福寺 / 右手に秋葉神社 と続く。すぐの十字路は、中山道と岐阜道の分岐点で交通の要衝であったところ。十字路の北西側に、江戸中期(1750年頃)造立の道標がある。正面に「左 中山道」右側面に「右
ぎふ道」と彫られている。
|
|
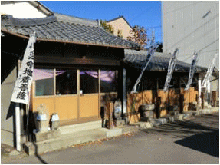 |
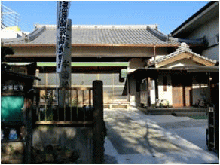 |
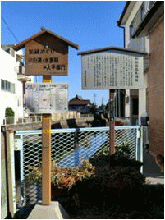 |
| 地蔵堂 |
水薬師寺 |
高札場跡 |
|
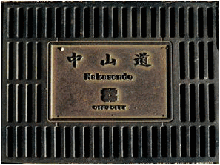 |
 |
 |
| 側溝蓋 |
中山道加納宿 石柱/ 加納城跡 石柱 |
大手門跡 |
|
|
旧中山道は十字路を左折して南西へ進む。すぐの清水川に架かる“ひろい橋”手前を右折すると、すぐ右手に地蔵堂 / 水薬師寺 と続く。“ひろい橋”を渡ると、左手に高札場跡がある。この通りの側溝蓋には”中山道”の刻印がある。すぐの加納大手町交差点の歩道橋前に、中山道加納宿 石柱 / 加納城跡 石柱 / 加納城大手門跡 がある。
|
|
|
|
| [寄り道]加納城 |
|
 |
 |
 |
| 加納城石垣 |
地蔵寺 |
盛徳寺 |
|
| 加納大手町交差点を直進して南へ5分ほどすると、突き当りに慶長7年(1602年)築城の加納城がある。文安2年(1445年)斎藤利永によって沓井城が築城されたのが始まり。天文7年(1538年)には廃城となっている。慶長6年(1601年)岐阜城が廃城となり、天下普請として加納城が築城される。加納藩に移封された奥平信昌は天正3年(1575年)長篠の戦いのとき、武田勝頼軍を相手に三河国・長篠城を守り抜いた武将。後に徳川家康の娘・亀姫と結婚している。建材は主に岐阜城のものが用いられ、岐阜城天守を二ノ丸御三階櫓として利用したと云われている。明治5年(1872年)廃城令により建物は破却、城門などは売却された。石垣と堀跡が残る。加納城から道なりに西へ進む。157号線を右折して北へ進む。加納旭朝日町3交差点を左折して西へ、十字路を左折して南へ進む。左手の路地に“おまかせ地蔵”の幟(のぼり)が立つ地蔵寺がある。さらに南へ進むとすぐ右手に、三河にあった奥平家の菩提寺・増瑞寺を移した盛徳寺がある。奥平信昌・亀姫の墓があり、山門前には岐阜市による案内看板がある。しかし境内に入ることはできない。加納城から盛徳寺までは10分ほど。 |
|
|
|
 |
 |
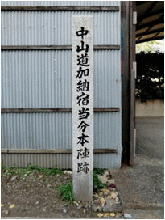 |
| 旧加納町役場 |
二文字屋 |
当分本陣跡 |
|
| 旧中山道は、加納大手町交差点手前を右折して北西へ進む。ここで枡形道が終わる。すぐ左手に旧加納町役場がある。黒ずんでいるのは空襲を避けるため黒く色を塗った跡で、戦後進駐軍に接収されていた。5分ほどすると、左手に元和6年(1620年)旅籠として創業した鰻料理・二文字屋がある。左甚五郎が宿賃がわりに欄間に彫った“月夜に川原で餅をつくウサギ”は、店の商標となっている。すぐ右手に当分本陣跡がある。文久元年(1861年)皇女和宮の下向の翌年に幕府は参勤交代の制度を大幅に緩和したため、江戸に人質として留め置かれた大名の妻子が帰藩した。各宿場の本陣が対応しきれなくなり、期間限定で当分の間宿場の有力者宅を臨時の本陣と定めたのが当分本陣。 |
|
 |
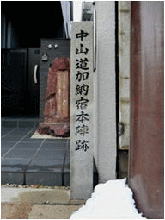 |
 |
| 中山道加納宿道標 |
本陣跡 |
皇女和宮御仮泊所跡 |
|
 |
 |
 |
| 皇女和宮句碑 |
西問屋跡 |
脇本陣跡 |
|
| 当分本陣跡からすぐの信号のない157号線(加納中通り)を横断する。右手に中山道加納宿道標 / 右手に本陣跡 / 右手に西問屋跡 / 右手に脇本陣跡 と続く。本陣跡碑の左側面に、皇女和宮御仮泊所跡と彫られている。後ろに皇女和宮句碑「遠ざかる 都としれば 旅衣 一夜の宿も たちうかりけれ」がある。 |
|
 |
 |
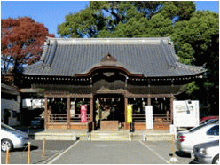 |
| 加納宿中山道 石柱 |
加納天満宮鳥居 |
加納天満宮拝殿 |
|
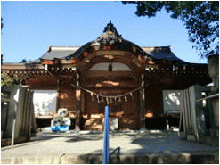 |
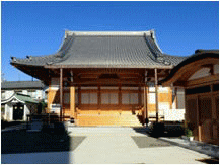 |
脇本陣跡からすぐの十字路左手に、加納宿中山道 石柱がある。旧中山道は直進する。右折すると突き当りに、加納天満宮 / 東側に雲端寺 がある。加納天満宮は文安2年(1445年)斎藤利永によって沓井城が築城されたとき、城の守護神として創建される。 |
| 加納天満宮幣殿 |
雲端寺 |
|
 |
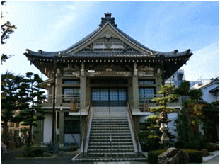 |
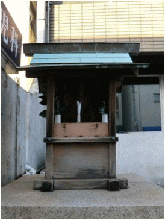 |
| 脇本陣跡 |
信浄寺 |
社 |
|
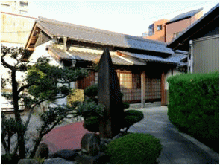 |
旧中山道に戻り西へ進むと、すぐ右手に脇本陣跡がある。次の十字路を右折すると、すぐ左手に信浄寺がある。旧中山道に戻り西へ進むと、すぐ右手に社 /
すぐに加納栄町通りと交差する。旧中山道は直進する。右折するとすぐ右手に欣浄寺、突当りにJR岐阜駅がある。 |
| 欣浄寺 |
|
|
|
| [寄り道]亀姫の墓 |
|
 |
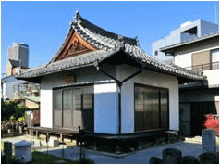 |
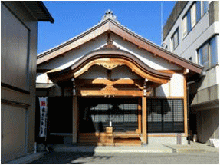 |
| 秋葉神社 |
久運寺 |
玉性院 |
|
| 岐阜駅南交差点の1本南側の道を東へ進む。突き当りに秋葉神社がある。突き当りを右折、すぐに左折する。さらにすぐの突き当りを左折すると、左手に文明元年(1469年)創建の久運寺がある。寛文5年(1665年)お茶壺道中の本陣を命ぜられる。住職・玉葉和尚は権威の横暴に反抗してこれを拒否、追放された逸話がある。道を戻り、左折したところを通り過ぎ南へ進む。突き当りを左折して東へ進む。加納天満宮鳥居前を過ぎると、左手に玉性院がある。 |
|
 |
 |
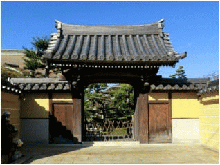 |
| 愛宕神社 |
円明院 |
光国寺 |
|
 |
玉性院から東へ、すぐの157号線(加納中通り)を横断する。すぐに左折して北へ進むと、左手に愛宕神社 / 円明院 と続く。さらに北へ進み、突き当りを左折して157号線(加納中通り)を右折して北へ 清水川に架かる天満橋を渡る。右斜め方向にある名鉄のガードを潜り東へ進むと、左手に慶長19年(1614年)創建の光国寺がある。ここにも亀姫の墓があるがここも盛徳寺同様、境内に入ることはできない。亀姫の墓は、右手の鉄柵の隙間から見ることができる。 |
| 亀姫の墓 |
|
|
|
|
|
| [寄り道]金神社 |
|
 |
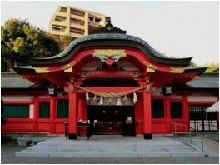 |
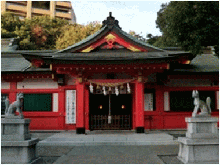 |
| 金神社鳥居 |
金神社拝殿 |
金祥稲荷神社 |
|
| JR岐阜駅北口から54号線(金華橋通り)を北へ15分ほど進むと、右手に金(こがね)神社がある。成務天皇5年(135年)朝廷より国造として派遣された物部臣賀夫良命(もののべのおみかぶらのみこと)が国府をこの地に定め、創建されたと云われている。古くから金運 / 財運に利益があるとされる。 |
|
|
|
 |