| 中山道69次 No.25 南木曽駅-(約13km)-馬篭バス停 |
|
| 2012年 7月18日(水)08:15 晴 |
|
| 南木曽駅 |
→ |
そでふりの松 |
→ |
かぶと観音 |
→ |
上久保一里塚 |
→ |
妻籠城跡 |
→ |
島崎本陣跡 |
→ |
おしゃごじさま |
→ |
倉科祖霊社 |
→ |
一石栃白木改番所跡 |
→ |
馬篭峠 |
→ |
馬篭宿本陣跡 |
→ |
阿弥陀堂 |
→ |
馬篭バス停 |
|
|
 |
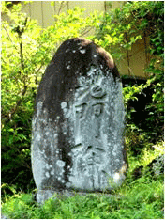 |
 |
| 町並み |
鬼門除 |
中山道石柱 |
|
 |
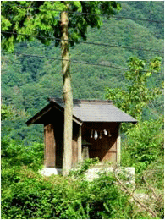 |
JR中央線・南木曽駅から左折して線路沿いに南へ進む。左手の跨線橋でJR中央本線を越える。左の坂を登り、右折して旧中山道を南へ進む。すぐ左手に鬼門除と彫られた石塔
/ 左手に中山道石柱 / 右手にD51 351が置かれているSL広場 / 「妻籠宿3.1km 南木曽駅500m」道標 / 右手の谷を挟んだ丘に秋葉神社
と続く。SL広場は、中央本線旧線の三留野駅跡。 |
| D51 351 |
秋葉神社 |
|
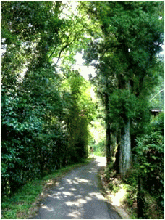 |
 |
 |
| 並木道 |
常夜燈 |
そでふりの松 |
|
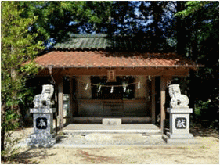 |
 |
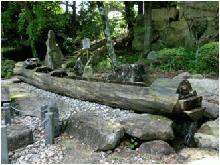 |
| 神明神社 |
かぶと観音 |
水舟 |
|
|
SL広場から10分ほどすると、右手に常夜燈 / 左手にそでふりの松 / 右手に神明神社 / 神明神社右手の石段を下るとかぶと観音 と続く。ふりそでの松は、木曽義仲が弓を引くのに邪魔になった松を巴御前が袖を振って倒したと云われている。木曽義仲は平家打倒の旗揚げのとき、木曽谷南の抑えとして妻籠に城を築いた。かぶと観音はその鬼門にあたるこの地に、兜に納めていた十一面観音を祠に祀ったのが起こりと云われている。かぶと観音境内には、大きな水舟や休息所がある。
|
|
 |
 |
 |
| 道標 |
神号碑(源氏光明院帝塚大明神) |
石畳の坂 |
|
 |
 |
 |
| せん澤道標 |
上久保一里塚 |
良寛歌碑 |
|
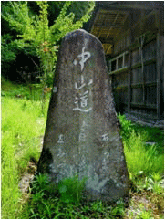 |
 |
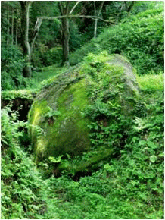 |
| 中山道くぼはら道標 |
中山道蛇石道標 |
蛇石 |
|
| かぶと観音から旧中山道に出ると、すぐに道標「北渡へ かんのん 東上り かんのん 南 前 旧道 つまご 西下り 國道」 / 「JR南木曽駅1.3km 妻籠宿2.4km」道標
/ 右手に神号碑(源氏光明院帝塚大明神)と続く。5分ほどすると、せん澤道標「左 なぎそ駅へ 下り 国道へ 右 妻籠宿へ」 / 左手に上久保一里塚
/ 左手に良寛歌碑「この暮れの もの悲しきにわかくさの 妻呼びたてて 小牡鹿鳴くも」と案内板 / 中山道くぼはら道標「左 みどの 右 つまご」
/ 「JR南木曽駅1.9km 妻籠宿1.8km」道標と続く。5分ほどすると、中山道蛇石道標「下り道 旧道 左 志ん道 右 つまご宿”と左手に蛇石(へんびいし)がある。 |
|
 |
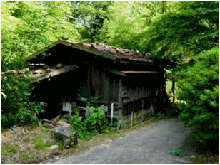 |
| 城山茶屋跡 |
|
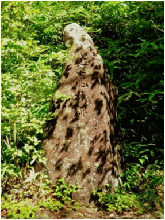 |
| 右:妻籠城総堀 |
妻籠城跡碑 |
|
| 中山道蛇石道標から、中世の中山道は沢沿いに上っていた。元禄16年(1703年)道の付け替え工事が行われ、妻籠城総堀を通る現在の道になった。5分ほどすると分岐があり、右へ妻籠城総堀を進む。すぐ右手に城山茶屋跡 / 三差路に「左 飯田 中 妻籠宿 右 妻籠城」標識 と続く。妻籠宿方面に進むと、すぐに道標を兼ねた妻籠城跡碑と妻籠城跡案内看板がある。 |
|
中山道69次 42番 妻籠(つまご)宿
所在地:長野県木曽郡南木曽町
天保14年(1843年)中山道宿村大概帳
人口:418人 家数:31 本陣:1 脇本陣:1 旅籠:31 |
|
| 蘭川(あららぎがわ)東岸に位置、旧中山道と伊奈街道の交わる交通の要衝だった宿場。馬篭峠を越える馬篭宿と合わせて、木曽路の観光名所になっている。明治25年(1892年)馬籠峠を迂回、馬車が通行できる19号線が開通する。全国の伝統的な町並みが姿を消してゆくなか、景観保全活動に取り組んだ。国の重要伝統的建造物群保存地区の最初の選定地の一つに選ばれている。 |
|
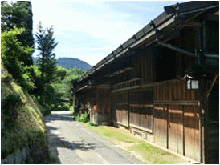 |
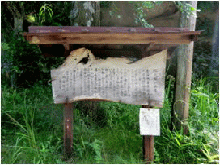 |
 |
| 町並み |
鯉ヶ岩案内板 |
口留番所跡 |
|
 |
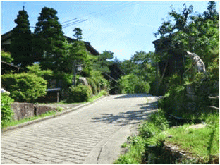 |
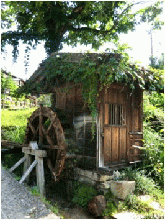 |
| 高札場 |
街道風景 |
水車小屋 |
|
| 妻籠城跡碑から10分ほどすると、左手に「JR南木曽駅3.2km これより妻籠宿の町並み」道標がある。すぐに左手に鯉ヶ岩案内板 / 口留番所跡
/ 地蔵橋を渡ると右手に復元された高札場 / 左手に水車小屋 と続く。鯉ヶ岩は案内板の後ろにある岩らしいが、はっきり解らない。大きな鯉の形をした岩であったが、明治24年(1891年)地震で頭の部分が落ちて形が変った。口留番所は、戦国時代から17世紀まで置かれていた関所。 |
|
 |
 |
 |
| 書状集箱(郵便ポスト) |
奥谷脇本陣跡 |
町並み |
|
 |
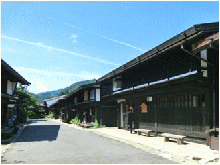 |
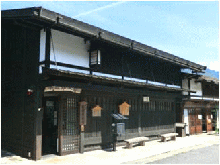 |
| 島崎本陣跡 |
町並み |
妻籠郵便局 |
|
| 水車小屋から5分ほどすると、右手に南木曽町博物館と歴史資料館になっている奥谷脇本陣跡 / 左手に妻籠宿ふれあい館 / 平成7年(1995年)復元された島崎本陣跡
/ 妻籠郵便局を兼ねた郵便資料博物館と続く。奥谷脇本陣の建物は、明治10年(1877年)築の重文。島崎本陣は、島崎藤村の母の生家。 |
|
 |
 |
 |
| 町並み |
常夜燈 |
石畳の坂 |
|
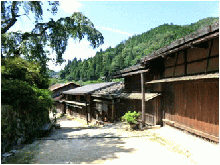 |
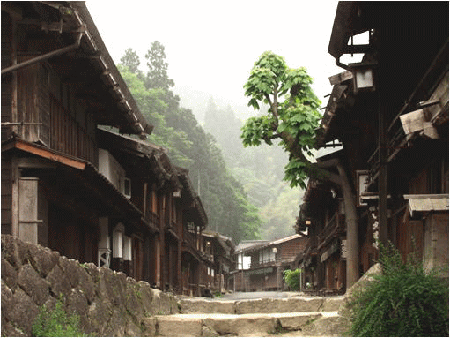 |
| 町並み |
|
 |
| 町並み |
寺下の町並み |
|
| 妻籠郵便局から5分ほどすると、右手に常夜燈がある。すぐに石畳の坂を下る。枡形があり、寺下の町並みに入る。 |
|
 |
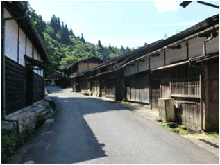 |
 |
| 馬頭観音 |
町並み |
おしゃごじさま / 不明の石仏2基 |
|
 |
 |
 |
| 地蔵 |
妻籠宿看板 |
中山道道標 |
|
| 寺下の町並みを5分ほど進むと、左手に馬頭観音 / 左手におしゃごじさま / 左手に地蔵と続く。おしゃごじさまは御左口(みさぐち)神を祀る、縄文時代から存在していたと云われる土俗信仰。石や樹木を依代とする神であったとされるが、謂れは解っていないと云う。地蔵からすぐに256号線と交差する。横断した左手の駐車場に妻籠宿看板がある。旧中山道は直進、左手に中山道道標「左
志ん道 いいだ 右 旧道 まごめ」がある。馬篭峠まではほとんど上りの連続となる。妻籠宿の標高は430m / 馬篭峠の標高は801mで、比高差371mを登ることになる。 |
|
 |
 |
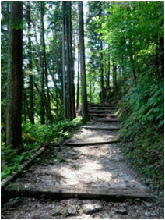 |
| 中山道はしば邑道標 |
中山道大島道標 |
山道 |
|
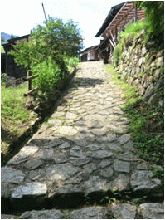 |
 |
 |
| 石畳の坂道 |
大妻籠 |
弘法大師石塔 |
|
 |
 |
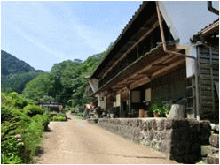 |
| 大妻籠看板 |
中山道大妻籠道標 |
町並み |
|
| 妻籠宿看板から5分ほどすると、明治14年(1881年)造立の中山道はしば邑道標「左 旧道 つまご 右 志ん道」がある。橋場は明治25年(1892年)まで、旧中山道と飯田街道の追分だったところ。すぐに中山道大島道標「左
志ん道 右 旧道」 / 「妻籠宿1.2km 馬篭宿6.5km」道標と続く。10分ほどすると、左手に明治36年(1903年)造立の弘法大師石塔
/ 左手に大妻籠看板 / 中山道大妻籠道標「左 志ん道 右 旧道」 / 「妻籠宿1.8km 馬篭宿5.9km」道標 と続く。 |
|
 |
 |
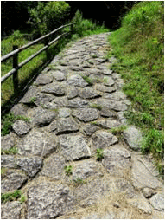 |
| 中山道庚申塚 |
どうがめ澤道標 |
石畳の坂道 |
|
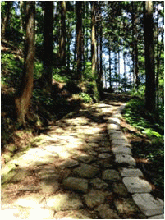 |
 |
 |
| 石畳 |
谷集落 |
中仙道道標 |
|
 |
中山道大妻籠道標から5分ほどすると、7号線に合流する手前左手に中山道庚申塚「左 旧道 右 志ん道」がある。7号線を右折すると、庚申塚バス停がある。すぐ左手にどうがめ澤道標「下り谷を經て馬籠峠へ」と「馬篭宿5.4km」道標があり、石畳の坂道を登る。15分ほどすると谷集落に入る。すぐに中仙道道標
/ 左手に倉科祖霊社と続く。天正14年(1586年)松本城主・小笠原貞慶の重臣・倉科七郎左衛門朝軌は、小笠原貞慶の命を受けて大阪の豊臣秀吉への使いに行った。帰途にここで従者30余人とともに地元土豪たちによって全滅させられた。 |
| 倉科祖霊社 |
|
 |
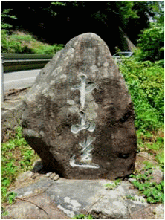 |
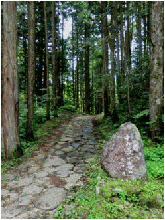 |
| 前方に橋が見える石畳 |
中山道道標 |
中山道一石栃口道標と石畳 |
|
 |
 |
| 一石栃白木改番所跡 |
|
 |
| 立場茶屋跡水舟 |
立場茶屋跡 |
|
|
倉科祖霊社から10分ほどすると、男滝女滝への分岐がある。ここから一石栃白木改番所跡付近まで、沢に架かる木橋を次々と渡る。またところどころに熊鈴がぶら下がっている。分岐から10分ほどすると「妻籠宿3.6km 馬篭宿4.1km」道標があり、車道と合流する。すぐに右手の木橋を渡る。15分ほどすると中山道道標があり、車道と交差をする。横断すると中山道一石栃口道標があり、石畳の坂道を進む。10分ほどすると右手に一石栃白木改番所跡
/ 右手に立場茶屋跡の牧野家と続く。一石栃は妻籠宿と馬篭宿の中間に位置しており、下り谷にあった白木改番所をここに移した。尾張藩は直轄で木曽山林の保護を図り、抜荷の取り締りを強化のため白木改めの番所を設けた。1軒残る立場茶屋跡の牧野家は、江戸時代後期築。水舟で冷やされたキュウリをご馳走になる。昼食を摂る。
|
|
 |
 |
立場茶屋跡から木橋を次々と渡り、急な坂道を登る。立場茶屋跡から20分ほどすると、右旧中山道道標がある。すぐに7号線と合流、標高801mの馬篭峠に辿り着く。馬篭峠子規句碑「白雲や青葉若葉の三十里」がある。この峠で長野県木曽郡南木曽町から岐阜県中津市に入る。 |
| 右旧中山道 |
馬篭峠子規句碑 |
|
 |
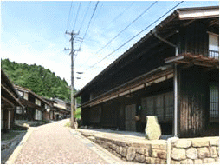 |
 |
| 熊野神社鳥居 |
町並み |
峠之御頭頌徳碑 |
|
 |
 |
 |
| 中山道道標 |
十返舎一九歌碑 |
中山道道標 |
|
 |
 |
| 双体道祖神 / 不明の石塔2基 |
|
 |
| 石畳の坂 |
中山道水車塚道標 |
|
 |
 |
 |
| 中山道道標 |
中山道道標 |
右中仙道道標 |
|
| 馬籠峠から7号線を進む。すぐに右折して坂を下ると、左手に熊野神社鳥居 / 「妻籠宿5.8km 馬篭宿1.9km」道標と続く。5分ほどすると、左手に峠之御頭頌徳碑
/ 「妻籠宿61km 馬篭宿1.6km」道標 / 中山道道標 / 「妻籠宿6.3km 馬篭宿1.5km」道標 / 右手に十返舎一九歌碑「渋皮の剥(む)けし女は見えねども
栗のこはめしここの名物」と続く。5分ほどすると車道を横断、「妻籠宿6.4km 馬篭宿1.3km」道標 / 「妻籠宿6.5km 馬篭宿1.2km」道標と続き左折する。横断すると「妻籠宿6.7km 馬篭宿1.0km」道標
/ 中山道道標があり、石畳の坂道を下る。左手に田んぼがあるが、妙に傾斜している様に見える。目の前で見ても同様で、メンバーの水準器付きカメラで確認する。目の錯覚で、田んぼは水平であった。すぐ左手に双体道祖神
/ 不明の石塔2基 / 中山道水車塚道標と続く。車道を横断すると中山道道標がある。5分ほどすると、「妻籠宿7.1km 馬篭宿0.6km」道標
/ 中山道道標 / 右中仙道道標と続く。 |
|
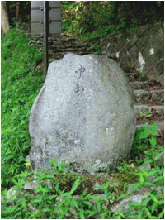 |
 |
| 中山道道標 |
| |
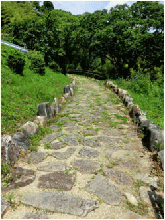 |
| 石畳の道 |
展望台からの恵那山(海抜2192m) |
|
 |
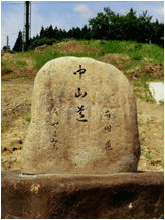 |
 |
| 双体道祖神 |
中山道道標 |
高札場 |
|
| さらに中山道道標があり、石段を登る。下って来た油断からか、ここからの登りはきつく感じる。「馬篭宿300m」道標があり、さらに石段を登る。石畳の道を進む。旧中山道は直進するが、左手に広い展望台がある。正面が北で、海抜2192mの恵那山が見える。広場から馬篭宿方向へ進むと、すぐに旧中山道と合流する。右手に双体道祖神
/ 「妻籠宿7.6km 馬篭宿100m」道標 / 右手に中山道道標「左 やまみち 右 旧道」 と続く。坂を下るとすぐ左手に復元された高札場がある。 |
|
中山道69次 43番 馬篭(まごめ)宿
所在地:岐阜県中津川市
天保14年(1843年)中山道宿村大概帳
人口:717人 家数:69 本陣:1 脇本陣:1 旅籠:18 |
|
| 木曽11宿の最後の宿場。山の尾根の全長600mの急傾斜面にある。明治28年(1895年)と大正4年(1915年)の大火で、建物はすべて消失する、石畳の敷かれた坂に沿う様に、復元された建物が並ぶ。二階部分が近代的な大きさになっているのが悔やまれる。妻籠宿と合わせて、木曽路の観光名所になっている。旧本陣は島崎藤村の生家で、藤村記念館がある。長野県木曽郡山口村に属していたが、平成17年(2005年)の越県合併により岐阜県中津川市に編入された。 |
|
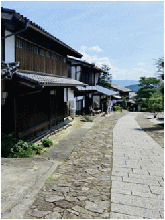 |
 |
 |
| 町並み |
脇本陣跡 |
本陣跡 |
|
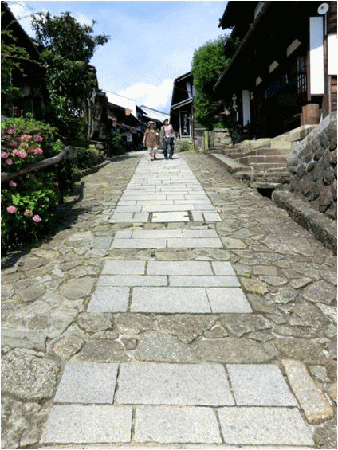 |
 |
| 枡形 |
|
 |
| 町並み |
車坂 |
|
 |
 |
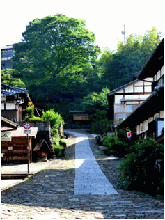 |
| 双対道祖神 |
阿弥陀堂 |
馬籠宿を振り返る |
|
| 高札場からすぐに、陣場バス停のある7号線と交差する。直進して馬篭宿に入り、近代的な石畳の坂を下る。右手の脇本陣跡に馬篭脇本陣資料館 / 右手の本陣跡に藤村記念館と続く。5分ほどすると枡形があり、旧中山道は右へ進む。左の車坂を進むと、右手に常夜燈がある。すぐに合流する手前、車坂の左手に双対道祖神がある。突き当りに阿弥陀堂があり、道は大きく右へ曲がる。すぐに7号線と交差、右折して馬篭バス停から中津川駅へ向かう。 |
|
 |