| 中山道69次 No.24 野尻駅-(約11km)-南木曽駅 |
|
| 2012年 6月 6日(水)09:40 晴 |
|
| 野尻駅 |
→ |
下在一里塚跡 |
→ |
熊野神社 |
→ |
十二兼駅 |
→ |
南寝覚 |
→ |
桃介橋 |
→ |
南木曽駅 |
|
|
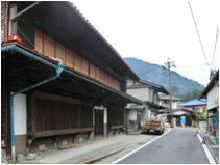 |
 |
 |
| 町並み |
津島社と祇園社 |
西のはずれ(南西側から撮影) |
|
| JR野尻駅より東へ進む。すぐの突き当りに旅館庭田屋があり、右折して旧中山道を南西へ進む。すぐ左手に津島社と祇園社の社がある。すぐに野尻宿西のはずれになり、左手に屋号が“はずれ”の西村家がある。宿場東はずれから西はずれまでの約1km間、道を7曲がりにして外敵を防いでいた。 |
|
 |
 |
| 下在一里塚跡 |
石塔群 |
|
 |
西のはずれからすぐに二反田橋を渡る。5分ほどすると、左手に一里塚跡がある。すぐに道標があり、右へ進む。さらに5分ほどすると道標があり、右へ進み
JR中央本線を潜る。すぐに道標があり左へ進むと、左手に石塔群 / 左手に妻神社と続く。
|
| 妻神社 |
|
 |
妻神社からすぐに道標があり、左へ進む。5分ほどすると旧第3中仙道踏切を渡り、右折する。5分ほどすると第13中仙道踏切、さらに5分ほどすると第14中仙道踏切を渡る。旧中山道は第13中仙道踏切手前からJR中央本線東側の勝井坂を通り、八人石へ通じていたが、通行はできなくなっている。第14中仙道踏切から5分ほどすると左手の生垣に石仏がある。 |
| 石仏 |
|
 |
石仏から10分ほどすると、19号線に突き当り右折する。すぐ八人石沢の橋を渡り、19号線を横断して反対側の沢沿いの坂を上る。坂の突当たりでターンして坂を上る。 |
| 19号線〜八人石沢の橋〜沢沿いの坂 |
|
 |
 |
 |
| 石塔群 |
廿三夜塔 |
常夜燈 |
|
 |
 |
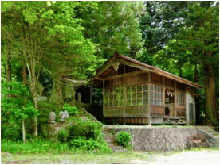 |
| 石塔群 |
神号碑(水神) |
熊野神社 |
|
|
坂を上ると、左手に石塔群 / 左手にの丘に廿三夜塔 / 左手に常夜燈 / 左手の丘に石塔群と続く。Y字路を右へ下ると、すぐ左手に神号碑(水神)
/ 左手に熊野神社と続く。
|
|
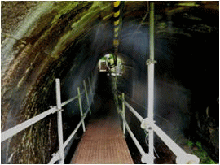 |
 |
熊野神社からすぐの十二兼北交差点から左折して草道を下る。すぐに19号線とJR中央本線を、水路トンネルに仮設の歩道で潜る。 このルートなかった
以前は十二兼北交差点で19号線を横断、危険にもJR中央本線を渡っていた。トンネルから5分ほどすると、左手に十二兼駅がある。上りホーム側に、十二兼駅開業二十周年記念碑が見える。下りホームの待合室で休憩する。
|
| 水路トンネルに仮設の歩道 |
十二兼駅開業二十周年記念碑 |
|
 |
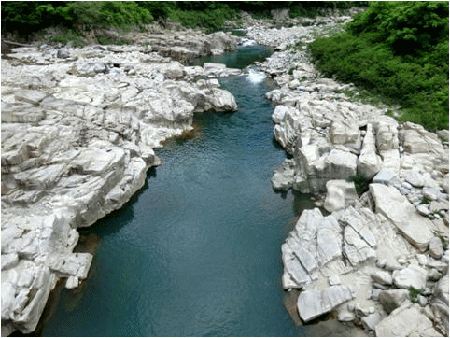 |
| 石仏 |
|
 |
| 八劔神社 |
南寝覚 |
|
| 十二兼駅から10分ほどすると、左手に石仏が2基並んでいる。すぐ右手に柿其橋がある。ここからの眺望は素晴らしく、南寝覚と呼ばれている。柿其橋を渡ると、右手に八劔神社がある。 |
|
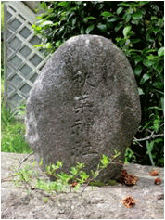 |
 |
| 神号碑(秋葉神社) |
|
 |
| 不明の石塔 |
19号線と木曽川(羅天橋から5分ほどのところ) |
|
|
柿其橋を東岸まで戻り、南へ進むとすぐ。右手に神号碑(秋葉神社)がある。すぐに柿其入口交差点で19号線に合流する。10分ほどすると左手に不明の石塔、5分ほどすると羅天橋を渡る。この辺りに断崖の下を通る難所、羅天の桟橋があった。
|
|
 |
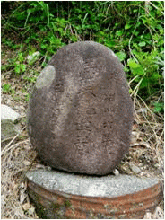 |
 |
| 19号線からの分岐 |
明治26年造立の馬頭観音 |
馬頭観音 |
|
|
羅天橋から10分ほどすると、与川側道橋を渡る。10分ほどすると、19号線から左へ進む。5分ほどすると左手に明治26年(1893年)造立の馬頭観音がある。すぐにJR中央本線を潜ると、左手に馬頭観音がある。
|
|
|
中山道69次 41番 三留野(みどの)宿
所在地:長野県木曽郡南木曽町
天保14年(1843年)中山道宿村大概帳
人口:594人 家数:77 本陣:1 脇本陣:1 旅籠:32
|
|
|
明治15年(1881年)の大火で多くの建物が焼失する。鉄道が開通したため、町の賑わいは駅周辺になっている。三留野宿の名前は、木曽氏の館があって御殿(みどの)と呼ばれたことに由来しているといわれている。三留野付近は標高1500mの高い山々が木曽川べりまで迫っている。
|
|
 |
 |
 |
| 町並み |
町並み |
常夜燈 / 社 |
|
|
馬頭観音から5分ほどすると、道標があり階段を下る。下り切ると左手に享和3年(1803年)造立の常夜燈と社がある。
|
|
 |
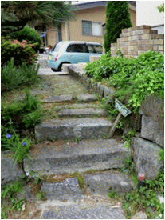 |
常夜燈と社からすぐに264号線と合流、すぐ左手に南木曽小学校への石段がある。 階段の手前左手に小さな中山道標識があり、先ずはそこの石段を登る。小学校への石段を数段上り、さらに右手の石段を登る。ここにも標識があるが、資料では民家の庭を通るらしい。小学校への石段を下り、264号線を進む。次を左折して坂を登ると、民家の庭からの旧中山道に突き当り右折する。迂回しても5分と掛からない。 |
| 左手の石段を登る |
民家の庭への石段 |
|
|
旧中山道を道標に従い5分ほど進むと。ふたたび264号線と合流する。
|
|
|
|
| 寄り道 |
 |
 |
| 桃介橋と鯉のぼり |
|
 |
| 社 |
桃介橋 |
|
| 264号線との合流からすぐに、264号線はJR中央本線を陸橋で越え坂を下る。分岐する三角地に「妻籠宿4.2km 三留野宿0.5km 与川経由野尻駅15.6km」道標があり、旧中山道は直進して南へ進む。JR中央本線を陸橋で越え坂を下ると、すぐ右手に南木曽郵便局がある。その先を右折して坂を下り19号線を越える。木曽川東岸にある公園で、桃介(ももすけ)橋を見ながら昼食を摂る。桃介橋下に社がある。264号線まで戻り南へ進むと、桃介橋に通じる道がある。桃介橋は、大正11年(1922年)大同電力(現:関西電力)が読書発電所の建設資材運搬路として木曽川に架けられた橋。4径間の吊橋
/ 橋桁トラスは木造 / 橋長は247.762mとなっている。老朽化が進み、平成5年(1993年)に修理復元される。平成6年(1994年)読書発電所施設の一部として、重文に指定される。福沢諭吉の婿養子にあたり、大同電力の社長を務めていた電力王と云われた福沢桃介
に因んで命名される。 |
|
|
|
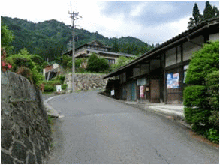 |
 |
| 町並み |
|
 |
| 園原先生碑 |
貯木場と桃介橋 |
|
|
「妻籠宿4.2km 三留野宿0.5km 与川経由野尻駅15.6km」道標まで戻り、旧中山道を南へ進む。10分ほどすると、右手の眼下に貯木場と桃介橋が見える。5分ほどすると、左手に天明元年(1781年)造立の園原先生碑がある。園原旧富は三留野出身の江戸時代中期の国学者。三留野・東山神社の神職を務め、,木曾谷を踏査して「木曾古道記」を著した。
|
|
| 園原先生碑からすぐにY字路があり、旧中山道は左へ進む。右へ進み坂を下ると、右手にある跨線橋でJR中央本線を越える。線路沿いに北へ進むと、JR南木曽駅に至る。 |
|
 |