| 中山道69次 No.16 塩尻下大門交差点-(約14km)-贄川(にえかわ)駅 |
|
| 2011年12月13日(火)08:00 晴 |
|
| 塩尻駅 |
→ |
下大門交差点 |
→ |
大門神社 |
→ |
平出一里塚 |
→ |
肱懸松 |
→ |
萬福寺 |
→ |
日出塩の青木 |
→ |
長泉院 |
→ |
鶯着寺 |
→ |
贄川駅 |
|
|
 |
 |
 |
| 大門神社 |
耳塚神社 |
奉納された素焼きの皿やおわん |
|
 |
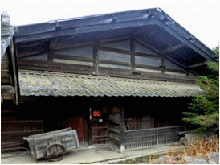 |
 |
| 双体道祖神 |
古民家 |
長屋門をイメージした様な建物 |
|
|
|
|
JR塩尻駅から南へ道なりに進む。15分ほどすると下大門交差点があり、右折して旧中山道を西へ進む。すぐ右手に大門神社 / 右手に耳塚神社 / 右手に双体道祖神
と続く。耳塚神社は天文17年(1548年)武田信玄と小笠原長時の桔梗ヶ原合戦で討死した将兵の耳を葬ったところと云われている。明治29年(1896年)塚に祠を建て、2本の剣を御神体として祀った。耳の形に似た素焼きの皿やおわんに穴を開けて奉納すると、耳の聞こえが良くなると云われている。左手に長屋門をイメージした様な建物がある。
|
|
 |
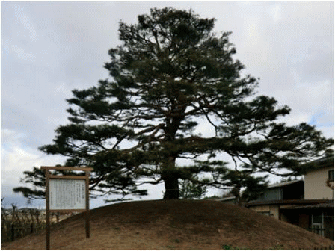 |
| 平出一里塚(南塚) |
平出一里塚(北塚) |
|
|
|
双体道祖神から5分ほどすると、JR中央本線のガードを潜る。さらに5分ほどすると、左手に平出一里塚(南塚)がある。北塚は右手の住宅に隠れている。
|
|
 |
 |
 |
| 果樹園 |
分岐 |
洗馬宿案内標識 |
|
|
平出一里塚からすぐ右手に“国史跡 平出遺跡”の案内看板がある。縄文時代から平安時代にかけての大集落跡で、古墳時代(約1300年前)の竪穴住居が復元されている。10分ほどすると、JR中央本線第1中仙道踏切を渡る。5分ほど果樹園が広がるのどかな道を進むと、右手に長野県中信農業試験場がある。さらに5分ほどすると中仙道一里塚交差点で19号線に突き当り、左折する。10分ほどするとガソリンスタンド手前に左への分岐があり、舗装されていない道を進む。5分ほどすると突当りを右折、平出歴史公園交差点で19号線と交差する。直進して304号線を進むと、すぐ右手に洗馬宿案内標識がある。
|
|
中山道69次 31番 洗馬(せば)宿
所在地:長野県塩尻市
天保14年(1843年)中山道宿村大概帳
人口:661人 家数:163 本陣:1 脇本陣:1 旅籠:29 |
|
|
慶長19年(1614年)中山道のルート変更に伴い、塩尻宿 / 本山宿とともに設置された宿場。中山道から善光寺街道が分岐、西国から善光寺への往来で賑わった。街道を通行する伝馬の荷物の重量を検査するために、荷物貫目改所が置かれた。古くは洗場とも記されていた。宿場成立当初から火災が多く、昭和7年(1932年)の大火で宿場の大部分が焼失している。治承4年(1180年)平氏追討の令旨を出され、木曽義仲も挙兵する。強行軍で疲れ果てた義仲の馬を湧く清水で洗ったところ、元気になったと云われている。この故事から“洗馬”と名付けられたと云われている。
|
|
 |
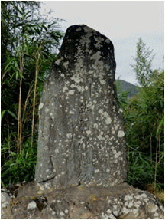 |
 |
| 肱懸松 |
細川幽斎肱懸松碑 |
肱懸松跡の標柱 |
|
|
304号線の相生坂と呼ばれていた坂を下ると、右手に“洗馬の肘松 日出塩の青木 お江戸屏風の絵にござる”と歌われた肱懸松(ひじかけまつ)と細川幽斎肱懸松碑がある。“肱懸けて しばし憩える松陰に たもと涼しく 通う河風”と細川幽斎が詠んだと云われている。かつての松は少し先にあった。すぐ右手に旧中仙道の標識があり、細い道を右へ下るとすぐ右手に肱懸松跡の標柱がある。
|
|
 |
肱懸松跡の標柱からすぐ右手に、安政4年(1857年)造立の常夜灯がある。中山道と善光寺街道の分去れで、左折するとすぐに昭和7年(1932年)洗馬の大火後に開通した新道と合流する。三角地帯に道標や石塔が並んでいる。道標は常夜灯がある枡形から移されたもの。正面に“右中山道”左側面に“左北国往還
善光寺道”と彫られたている。下記の石塔群1は左から、不明の石塔 / 庚申塔 / 題目塔 / 庚申塔2基。石塔群2は左から、庚申塔2基(石塔群1と重複)
/ 不明の石塔4基。 |
| 常夜灯 |
|
 |
 |
 |
| 道標 / 道祖神 |
石塔群1 |
石塔群2 |
|
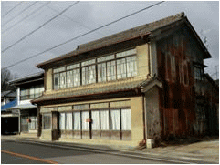 |
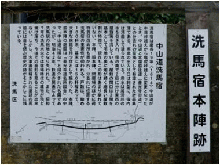 |
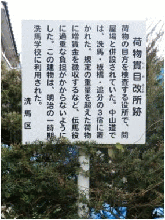 |
| 古民家 |
本陣跡 |
荷物貫目改所跡 |
|
 |
 |
 |
| 脇本陣跡 |
萬福寺 |
古民家 |
|
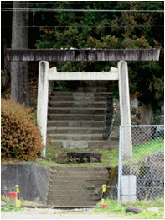 |
 |
 |
| 洗馬神明宮鳥居 |
芭蕉歌碑 |
高札場跡 |
|
|
道標のある三角地帯からすぐ右手に、邂逅(あふた)の清水入口標識がある。治承4年(1180年)平氏追討の令旨を出され、木曽義仲も挙兵する。強行軍で疲れ果てた義仲の馬を湧く清水で洗ったところ、元気になったと云われている。5分ほどすると、左手にJR洗馬駅案内標識
/ 左手に本陣跡 / 左手に荷物貫目改所跡 / 左手に脇本陣跡 / 右手に萬福寺 / 左手に洗馬神明宮の鳥居 / 左手に芭蕉歌碑 / 左手の高札場跡に中仙道と洗馬宿標識
と続く。中山道では、板橋 / 追分 / 洗馬の3宿に荷物貫目改所が置かれていた。人足と馬に過重な負担が掛らないように、規定の重量を越えた荷物に増賃金を徴収などをしたところ。洗馬神明宮の鳥居の先にある参道は、JR中央本線が横切り途切れている。
|
|
 |
 |
 |
| 牧野一里塚跡 |
旧牧野公民館 |
題目燈2基 |
|
 |
 |
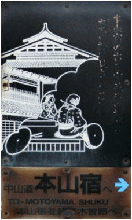 |
| 庚申塔 |
石塔群 |
本山宿案内標識 |
|
|
高札場跡から5分ほどすると、JR中央本線ガードを潜る。すぐ左手に牧野一里塚跡がある。背後の高台に旧牧野公民館があり、登る途中の右手に題目燈(南無妙法蓮華経)2基
/ 高台の右手前に庚申塔 / 右手奥に石塔が15基確認できる。左から、題目塔(南無阿弥陀仏) / 念仏供養塔 / 庚申塔 / 不明の石塔 /
馬頭観音? / 庚申塔 / 地蔵 / 不明の石塔5基 / 地蔵 / 不明の石塔 / 地蔵 と並んでいる。15分ほどすると、道は弧を描く様に大きく迂回する。細い道を直進しても行ける。牧野交差点で19号線を右折する。5分ほどすると左手に本山宿案内標識がある。
|
|
中山道69次 32番 本山(もとやま)宿
所在地:長野県塩尻市
天保14年(1843年)中山道宿村大概帳
人口:502人 家数:117 本陣:1 脇本陣:1 旅籠:34 |
|
| 慶長19年(1614年)旧中山道のルート変更に伴い、塩尻宿 / 洗馬宿とともに設置された宿場。木曽路の玄関口として栄え、松本藩の木曽口の固めとして口留番所が置かれていた。昭和7年(1932年)の大火で、宿場の大部分が焼失している。そば切り発祥の地と云われている。“そば切り”は現在の一般的なそばの形態で、そば粉を薄く平に延ばして包丁で切るやり方。そば粉を練った“そば掻き”と区別していた。本山でそばを食べられるのは、本山そばの里だけになっている。 |
|
 |
 |
本山宿案内標識から10分ほどすると、19号線から右へ進む。すぐ右手の池に瀦水墾田記念碑 / 左手に中仙道本山宿標識 / 左手に秋葉神社と灯篭
/ 石仏群と続く。石仏群は、道祖神 / 馬頭観音 / 馬頭観音 / 題目塔(阿弥陀仏) / 地蔵 / 題目塔(南無阿弥陀仏) / 二十三夜塔?
/ 不明の石塔 / 庚申塔 / 庚申塔 と並んでいる。バス待合所で昼食を摂る。
|
| 瀦水墾田記念碑 |
中仙道本山宿標識 |
|
 |
 |
| 秋葉神社 |
石仏群 |
|
 |
 |
 |
| 池生神社と本山そばの里看板 |
古民家 |
小林本陣跡 |
|
 |
 |
秋葉神社から5分ほどすると右手に池生(いけおい)神社と本山そばの里看板がある。5分ほどすると、右手に明治天皇行在所跡碑のある小林本陣跡 / 左手に中山道本山宿標識と続く。5分ほどすると、左手に灯篭
/ 朽ちかけた秋葉神社の社 / 秋葉大権現がある。 |
| 中山道本山宿標識 |
秋葉神社 |
|
 |
 |
 |
| 日出塩の青木 |
本山一里塚跡 |
長泉院 |
|
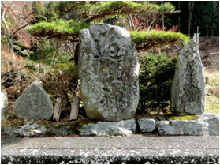 |
秋葉神社からすぐに19号線と合流する。5分ほどすると右へ細い道を進む。すぐに中仙道第2踏切を渡り、線路沿いに進む、すぐ右手に “洗馬の肘松 日出塩の青木
お江戸屏風の絵にござる”と歌われた日出塩の青木への案内看板がある。小道を道なりに進むと、突き当りの建物に囲まれたところにある。旧中山道に戻り5分ほどすると、合流地点の左手に本山一里塚跡がある。すぐ左手に長泉院 / 左手にJR日出塩駅案内標識 / 左手に石塔群(筆塚 /道祖神 / 秋葉権現)と続く。
|
| 筆塚 / 道祖神 / 秋葉権現 |
|
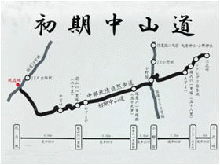 |
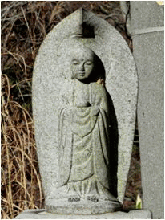 |
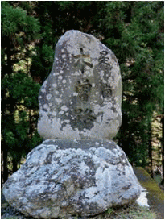 |
| 初期中仙道案内板抜粋 |
地蔵 |
是より南 木曾路 |
|
| 石塔群から10分ほどすると道標があり、右へ進む。19号線を潜り奈良井川の崖道を道なりに進むと、19号線と合流する。道標から15分ほどのところに、初期中仙道案内板
/ 右手に地蔵と続く。5分ほどすると橋を渡った右手に、東屋 / これより南木曾路案内板 / 昭和15年(1940年)造立の“是より南 木曾路”碑がある。裏面に“歌ニ絵ニ其ノ名ヲ知ラレタル、木曽路ハコノ桜沢ヨリ神坂ニ至ル南二十余里ナリ”と彫られている。木曽路の北の入口であり、江戸時代は尾張藩領の北境であった。旧中山道で木曽路と呼ばれるのは、桜沢から馬籠・落合間にある立場茶屋までの88km。この間に北から贄川
/ 奈良井 / 薮原 / 宮越 / 福島 / 上松 / 須原 / 野尻 / 三留野 / 妻籠 / 馬籠の宿があり、木曽十一宿と呼ばれた。東屋で休憩する。 |
|
 |
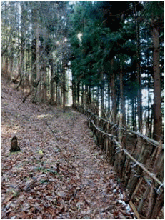 |
 |
| 19号線を鋭角に登る坂 |
山道 |
不明の石塔 / 馬頭観音 |
|
 |
 |
東屋からすぐに交通量の多い19号線を横断、旧中仙道は左手の坂を鋭角に登る。坂道を上り突当りを右折して、道なりに山道を進む。5分ほどすると左手に不明の石塔と馬頭観音がある。さらに5分ほどすると、左手の祠に馬頭観音と不明の石塔2基が並んでいる。左手に旧中央本線のトンネルが見える。 |
| 馬頭観音 / 不明の石塔2基 |
旧中央本線のトンネル |
|
 |
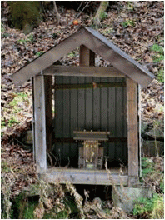 |
 |
| 桜沢茶屋本陣 |
不明の社 |
白山神社鳥居 |
|
 |
 |
 |
| 庚申塔 |
中部北陸自然歩道道標 |
不明の石塔 |
|
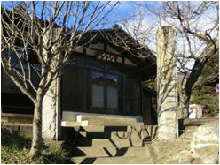 |
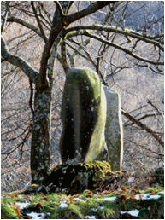 |
 |
| 鶯着寺 |
不明の石塔 |
若神子一里塚 |
|
| 馬頭観音と不明の石塔2基から5分ほど坂を下ると19号線と合流、すぐ右手に明治天皇櫻澤御小休所碑のある桜沢茶屋本陣。5分ほどすると左手に不明の社がある。さらに5分ほどすると奈良井川に架かる片平橋を渡ると、右手に白山神社鳥居 / すぐ右手に庚申塔と続く。5分ほどすると中部北陸自然歩道道標(贄川駅まで2.2km)があり、細い道を進む。ここから先は中部北陸自然歩道道標がところどころにあり、贄川駅まで迷うことはない。中部北陸自然歩道道標(贄川駅まで2.2km)から5分ほどすると、左手の道端に不明の石塔3基 / 高台に鶯着(おうちゃく)寺がある。すぐに歩道橋があり、左手に石塔が数基見える。5分ほどすると、右手に若神子一里塚がある。明治43年(1910年)中央本線の鉄道敷設時に1基が取り壊される。現存する1基も19号線の拡幅によって切り崩されて、直径約5m・高さ1mほどを残すのみとなっている。 |
|
 |
 |
 |
| 諏訪社鳥居 |
石塔群 |
中部北陸自然歩道道標 |
|
 |
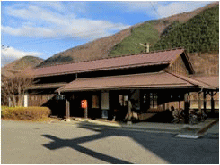 |
| 石塔群 |
贄川駅 |
|
|
若神子一里塚からすぐに中部北陸自然歩道道標(贄川駅まで1.7km)があり、19号線と分かれ右手の細い坂道を進む。5分ほどすると右手に諏訪社鳥居
/ 左手に石塔群と続く。二三夜待供養塔 / 道祖神 / 不明の石塔 / 庚申塔 と並んでいる。10分ほどすると、突き当りに石塔が12基ある。道祖神
/ 西国巡拝供養塔 / 庚申塔 / 光明真言 弥陀念仏供養塔 / 不明の石塔 / 廻国供養塔 / 不明の石塔5基 と並んでいる。道なりに10分ほど進むと車道と合流、さらに5分ほどすると19号線と合流する。旧中山道は、この辺りから19号線とJR中央本線を横切っていた。贄川駅裏を通り贄川宿に入るが、ここから贄川関所までの道が消滅している。19号線を進むとすぐ左手にJR贄川駅がある。
|
|
中山道69次 33番 贄川(にえかわ)宿
所在地:長野県塩尻市
天保14年(1843年)中山道宿村大概帳
人口:545人 家数:124 本陣:1 脇本陣:1 旅籠:25 |
|
|
古くは温泉があり“熱川”だったが、温泉が枯れてから“贄川”になった。宿が開設されたのは天文年間(1532年〜1555年)で、木曽11宿の最北端にある山間の小さな宿場。木曽路は尾張藩領で、本山宿の松本藩との領界にあたる。北の入口に関所があり、福島関所の補助的役割を果たしていた。贄川関所は古文書などに基づき忠実に復元される。宿場はこれまで数回の大火にみまわれ、昭和5年(1930年)の大火で宿場の大部分が焼失している。
|
|
 |