| 中山道69次 No.07 本庄駅-(約10km)-新町駅 |
|
| 2011年 5月29日(日)10:00 雨 |
|
| 本庄駅 |
→ |
開善寺 |
→ |
慈恩寺 |
→ |
歴史民俗資料館 |
→ |
安養院 |
→ |
金鑚神社 |
→ |
佛母寺 |
→ |
浅間山古墳 |
→ |
八幡神社 |
→ |
陽雲寺 |
→ |
勝場一里塚跡 |
→ |
神流川古戦場跡 |
→ |
八坂神社 |
→ |
諏訪神社 |
→ |
浄泉寺 |
→ |
新町駅 |
|
|
 |
 |
 |
| 庚申堂 |
石塔群 |
庚申塔 |
|
 |
 |
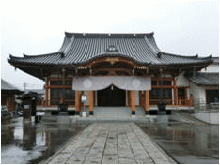 |
| 庚申堂 |
円心寺山門 |
円心寺 |
|
| 本庄駅から北へ進むと、左手に庚申堂 / 奥に庚申塔などの石塔が並んでいる。本庄駅入口交差点で旧中山道と交差する。直進すると、右手に本庄城主・小笠原信嶺が天正19年(1591年)に創建したと云われる円心寺が見えて来る。山門は天明年間(1781年〜1788年)建立と云われている。本庄七福神(福禄寿)になっている。 |
|
 |
 |
 |
| 城山稲荷神社石柱 |
城山稲荷神社鳥居 |
ケヤキと城山稲荷神社社殿 |
|
|
本庄市役所手前の交差点を右折すると、左手に城山稲荷神社の石柱がある。左折して北へ進むと城山稲荷神社がある。鳥居の左手に本庄城城址案内板がある。武蔵七党の小玉党から分かれた庄氏が、本庄氏を名乗り弘治2年(1558年)に築城する。永禄10年(1567年)後北条軍に攻められ落城、服属する。天正18年(1590年)小田原合戦のとき落城、本庄氏は滅亡する。徳川家康の関東入国後は、小笠原信嶺が城主になる。慶長17年(1612年)小笠原信之が古河に転封となり廃城となる。城山稲荷神社の南西、本庄市役所との間に本丸があった。天保15年(1844年)に再建された城山稲荷神社社殿前にあるケヤキは、築城のおりに献木されたと云われている。
|
|
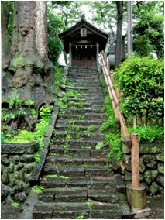 |
 |
 |
| 愛宕神社 |
開善寺 |
小笠原信嶺夫婦の墓 |
|
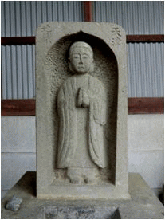 |
 |
 |
| 地蔵 |
道祖神 / 庚申塔 |
慈恩寺 |
|
| 本庄駅入口交差点まで戻り、旧中山道を西へ進む。交差点北東側の埼玉りそな銀行辺りが、田村本陣跡。西へ進むと左手にある東和銀行と足利銀行辺りが、内田本陣跡。本庄1丁目交差点手前を右折して北へ進むと、右手に天正19年(1591年)創建と云われている愛宕神社の鳥居がある。狭い参道を進むと、古墳の上に社殿がある。鳥居まで戻り北へ進むと、
突き当たりに天正19年(1591年)に創建の開善寺がある。本庄七福神(布袋尊)になっている。小笠原氏の菩提寺で、道をはさんだ南西側の古墳に、小笠原信嶺夫婦の墓がある。西へ進むとすぐ左手の祠に、地蔵
/ 道祖神 / 庚申塔 が並んでいる。突き当たりを左折すると、すぐ右手に慈恩寺がある。本庄七福神(弁財天)になっている。 |
|
 |
 |
 |
| 田村本陣門 |
歴史民俗資料館 |
小倉山房石碑群 |
|
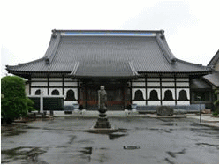 |
慈恩寺から南へ、旧中山道方向へ進む。右折すると、右手に田村本陣跡から移築された田村本陣門と市立歴史民俗資料館(旧本庄警察署)がある。明治16年(1883年)築の洋風建築物で、左手に小倉山房石碑群がある。歴史民俗資料館の北にあった崖を、京都嵐山の小倉山に見立てて造られた小倉山房があった。文人の作品を石碑にして、崖や庭に置いていた。ほとんどは安養院に移されたが、最後まで残っていたものを移したもの。西へ進み交差点を越えると、右手に文明7年(1475年)創建の安養院がある。本庄七福神(毘沙門天)になっている。 |
| 安養院 |
|
 |
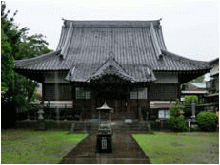 |
 |
| 金鑚神社 |
佛母寺 |
銭洗いの光景 |
|
|
安養院から南へ進むと、中央3丁目交差点で旧中山道と交差する。旧中山道を西へ5分ほど進むと、右手に欽明天皇2年(541年)創建の金鑚(かなさな)神社がある。本庄七福神(恵比寿)になっている。千代田三交差点を右折して北東へ進む。すぐに右折すると、左手に佛母寺がある。本庄七福神(弁財天)になっている。
|
|
|
|
| 本庄七福神 |
|
| 本庄七福神は、旧中山道の本庄宿にある。弁財天が佛母寺 / 慈恩寺 / 大正院 にあり、9寺社となっている。 |
|
 |
 |
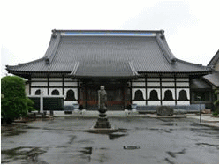 |
| 金鑚神社 |
城立寺 |
安養院 |
|
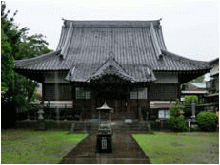 |
 |
 |
| 佛母寺 |
慈恩寺 |
大正院 |
|
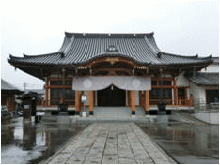 |
 |
 |
| 円心寺 |
泉林寺 |
開善寺 |
|
| 恵比寿 |
金鑚神社 |
本庄市千代田3-2-3 |
| 大黒天 |
城立寺 |
本庄市銀座3-4-7 |
| 毘沙門天 |
安養院 |
本庄市中央3-3-6 |
| 弁財天 |
佛母寺 |
本庄市千代田3-3-10 |
| 弁財天 |
慈恩寺 |
本庄市中央1-2-22 |
| 弁財天 |
大正院 |
本庄市本庄2-4-8 |
| 福禄寿 |
円心寺 |
本庄市本庄3-3-2 |
| 寿老人 |
泉林寺 |
本庄市銀座1-5-3 |
| 布袋尊 |
開善寺 |
本庄市中央2-8-26 |
|
|
|
|
 |
 |
| 馬頭観音 |
|
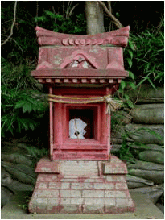 |
| 社 |
浅間山古墳 |
|
| 462号線に架かる横断歩道橋を渡り、西へ進む。10分ほどすると、392号線と合流する。15分ほどすると、右手に平成7年(1995年)造立の馬頭観音がある。さらに15分ほどすると、左手に七世紀前半に造られた浅間山古墳がある。直径約38m
/ 高さ約6m の円墳で、全長約9.5m横穴式石室がある。古墳の上に社がある。 |
|
 |
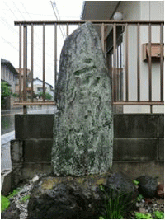 |
 |
| 庚申塔(左) |
庚申塔(右) |
石塔 / 薬師堂 |
|
 |
 |
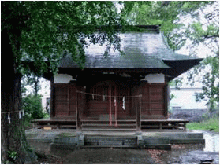 |
| 薬師堂 |
庚申塔 |
金久保八幡神社 |
|
| 浅間山古墳から10分ほどすると、御陣場川にかかる楠森橋(くすもりはし)を渡る。5分ほどすると、左右に庚申塔がある。392号線は神保原1丁目交差点を右折、神保原(北)交差点で17号線と斜めに交差する。庚申塔から10分ほどすると、左手に庚申塔 / 馬頭観世音 /宝篋印塔などの石塔が並んでいる。奥の祠に享保10年(1725年)造立の薬師がある。すぐ右手に庚申塔がある。さらに10分ほどすると、右手に金久保八幡神社がある。拝殿で雨をしのぎ、昼食を摂る。 |
|
 |
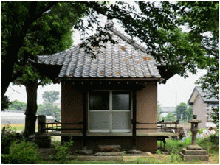 |
 |
| 金窪城址入口石柱 |
法西寺 |
地蔵 |
|
 |
旧中山道を進むと、すぐ右手に金窪城址入口石柱がある。右折して北へ進む。すぐに十字路を左折すると、右手に法西寺がある。十字路まで戻り北へ進むと、すぐ右手に地蔵の祠 / 左側に石塔が並んでいる。 |
| 石塔群 |
|
 |
左手に金窪城址公園がある。金窪城は、武蔵七党の丹党から分かれた加治家治が治承年間(1177年〜1180年)に築城したと云われている。神流川(かんながわ)に臨む崖上にあり、土塁や堀が一部に残る。元弘年間(1331年〜1334年)新田義貞が修築したと云われている。寛正年間(1460年〜1466年)から斉藤盛光が居城するが、天正10年(1582年)神流川の戦いで落城する。武田信玄の異母弟・川窪信実が居城するが、天正3年(1575年)長篠の合戦で戦死する。元和3年(1617年)嫡男・川窪信俊が金窪城主となり、養母である信玄の室・三条夫人と居城する。元禄11年(1698年)丹波に転封となり、廃城となる。 |
| 金窪城址 |
|
 |
 |
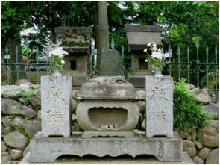 |
| 陽雲寺 |
陽雲寺銅鐘 |
畑時能供養祠 |
|
 |
 |
 |
| 地蔵 |
庚申塔などの石仏群 |
社 |
|
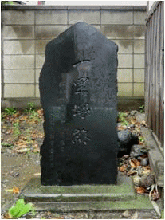 |
 |
 |
|
勝場一里塚跡碑
|
常夜灯(東側) |
常夜灯(西側) |
|
| 金窪城址入口石柱から旧中山道を進むと、すぐ左手に陽雲寺石柱があり左折する。さらに右折すると、奥まったところに本堂がある。元久2年(1205年)創建時は満願寺と称していたが、元弘3年(1333年)新田義貞が不動堂を建立したことから新田勝軍不動堂と称された。その後金窪城主・斎藤氏の加護を受けて崇栄寺と改めたが、天正10年(1582年)神流川の戦いで焼失する。天正19年(1591年)金窪城主となった川窪信俊の養母である信玄の室・三条夫人がこの境内に居住、元和4年(1618年)没した。信俊は養母の菩提を弔うため、その法号・陽雲院から陽雲寺と改称した。参道入口右側に、歴王2年(1339年)加賀国で足利氏に討たれた新田義貞の家臣・畑時能の供養祠
/ 境内に、元禄8年(1695年)鋳造の銅鐘(国認定重要美術品)がある。陽雲寺から15分ほどすると、右手に地蔵2基 / 寛政12年(1800年)造立の庚申塔と石仏群
/ 右手に社、左側に勝場一里塚跡碑と続く。勅使河原(北)交差点で、17号線と合流する。勝場一里塚跡から5分ほどすると、神流川に架かる神流川橋を渡る。橋の欄干、右手の東側と西側にそれぞれ文化12年と彫られた常夜燈がある。見透燈籠と呼ばれていた常夜燈の複製で、本物は近くの大光寺に移築されている。神流川は出水のたびに道筋が変化し、渡船場や橋の位置も変わっていた。文化12年(1815年)川の両岸に常夜灯を造立、夜往来する旅人の目印とした。旧中山道は、神流川橋の左手を通っていた。本庄側から中洲までは仮土橋(満水時は渡船)、中洲から対岸の新町までは舟で渡っていた。 |
|
 |
 |
 |
| 神流川古戦場跡碑 |
道標 |
新町宿常夜灯 |
|
| 埼玉県から群馬県に入る。西側の常夜燈から5分ほどすると、右手に神流川古戦場跡碑がある。この辺りで消滅した旧中山道が復活する。神流川の戦いは、天正10年(1582年)本能寺の変直後、織田信長の仇を討つため京都へ向かった滝川一益と北条氏邦・氏直が神流川流域において繰り広げられた戦い。滝川一益16000
/ 北条氏邦・氏直氏50000の兵力で、戦国時代を通じて関東地方でもっとも大きな野戦と云われている。滝川一益は惨敗を喫し厩橋城に遁走、碓氷峠から小諸を経て本拠地の伊勢長島城に逃げ帰る。神流川古戦場跡碑から5分ほどすると、三角地帯に“従是 左
江戸 二十四里 右 碓氷峠 十一里”と彫られた昭和53年(1978年)造立の道標と昭和53年(1978年)造立の複製された新町宿常夜灯がある。文化12年(1815年)造立の見透燈籠と呼ばれた本物は、高崎市大八木の諏訪神社に移築されている。この灯籠には“従是
左江戸二十四里 右碓氷峠 十一里”と彫られており、新町宿の入口道標となっていた。 |
|
中山道69次 11番 新町宿
所在地:群馬県高崎市
天保14年(1843年)中山道宿村大概帳
人口:1473人 家数:407 本陣:2 脇本陣:1 旅籠:43 |
|
| 本庄宿と倉賀野宿との間は、烏川北岸の玉村を経由するルートだった。慶安4年(1651年)落合新町 / 承応2年(1653年)笛木新町に伝馬役が命ぜられ、ルートが変更された。これに伴い、享保9年(1724年)に両方の町を合わせて新町宿が成立した。 |
|
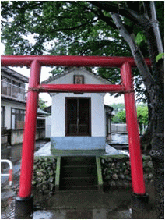 |
 |
 |
| 八坂神社 |
庚申塔 |
芭蕉句碑 |
|
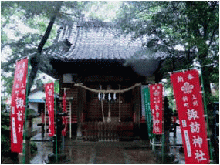 |
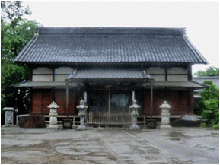 |
 |
| 諏訪神社 |
専福寺 |
浄泉寺 |
|
| 17号線から右方向へ、131号線を進む。交差点を渡ると右手に八坂神社がある。社殿の右側に、破損した庚申塔と天保10年(1839年)造立の芭蕉句碑「傘におしわけ見たる柳かな」がある。 この句碑は明治の廃仏稀釈で、河原に捨て去られたもの。すぐ右手に本屋敷から宝永5年(1708年)に現在地に移された諏訪神社 / 専福寺と続く。さらに5分ほどすると新町郵便局前交差点手前に浄泉寺がある。 |
|
 |
 |
 |
| 妙見寺 |
道祖神 |
於菊稲荷神社拝殿 |
|
| 道標があり、新町駅入口交差点手前を右折する。左手に妙見寺、右手に文政6年(1823年)創建の於菊稲荷神社がある。入口左手に、平成10年(1998年)造立の道祖神がある。旅籠大黒屋で働く飯盛り女・於菊は、この稲荷神社を信仰していた。ある日、突然体が動かなくなる病気に掛る。宿場の人たちが哀れに思い、稲荷の境内に小屋を建て3年もの間養生させた。ある夜、稲荷神が現れ病を治してくれる。於菊は稲荷神社の巫女となり、以来於菊稲荷神社と呼ばれる様になったと云われている。 |
|
 |
旧中山道を西へ進み、新町駅入口交差点を左折して179号線を南西へ進む。17号線と交差する新町駅前交差点の東側に、高長神社がある。金豊大神 /
諏訪大明神 / 高長大神の額が掛っている。新町駅前交差点からさらに南西へ進むと、JR高崎線・新町駅に至る。 |
| 高長神社 |
|
 |