| 中山道69次 No.04 北本駅-(約13km)-行田駅 |
|
| 2011年 2月20日(日)09:30 曇り |
|
| 北本駅 |
→ |
東間浅間神社 |
→ |
金剛院 |
→ |
鴻巣観光協会 |
→ |
勝願寺 |
→ |
鴻神社 |
→ |
蓑田観音堂 |
→ |
永川八幡神社 |
→ |
前砂一里塚跡 |
→ |
東曜寺 |
→ |
権八地蔵 |
→ |
行田駅 |
|
|
 |
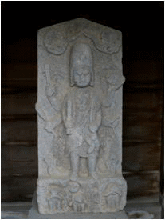 |
 |
| 勝林寺 |
庚申塔 |
東間浅間神社 |
|
| 北本駅より北東へ、駅入口交差点を左折して中山道を北西へ進む。5分ほどすると右手に寛永元年(1624年)創建と云われる勝林寺、すぐ左手に東間(あずま)浅間神社がある。参道の右手に庚申塔、富士塚に社殿がある。 |
|
 |
 |
 |
| 八幡神社 |
浅間神社 |
不動明王 |
|
 |
東間浅間神社から30分ほどすると、右手に八幡神社がある。社殿右手に浅間神社と不動明王、奥に金剛院がある。 |
| 金剛院 |
|
中山道69次 05番 鴻巣宿
所在地:埼玉県鴻巣市
家数:566 本陣:1 脇本陣:1 旅籠:58 |
|
| 慶長7年(1602年)本宿村の宿場を移して鴻巣宿と改称された。鴻巣の地名由来は、[1]人に害をなす“木の神”と言われる大木があり、人々は難を逃れるため供えをしていた。コウノトリがこの大木に巣を作り、卵を産み育て始めた。大蛇が卵を飲み込もうとしたので、コウノトリは大蛇と戦い退散させた。それから“木の神”は人に害をなすことがなくなったので、人々は大木の傍に社を建立する。“鴻の宮”と呼ばれていて、いつしかこの地を“鴻巣”と呼ぶようになった。
[2]古代にこの地が武蔵国の国府となったことから、国府の州(こうのす)がコウノトリ伝説から“鴻巣”の字を当てるようになった。 |
|
|
 |
 |
| 鴻巣観光協会 |
|
 |
| 人形店 |
街路灯の雛人形 |
|
| 八幡神社から10分ほどすると、左手に鴻巣観光協会があり立ち寄る。江戸時代に京都の伏見人形師が移り住み作ったのが始まりで、江戸時代より雛人形の生産地として栄えた。時節柄か、雛人形が街路灯にも飾られていた。 |
|
 |
 |
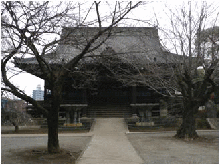 |
| 勝願寺山門 |
勝願寺仁王門 |
勝願寺本堂 |
|
 |
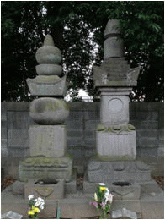 |
 |
| 仙石秀久の墓 |
真田信重の墓 / 信重室の墓 |
真田小松姫の墓 |
|
 |
鴻巣観光協会から5分ほどすると、左手に鎌倉時代(1185年頃〜1333年)創建の勝願寺がある。江戸時代には,浄土宗の関東七大寺の一つに数えられている。敷地は環濠が巡らされていて、城としての構造を有していたと云われる。寺の屋根には徳川家葵の紋瓦がある。江戸増上寺を頂点とする、浄土宗の関東十八檀林の一つ。本堂は明治24年(1891年)、仁王門は大正9年(1920年)に再建されたもの。本堂の左手に、信州小諸藩主・仙石秀久の墓
/ 真田信重(信州松代藩主・真田信之の三男)の墓 / 真田信重室の墓 / 真田小松姫(真田信之室)の墓がある。真田信之は真田幸村の兄。真田小松姫は徳川譜代家臣の本多忠勝の長女で、徳川家康の養女として真田信之に嫁ぐ。 |
| 六地蔵 |
|
 |
 |
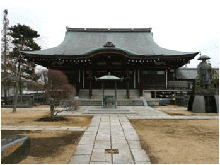 |
| 古民家 |
鴻巣本陣跡 |
法要寺 |
|
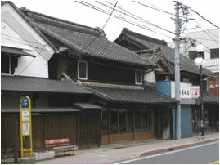 |
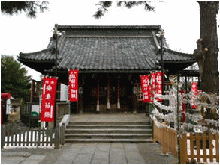 |
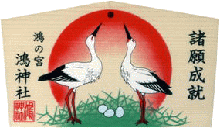 |
| 古民家 |
鴻神社 |
鴻神社絵馬 |
|
| 勝願寺からすぐ左手に鴻巣本陣跡がある。5分ほどすると右手に、長禄元年(1457年)創建と云われる法要寺がある。加賀藩が宿泊として利用、加賀藩の梅鉢紋を寺紋として許されていた。さらに5分ほどすると、右手に鴻神社がある。明治6年(1873年)に、氷川社
/ 熊野社 / 竹ノ森雷電社(現在地)を合祀して鴻三社となる。さらに明治35年(1902年)から明治40年(1907年)にかけて、日枝神社 /
東照宮 / 大花稲荷社 / 八幡神社を合祀して明治40年(1907年)に鴻神社となる。氷川社は氷川鴻ノ宮とも呼ばれ,鴻巣宿の総鎮守。また“こうのとり伝説”の由来となっている社。 |
|
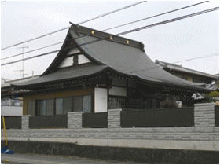 |
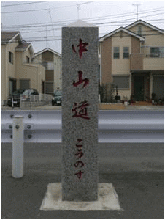 |
 |
| 池元院 |
中山道鴻巣宿石柱 |
白山神社 |
|
 |
 |
 |
| 蓑田観音堂 |
庚申塔 |
庚申塔 |
|
| 鴻神社から10分ほどすると、右手に宿場の有志により創建されたと云われる池元院がある。すぐに加美交差点を左方向へ進む。この辺りまでが鴻巣宿で、当時木戸が設置されていた。中山道鴻巣宿石柱がある。JR高崎線の第三中仙道踏切を渡り、5分ほどすると右手に白山神社がある。すぐ右手に蓑田観音堂、境内左手には街道筋にあった庚申塔などが多数並んでいる。蓑田は嵯峨源氏の支流・箕田源氏など武蔵武士発祥の地。清和源氏・源経基から嵯峨源氏に受け継がれ、渡辺綱に伝えられたと云われる一寸八分(6cm弱)の馬頭観音が本尊。5分ほど先にあるショッピングセンターで昼食を摂る。 |
|
 |
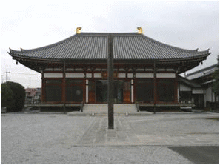 |
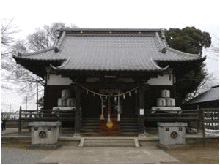 |
| 龍昌寺 |
宝持寺 |
永川八幡神社 |
|
| 蓑田観音堂から5分ほどすると、右手に多数の板碑がある龍昌寺がある。15分ほどすると、右手に渡辺綱が父と祖父の菩題を弔うために創建したと云われる宝持寺がある。
左隣に渡辺綱を祀る八幡社と承平元年(966年)源経基が勧請したと云われる氷川神社が、明治6年(1873年)に合祀された氷川八幡神社がある。境内には嵯峨源氏の由来を記した“箕田碑”がある。龍昌寺
/ 宝持寺 / 氷川神社は箕田源氏ゆかりの寺社。 |
|
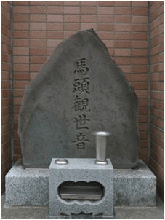 |
 |
 |
| 馬頭観音 |
石塔群 |
中山道石柱 |
|
 |
 |
 |
| 地蔵堂 |
庚申塔 |
正徳2年造立の庚申塔 |
|
 |
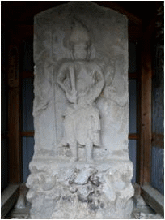 |
永川八幡神社から、5分ほどすると左手に馬頭観音 / 5分ほどすると左手に石塔群 / 5分ほどすると右手に中山道石柱、左手に地蔵堂と庚申塔 / 5分ほどすると左手に正徳2年(1712年)造立の庚申塔と岡象女之神の神号碑 / 5分ほどすると右手に馬頭観音 と続く。 |
| 岡象女之神の神号碑 |
馬頭観音 |
|
 |
 |
 |
| 中山道前砂村石柱 |
前砂一里塚跡 |
妙徳地蔵堂 |
|
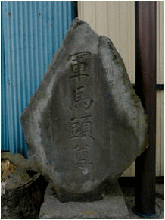 |
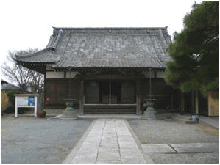 |
 |
| 軍馬頭脾 |
東曜寺 |
吹上神社 |
|
|
| 馬頭観音から5分ほどすると、右手に中山道前砂村石柱がある。すぐ右手に前砂一里塚跡、左右の塚に榎が植わっていたと云う。10分ほどすると、左手に“中山道みち案内”がある。十字路を右折してJR高崎線の踏切を渡る。すぐに左折すると、左手に妙徳地蔵堂がある。眼病に霊験があると云われている。すぐに307号線と合流する。10分ほどすると、左手に明治37年(1904年)造立の軍馬頭脾がある。本町交差点を左折する。道は大きく左に曲がり、右手に宝暦年間(1751年〜1764年)造立のいぼ地蔵で知られる東曜寺がある。道は直角に右に折れ、すぐ右手に吹上神社がある。日枝神社(山王社)を勧進した吹上の鎮守。明治時代に稲荷神社と氷川神社を合祀し吹上神社となった。 |
|
 |
 |
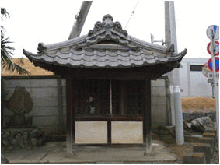 |
| 吹上間の宿石柱 |
吹上間の宿案内板 |
権八地蔵 |
|
 |
吹上神社から5分ほどすると、歩道橋下に吹上“間(あい)の宿”石柱と案内板がある。吹上駅前交差点から吹上本町交差点にかけて賑わっていたと云われている。中山道はここからJR高崎線で分断されている。5分ほど線路沿いに進み、榎戸踏切を渡る。10分ほどすると左手に元禄11年(1698年)造立の権八地蔵堂がある。権八は路銀に困り、上州の絹商人を殺害して300両を奪った。傍らで見ていた地蔵に「今のことを他言するな」と口封じをすると、地蔵が「己れは言はぬが汝も言うな」と口を利いたと云う。荒川の土手が続くこの辺りは、とても寂しい街道で物騒な場所であったと云われている。Y字路を左へ進み、土手を登る。左下に堂が見える。 |
| 堂 |
|
| 堤防に登り、鋭角に右折して北西へ進む。左手は荒川の河川敷であるが、荒川ば見えない。しばらくすると、マンションが3棟あり、土手を下り道なりに北東へ進むと、行田駅南口に至る。 |
|
 |