| 中山道69次 No.02 戸田公園駅-(約13km)-大宮駅 |
|
| 2010年12月12日(日)09:30 晴のち曇り |
|
| 戸田公園駅 |
→ |
歴史民俗資料館 |
→ |
三学院 |
→ |
宝蔵寺 |
→ |
熊野神社 |
→ |
焼米坂 |
→ |
調神社 |
→ |
玉蔵院 |
→ |
成就院 |
→ |
廓信寺 |
→ |
氷川神社 |
→ |
大宮駅 |
|
|
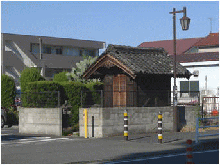 |
 |
JR戸田公園駅から線路沿いに南へ、68号線を左折する。川岸3丁目交差点を左折して17号線を北へ進む。本町1丁目交差点を右折、十字路を左折して下前公園通りを北へ進む。突き当たりを左折、交差点を右折して17号線を北へ進む。すぐ左手に社、さらに右手の祠に庚申塔がある。
|
| 社 |
庚申塔 |
|
|
中山道69次 02番 蕨宿
所在地:埼玉県蕨市
家数:430 本陣:2 脇本陣:1 旅籠:23
|
|
 |
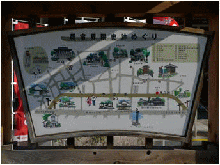 |
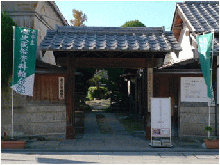 |
| 中山道蕨宿石柱 |
蕨宿界隈史跡めぐり案内板 |
歴史民俗資料館分館 |
|
 |
 |
 |
| 歴史民俗資料館 |
歴史民俗資料館 |
中山道武州蕨宿石柱とまちづくり憲章 |
|
 |
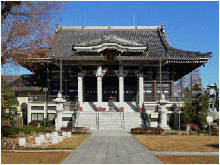 |
 |
| 古民家 |
三学院 |
梵字馬頭観音 |
|
 |
 |
 |
| 子育地蔵 |
六地蔵 |
目疾地蔵 |
|
|
庚申塔から5分ほどすると、右手のY字路に中山道蕨宿石柱がある。17号線と分岐、右方向へ進む。5分ほどすると、右手に蕨宿界隈史跡めぐり案内板 /
左手に歴史民俗資料館分館 / 左手の蕨本陣跡に歴史民俗資料館 と続く。歴史民俗資料館には、寛政4年(1792年)造立などの説明がある庚申塔が置かれている。あまりに綺麗なので触れてみると、プラスティックの張りぼてであった。中山道を進むと、すぐ右手に中山道武州蕨宿石柱と中山道蕨宿まちづくり憲章
/ 地蔵の小径石柱 と続く。右折すると突き当たりに、天正元年(1573年)創建と云われている三学院がある。足立坂東三十三観音20番札所 / 北足立八十八ヶ所30番札所になっている。江戸時代には関東七ヶ寺の一つとして、僧侶の教育機関であった。境内に、阿弥陀堂
/ 弁天堂 / 仏舎利殿 / 閻魔堂 / 三重の塔 がある。山門手前右手に、供養塔と寛政12年(1800年)造立の梵字で陰刻した馬頭観音 /
元禄7年(1694年)造立の子育地蔵 / 寛文〜元禄年間(1661年〜1704年)にかけて造立された六地蔵 / 万治元年(1658年)造立の地蔵(目疾めやみ地蔵)がある。目疾地蔵は目に味噌を塗ると目の病気が治る、あるいは目の病気にかからないと云われている。
|
|
 |
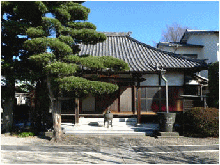 |
 |
| 古民家 |
宝蔵寺 |
辻の一里塚跡 |
|
 |
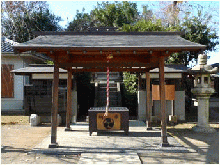 |
 |
| 弁財天 |
熊野神社 |
焼米坂石柱 |
|
|
三学院から中山道に戻って進むと、すぐに17号線と斜めに交差する。道は途中で大きく北へ進路を変える。三学院から15分ほどで、右手に宝蔵寺がある。さらに10分ほどすると、右手に辻の一里塚跡と弁財天の石祠
/ 5分ほどすると左手に熊野神社 がある。突き当たりを右折すると、六辻交差点で17号線を渡る。次の交差点を左へ213号線を進むと焼米坂で、坂の途中に“焼米坂石柱”がある。江戸時代に中山道を通る旅人に“焼き米”を売る店が何軒かあり、“焼米坂”と呼ばれる様になった。“焼米坂”は携行食としても便利だった。
|
|
 |
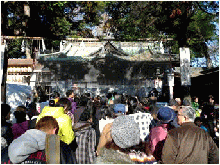 |
 |
| 調神社境内 |
調神社本殿 |
調神社旧本殿 |
|
|
焼米坂を登り10分ほどすると、右手に開化天皇3年(紀元前156年)創建と云われる調(つき)神社がある。安政年間(1854年〜1860年)まで使用された旧本殿は、享保18年(1733年)に建立されたもの。毎年12月12日に開かれる大市“十二日まち”で、大変混雑していた。広い境内には所狭しと露店が立ち並び、熊手も販売されていた。中山道沿いにも、かなり手前から浦和駅西口交差点まで露店が続いていた。境内で昼食を摂る。
|
|
中山道69次 03番 浦和宿
所在地:埼玉県さいたま市
家数:273 本陣:1 脇本陣:3 旅籠:15 |
|
 |
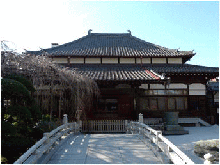 |
| 玉蔵院本堂 |
|
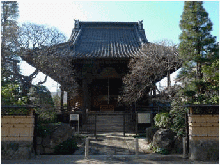 |
| 公園 |
玉蔵院地蔵堂 |
|
 |
 |
 |
| 浦和二七の市場跡 |
慈恵稲荷神社
|
成就院 |
|
 |
 |
 |
| 廓信寺 |
ケヤキの並木 |
氷川神社一の鳥居 |
|
| 調神社から15分ほどすると、左手に玉蔵院がある。山門のは閉じられており、左手から迂回する。公園に見事な銀杏の木があり、紅葉している。本堂の左手に、安永9年(1780年)建立の地蔵堂がある。中山道に戻り5分ほどすると、左手に浦和二七(にしち)の市場跡がある。毎月二と七の日に市が開かれ、農産物や各種生活必需品が取引された。奥に慈恵稲荷神社がある。すぐ左手に成就院、20分ほどすると慶長年間(1596年〜1615年)創建と云われる廓信寺がある。仁王門は江戸後期の建立。境内にさつまいも紅赤発祥の地碑がある。30分ほどするとケヤキの並木が続く。ケヤキの並木が終わり5分ほどすると、右手に氷川神社一の鳥居がある。 |
|
| 氷川神社一の鳥居からの参道は、三の鳥居まで約2km続く。 ケヤキ並木になっているが、江戸時代には松並木 / 太平洋戦争前までは杉並木であったと云われる。寛永5年(1628年)西側に街道が付け替えられるまで中山道として利用されていた。西側の裏参道へと抜けていた。氷川神社の門前や参道にあった宿や家屋敷は、新しい中山道に移転させられる。大宮は、氷川神社の門前町から宿場町へ転換する。 |
|
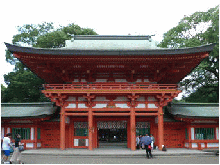 |
 |
 |
| 氷川神社楼門 |
氷川神社舞殿 |
氷川神社拝殿 |
|
|
一の鳥居から約2km続くケヤキ並木の参道を進むと、突き当たりに孝昭天皇3年(紀元前473年)創建と云われる氷川神社がある。武蔵国(東京都と埼玉県)にある氷川神社の総本社である。室町時代以前は、武蔵国一宮は多摩市・小野神社
/ 二宮はあきる野市・二宮神社 / 三宮は氷川神社 となっていた。室町時代以降、武蔵国一宮になっている。
|
|
|
中山道69次 04番 大宮宿
所在地:埼玉県さいたま市
家数:329 本陣:1 脇本陣:9 旅籠:25
|
|
 |
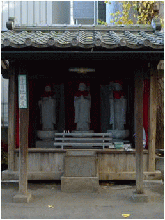 |
氷川神社一の鳥居から中山道を15分ほど進む。吉敷町交差点を渡った先の右手に、塩地蔵の案内板がある。右手の路地を進むと、右手に塩地蔵と子育地蔵の祠が並んでいる。浪人が病で倒れ、2人の娘が地蔵のお告げに従い“塩断ち”をしたところ全快したと云われている。たくさんの塩が地蔵に奉納される。北へ進み、高島屋の角を左折するとJR大宮駅がある。 |
| 塩地蔵 |
子育地蔵 |
|
 |