| 所沢寺社撮影散歩 |
|
| 西武池袋線/新宿線・所沢駅〜牛沼〜安松〜西武池袋線・秋津駅 |
|
| 所沢駅 |
→ |
熊野神社 |
→ |
神明神社 |
→ |
長栄寺 |
→ |
吹上稲荷神社 |
→ |
長源寺 |
→ |
安松神社 |
→ |
秋津駅 |
|
|
 |
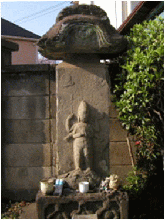 |
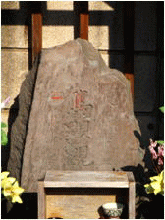 |
| 旭橋 |
庚申塔 |
馬頭観音 |
|
| 所沢駅西口入口交差点を右折して、県道337号線を北へ進む。
K字路のファルマン交差点を北東へ進む。5分ほどの東川(あづまがわ)に架かる旭橋を渡ると、すぐ左手に安永6年(1777年)造立の庚申塔がある。旭橋は、明治44年(1911年)所沢飛行場が造られた際に架けられた国登録有形文化財。昭和5年(1920年)土橋から架け替えられる。親柱にはブロンズ製の電灯があったが、戦時の金属供出により台座だけとなっている。西武新宿線のガードを潜り、北御幸町交差点手前をすぐに左折する。道なりに北へ進むと、右手に天保13年(1842年)造立の馬頭観音がある。庚申塔から馬頭観音へは1本道であったが、明治28年(1895年)に開通した西武新宿線の建設に伴い分断される。西武新宿線のガード北側には、昭和13年(1938年)に開設された所沢飛行場駅があった。昭和16年(1941年)御幸町駅に改称、昭和26年(1951年)に廃止される。 |
|
| 東川(あづまがわ) |
| 狭山丘陵北部から所沢市街地を流れ、清瀬市附近で狭山湖からの柳瀬川と合流する全長11.46kmの川。 |
|
| 地名の由来:御幸町(みゆきちょう) |
| 大正元年(1912年)大正天皇が陸軍大演習の際、所沢飛行場に行幸したことに由来する。 |
|
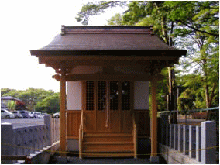 |
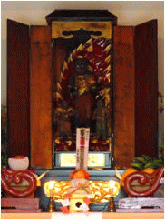 |
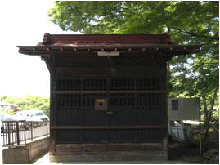 |
| 西新井不動堂 |
旧西新井不動堂 |
|
| 北御幸町交差点から、約1kmの河岸が桜並木となっている東川(あづまがわ)沿いに東へ進む。左手に江戸時代(1603年〜1867年)初期創建の西新井不動堂がある。平成20年(2008年)春に堂が新築される。 |
|
| 西新井不動:所沢市西新井町9 |
|
 |
 |
 |
| 熊野神社鳥居 |
熊野神社鳥居 |
藁の蛇 |
|
 |
 |
 |
| 熊野神社拝殿 |
八雲神社 |
境内社 |
|
| 西新井不動堂の東側に熊野神社がある。安閑天皇の時代(531年〜536年)に創建された熊野宮中氷川大明神が衰退、長禄3年(1459年)に再興したと云われている。大晦日に藁(わら)で大蛇や〆縄を作り、元旦に鳥居や社殿に巻き付ける“若〆神事”が行われる。古い大蛇や〆縄はお札とともに燃やされ、“お焚上げ”にあたるとその年は無病息災に過ごすことができるとされている。拝殿右手に八雲神社や境内社がある。 |
|
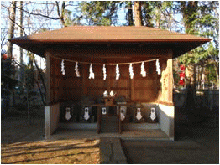 |
拝殿の左手奥に石祠が並んでいる。左から、昭和8年(1933年)造立の弁財天 / 明治11年(1878年)造立の稲荷社 / 文化年間造立の天王社
/ 平成16年再建の奥宮 / 明治11年(1878年)造立の日の宮 / 造立年不明の幡織社がある。天王社の祠には、八雲神社と彫られている。奥宮の屋根と台座の部分は古い。 |
| 石祠 |
|
| 熊野神社:所沢市西新井町17-33 |
|
 |
 |
 |
| 長屋門(2007年4月撮影) |
主屋 |
新しい門 |
|
| 東川沿いに東へ進む。すぐに右折して橋を渡ると、右手に長屋門能面美術館がある。能面美術館は安政2年(1855年)江戸時代末期に建てられた平塚家の旧宅を利用している。平塚家は4代続いた医者の家で、長屋門や式台のある玄関を持つ主屋などがある。能面教室の開催や福山元誠作の能面を常時展示している。毎年4月に元匠会能面展が開催されている。2013年4月に訪れたときには、老朽化により長屋門は取り壊されていた。 |
|
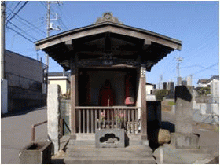 |
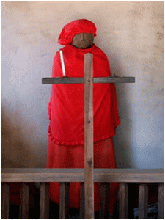 |
 |
| 塚口地蔵 |
馬頭観音 |
|
| 熊野神社の境内裏手を通る国道463号線を東へ進む。東新井町交差点の次の交差点を左折すると、宮地共同墓地前に天正年間(1573年〜1591年)造立の塚口地蔵と文化8年(1811年)造立の馬頭観音がある。馬頭観音は東川の学校橋傍にあったが、東川の改修に伴い移転する。 |
|
 |
 |
国道463号線を西へ進み、若松小学校入口交差点の先にある歩道橋の手前を右折する。左手の畑の生垣に近いところに石鳥居、畑のなかに弥生神社がある。 |
| 弥生神社 |
|
| 弥生神社:所沢市牛沼443 |
|
 |
 |
 |
| 神明神社拝殿 |
八坂神社 |
稲荷神社 |
|
 |
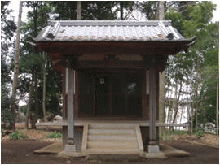 |
 |
| 愛宕神社・秋葉神社 |
牛沼薬師堂 |
|
| 弥生神社から南へ進む。十字路を直進して次を右折すると、左手に牛沼市民の森がある。西側に享保9年(1724年)創建の神明神社、東側の鬱蒼とした木立のなかに元徳年間(1329年〜1331年)造立の牛沼薬師堂がある。神明神社は、所沢神明社を勧請したと云われている。拝殿左手に八坂神社、右手に稲荷神社と愛宕神社・秋葉神社がある。 |
|
| 神明神社:所沢市牛沼410 |
| 牛沼薬師堂:所沢市牛沼496 |
|
 |
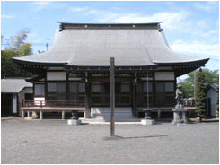 |
 |
| 長栄寺 |
長栄寺本堂 |
閻魔堂 |
|
 |
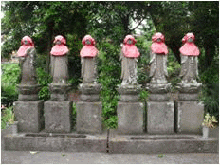 |
 |
| 鐘楼 |
六地蔵 |
宝歴9年造立の地蔵 |
|
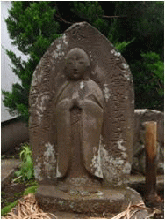 |
 |
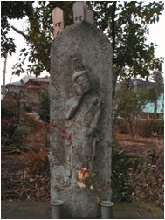 |
| 地蔵 |
宝歴2年造立の観音 |
明和2年造立の観音 |
|
 |
神明神社から参道を南へ進み、突き当たりを左折する。十字路を右折して東川に架かる長栄橋を渡ると、左手に寛保元年(1741年)創建の牛沼山・長栄寺[真言宗豊山派]がある。本尊は十一面観音。明治の廃仏棄釈で廃寺となった巌浄寺[浄土宗]から移された、牛沼の閻魔がある。境内に、鐘楼
/ 文政年間(1818年〜1829年)造立の六地蔵 / 宝歴9年(1759年)造立の地蔵 / 地蔵 / 宝歴2年(1742年)造立の観音 /
明和2年(1765年)造立の観音 / 文政11年(1828年)造立の宝篋印塔がある。 |
| 宝篋印塔 |
|
| 長栄寺:所沢市牛沼52 |
|
 |
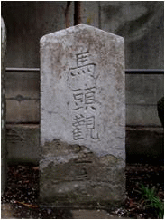 |
 |
| 文政11年造立の馬頭観音 |
造立年不明の馬頭観音 |
庚申塔 |
|
| 長栄寺から東川の南側を沿って西へ進む。中橋のところを左折すると、すぐ左手に文政11年(1826年)造立の馬頭観音 / 造立年不明の馬頭観音 /
安永5年(1776年)造立の庚申塔が並んでいる。 |
|
 |
 |
中橋のところまで戻り、東川の南側を沿って西へ進む。東川に架かる境橋を渡ると、左手(北西側)に寛政10年(1798年)造立の庚申塔がある。左折して東川沿いに西へ進むと、すぐ右手に大正9年(1920年)造立の馬頭観音がある。 |
| 庚申塔 |
馬頭観音 |
|
 |
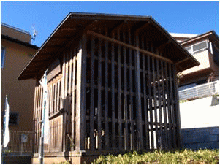 |
 |
| 七曲り坂庚申塔 |
稲荷神社 |
路線バス用の標識 |
|
| 東川沿いに西へ、県道56号線を左折して南へ進む。しばらくすると所沢陸橋交差点があり、左折して県道24号線を東へ進む。上安松交差点を右折して七曲り通りを南へ進む。坂が下りになると、七曲りが始る。下りは間違うことが少ないが、上りは間違い易いところがある。路線バス用の標識がある。 |
|
 |
 |
七曲り坂の2つ目の曲りのところを北へ進むと、左手に稲荷神社がある。3つ目を曲る手前の右手に元禄15年(1702年)造立の庚申塔がある。5回目と6回目の曲りの中間左手に明治37年(1904年)創建の吹上稲荷神社がある。以前は社殿がなく、石祠や石塔が露出していた。 |
| 吹上稲荷神社 |
社殿がないときの吹上稲荷神社 |
|
| 稲荷神社:所沢市上安松606-3 |
| 吹上稲荷神社:所沢市上安松471 |
|
 |
 |
 |
| 上安松地蔵堂 |
馬頭観音 |
地蔵 |
|
 |
東へ進むと、直進方向と左折方向が狭い道になっている十字路がある。右折して南へ進むと、松戸橋北側の交差点南東側に 元禄14年(1701年)造立の庚申塔と地蔵堂がある。地蔵堂には馬頭観音と享保5年(1720年)造立の地蔵がある。 |
| 庚申塔 |
|
 |
 |
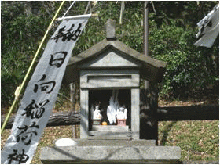 |
| 六地蔵 |
日向稲荷神社 |
|
| 十字路まで戻り、右折して東へ進む。3本目を左折して北へ道なりに進む。しばらくすると変則十字路がある。北西方向に坂を登り、Y字路を道なりに右へ進む。次を左折すると、右手に上安松共同墓地がある。新しく造立された六地蔵の背面に、上安松六地蔵と呼ばれる損傷が激しい六地蔵がある。変則十字路まで戻り南西方向へ進むと、すぐ右手に日向稲荷神社がある。 |
|
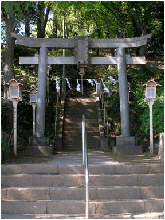 |
 |
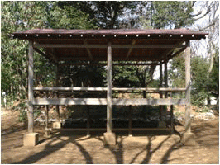 |
| 安松神社鳥居 |
安松神社拝殿 |
神楽殿 |
|
 |
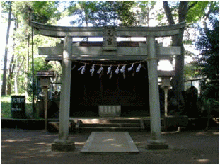 |
|
| 富士塚 |
元宮 |
|
|
| 日向稲荷神社から東へ進むと、すぐ左手に安松神社がある。日枝社 / 氷川社 / 八雲神社 / 神明社 / 稲荷社2社を統合して、大正3年(1914年)に創建される。安松の天王様は、統合された八雲神社の祭事。境内右手に神楽殿や富士塚がある。奥にある元宮には、左から大正3年(1914年)造立の日枝社
/ 造立年不明の氷川社 / 天保4年(1833年)造立の八雲神社 / 寛政7年(1795年)造立の神明社 / 造立年不明の稲荷社 の石祠並んでいる。 |
|
| 安松神社:所沢市下安松486-1 |
|
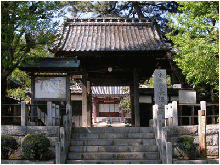 |
 |
 |
| 長源寺山門 |
長源寺本堂 |
鐘楼 |
|
 |
 |
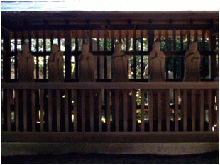 |
| 薬師堂 |
六地蔵 |
|
 |
 |
 |
| 結界石 |
観音 |
出羽三山供養塔 |
|
| 安松神社の東側に、天正19年(1591年)創建の安松山・長源寺[曹洞宗]がある。本尊は釈迦如来。山門(四脚門)は天明年間(1781年〜1788年)建立と云われている。山門前左手に、文化7年(1810年)造立の結界石がある。正面に“不許葷酒入山門”
右側面に“西国 坂東 秩父 百番奉順禮供養塔”と彫られている。境内に鐘楼 / 薬師堂 / 明治5年(1872年)造立の六地蔵 / 観音 / 万延元年(1860年)造立の出羽三山供養塔がある。 |
|
| 長源寺:所沢市下安松487 |
|
 |
長源寺から南へ、突き当たりを左折して東へ進む。右折してJR武蔵野線の高架を潜り、南へ進む。十字路を左折すると、左手に氏照院跡から発掘された元禄10年(1697年)造立の庚申塔がある。氏照は北条氏3代目氏康の三男で、養子縁組をして大石氏照となる。豊臣秀吉の小田原攻め後に切腹させられ、旧臣により氏照院が創建される。明治の廃仏毀釈で廃寺となり、長源寺に合併される。 |
| 庚申塔 |
|
 |
道を戻り西へ進み、JR武蔵野線の高架を潜る。5分ほどすると、左手に金山神社が見える。すぐに松戸橋北側の交差点に出る。 |
| 金山神社 |
|
 |
 |
松戸橋北側の交差点を左折して南へ進む。松戸橋を渡る手前右手に、明治9年(1876年)造立の松戸橋供養塔がある。松戸橋を渡り、南へ進む。左手の秋津市側に地蔵の祠がある。西武池袋線の踏切手前を左折すると、西武池袋線・秋津駅に至る。 |
| 松戸橋供養塔 |
地蔵 |
|
|
|
| [寄り道]秋津神社 |
|
 |
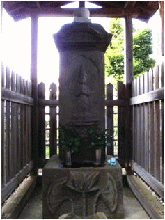 |
西武池袋線の踏切を渡りすぐに右折すると、突き当たりに秋津神社がある。境内にある宝永7年(1710年)造立の庚申塔は、昔は所沢地区にあったもの。大正4年(1915年)に開通した西武池袋線の建設に伴い移転する。秋津神社には元禄12年(1699年)造立の不動明王があり、秋津の不動として知られている。 |
| 秋津神社拝殿 |
庚申塔 |
|
| 秋津神社:東村山市秋津町5-27 |
|
 |