| 所沢寺社撮影散歩 |
|
| 西武池袋線/狭山線・西所沢駅~将軍塚~荒幡富士~西武狭山線・下山口駅 |
|
| 西所沢駅 |
→ |
朝日稲荷社 |
→ |
永源寺 |
→ |
十人坂 |
→ |
長久寺 |
→ |
将軍塚 |
→ |
佛眼寺 |
→ |
鳩峯八幡神社 |
→ |
光蔵寺 |
→ |
荒幡富士 |
→ |
本覚院 |
→ |
関地蔵堂 |
→ |
下山口駅 |
|
|
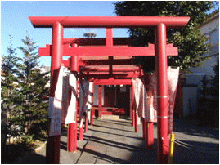 |
 |
西所沢駅より東へ、西所沢駅入口交差点を直進する。さらに4号線の星の宮交差点を直進する。2本目を右折して南へ進むと、左手に星の宮朝日稲荷社がある。 |
| 星の宮朝日稲荷社 |
|
| 星の宮朝日稲荷社:所沢市星の宮1-1023 |
|
 |
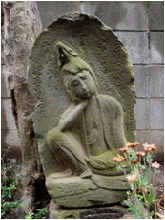 |
 |
|
|
|
|
 |
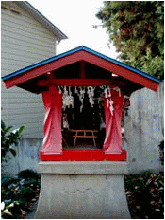 |
突き当たりを右折すると4号線と交差、左折して南東へ進む。所沢高校入口交差点を右折、西武池袋線の踏切を越えて十人坂を下る。坂の途中に十字路があり、右折して江戸道を進む。左手の墓地に石仏がある。所沢高校の敷地で江戸道は分断され、道なりに左へ下る。坂の途中の左手に小道があり、安永元年(1772年)造立の庚申塔と稲荷神社がある。庚申塔は自然石に青面金剛明王が線刻されている。 |
| 庚申塔 |
稲荷神社 |
|
| 稲荷神社:所沢市久米1284 |
|
 |
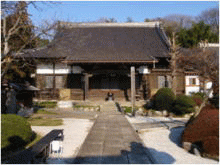 |
 |
| 永源寺山門 |
永源寺本堂 |
弁天堂 |
|
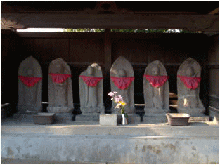 |
 |
 |
| 六地蔵 |
庚申塔 |
子育延命地蔵 |
|
| 坂を下り十字路を右折すると、交差点の右手に応永26年(1419年)創建の大竜山・永源寺[曹洞宗]がある。本尊は釈迦牟尼仏。道をはさんだ西側の弁天池に弁天堂がある。山門前の右手に明治40年(1907年)造立の子育延命地蔵
/ 山門を潜ると右手に安永2年(1773年)造立の庚申塔 / 左手に寛文3年(1663年)造立の六地蔵がある。本堂は1853年(嘉永6年)に建立されたもの。狭山三十七薬師25番札所になっている。 |
|
| 永源寺:所沢市久米1342 |
|
 |
| 十人坂の地蔵 |
|
| 永源寺から道を戻り、南東へ進む。突き当たりを左折すると、じゅうにん坂交差点がある。直進すると左手に10基の地蔵が並んでいる。左から、元禄6年(1693年)造立の地蔵 / 安永元年(1772年)造立の地蔵 / 宝永2年(1705年)造立の地蔵 / 貞享3年(1686年)造立の地蔵 / 享保16年(1731年)造立の地蔵 / 元禄11年(1698年)造立の地蔵 / 貞享3年(1686年)造立の地蔵 / 元禄9年(1696年)造立の地蔵 / 造立年不明の地蔵 / 造立年不明の地蔵。10基の地蔵は墓石で、道路の拡幅によりこの付近の墓地にあったものを並べたもの。十人坂の由来は、この坂を荷車で登るのに10人の力が必要だったからと云われている。 |
|
 |
 |
 |
| 所沢郷土美術館 |
馬頭観音 |
石橋造立塔 |
|
| じゅうにん坂交差点まで戻り、左折して南東へ道なりに進む。所沢郷土美術館角の交差点を左折すると、所沢郷土美術館の右手に寛政11年(1799年)造立の馬頭観音がある。所沢郷土美術館角の交差点まで戻り、南東へ進む。JA前を右折して吾妻橋を渡る。すぐに右折して川沿いに進むと、左手に安永7年(1778年)造立の石橋造立塔がある。 |
|
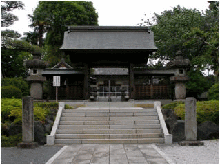 |
 |
 |
| 長久寺 |
吽形力士 |
阿形金剛 |
|
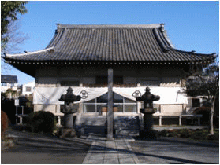 |
 |
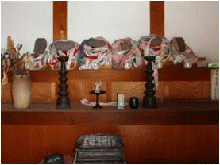 |
| 長久寺本堂 |
地蔵堂 |
寿和婦貴六地蔵 |
|
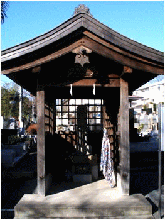 |
 |
 |
| 薬師堂 |
薬師如来と廻国供養塔 |
鐘楼 |
|
| JA前まで戻り、右折して道なりに東へ進む。突き当たりを左折すると、すぐ右手に文永11年(1274年)創建の花向山常行院・長久寺[時宗]がある。本尊は阿弥陀三尊立像。山門を潜ると左手に薬師堂、堂内に天明5年(1785年)造立の薬師如来がある。台座は安永3年(1774年)造立の廻国供養塔になっている。本堂側左手に地蔵堂、堂内に造立年不明の寿和婦貴六地蔵がある。首が無い寿和婦貴地蔵は咳に苦しむことがないことから、風邪や咳に苦しむ人にご利益があると云われている。境内右手に鐘楼がある。 |
|
 |
 |
 |
| 子育地蔵 |
標石(善光寺如来) |
六字名号塔(南無阿弥陀佛) |
|
| 入口右手に平成8年(1996年)造立の子育地蔵、山門前の石段左手に文政5年(1822年)造立の標石(善光寺如来) / 右手に文政7年(1824年)造立の六字名号塔(南無阿弥陀佛)がある。 |
|
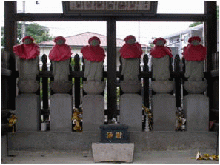 |
 |
 |
| 六地蔵 |
地蔵 |
宝篋印塔 |
|
| 境内に入ると、薬師堂と地蔵堂の間に寛政6年(1794年)造立の六地蔵 / 左手に平成8年(1996年)造立の地蔵と万延元年(1860年)造立の宝篋印塔がある。 |
|
 |
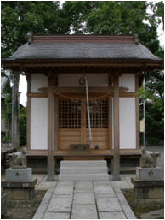 |
 |
| 豊川稲荷 |
旧鎌倉街道道標 |
|
|
右手に明治44年(1911年)愛知の豊川稲荷を勧請した豊川稲荷がある。門前に旧鎌倉街道の道標がある。.ここから先の鎌倉街道は、途切れている。斜めに勢揃橋を通り、弧を描く様に二瀬橋交差点の南側に通じていた。
|
|
| 長久寺:所沢市久米411 |
|
 |
長久寺から南東へ進むと、すぐに勢揃橋北交差点がある。直進して次の変則十字路を右折して南へ進むと、右手の三角地帯に文政元年(1818年)造立の庚申塔がある。
|
| 庚申塔 |
|
 |
 |
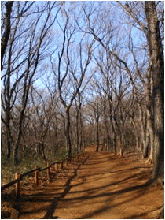 |
| 将軍塚 |
元弘青石塔婆所在跡碑
|
八国山尾根道 |
|
| 庚申塔のところを鋭角に右折して道なりに進むと、勢揃橋北交差点からの旧鎌倉街道に突き当る。左折して柳瀬川に架かる勢揃橋を渡る。勢揃橋は新田義貞の鎌倉攻めのときに、軍をここで勢揃いさせたと云われる橋。正面に八国山が見える。道なりに進むとすぐ松が丘調整池がある。池の西側を通り交差点を直進する。右に大きくカーブするところを直進すると、八国山(標高89.4m)への登り口がある。上野・下野・常陸・安房・相模・駿河・信濃・甲斐の八国が見渡せることが由来と云われている。八国山の周辺は、元弘3年(1333年)新田義貞の鎌倉攻め
/ 建武2年(1335年)北条高時の遺子時行と足利尊氏の弟直義らの戦い / 正平7年(1352年)の武蔵野合戦 などの戦場となったところである。八国山山頂には昭和12年(1937年)造立の将軍塚
/ 昭和12年(1937年)造立の元弘青石塔婆所在跡碑、山麓には久米川古戦場碑がある。 将軍塚は、新田義貞が兵馬を指揮した場所と云われている。元弘の板碑(重文)は、ここにあったものを文化年間(1804年~1818年)に東村山市の徳蔵寺に移したものである。 |
|
|
|
| [寄り道]久米川古戦場跡 / 徳蔵寺 |
|
 |
 |
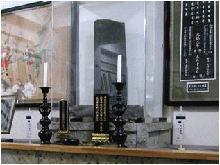 |
| 久米川古戦場碑 |
徳蔵寺 |
元弘の板碑 |
|
| 久米川古戦場碑は八国山南麓の東村山市・西宿公園にある。少し離れた南西方向に、元弘2年(1332年)創建の福壽山・徳蔵寺[臨済宗大徳寺派]がある。武蔵野三十三観音7番札所
/ 狭山三十三観音11番札所になっている。境内の板碑保存館(有料施設)には多数の板碑や民俗資料が収集されており、元弘の板碑(重文)が展示されている。元弘の板碑は、元弘の役で戦死した飽間斎藤一族の菩提を弔った供養碑である。 |
|
|
|
 |
 |
 |
| 佛眼寺本堂 |
地蔵堂 |
六地蔵 |
|
 |
 |
 |
| 一願地蔵 |
二十三夜待供養塔 |
庚申塔 |
|
 |
 |
|
| 法華経千部供養塔 |
宝篋印塔 |
|
|
| 将軍塚から尾根道を鳩峰八幡神社や久米水天宮方面へ進む。道標がところどころにあり、迷うことはない。松が丘中央交差点から北西方向へ進むと、鎌倉時代(1185年頃~1333年)初期創建の王禅山・佛眼寺[真言宗豊山派]がある。多摩新四国八十八ヶ所53番札所になっている。鳩峰八幡神社の別当寺で、梵鐘は鳩峰八幡神社境内にある。参道の右手に、手前から延享3年(1746年)造立の法華経千部供養塔
/ 寛政元年(1789年)造立の庚申塔 / 文政3年(1820年)造立の二十三夜待供養塔、参道の左手に享保10年(1725年)造立の六地蔵がある。本堂の右手に一願地蔵、左手に地蔵堂がある。駐車場側に文化13年(1816年)造立の宝篋印塔がある。 |
|
| 佛眼寺:所沢市久米2445 |
|
 |
 |
| 久米水天宮拝殿 |
拝殿のだるま |
|
| 佛眼寺の角を左折して北へ進む。坂を登ると十字路があり、左折すると福岡県久留米市の久留米水天宮を総本社とする久米水天宮がある。毎年1月5日には初大祭とだるま市が開かれる。 |
|
 |
 |
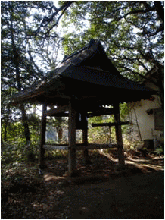 |
| 鳩峯八幡神社鳥居 |
鳩峯八幡神社拝殿 |
佛眼寺の梵鐘 |
|
 |
 |
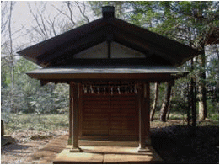 |
| 宝物殿 |
八坂神社 |
八坂神社本殿 |
|
| 十字路を直進すると、左手に延喜21年(921年)創建と云われる鳩峯八幡神社がある。鳥居を潜り参道を進むと、左手に寛永17年(1640年)鋳造の佛眼寺梵鐘 / 右手に宝物殿がある。本殿は見世棚造で、室町時代以前に建立されたのもの。慶長13年(1608年)に屋根を修理した棟札がある。境内に長久寺の西側にあったが、明治40年(1907年)に合社された八坂神社がある。本殿は天保14年(1843年)建立、鳥居は文政11年(1878年)造立。鳩峯八幡神社と久米水天宮は境内が繋がっている。 |
|
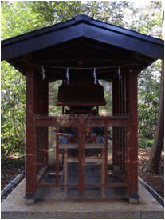 |
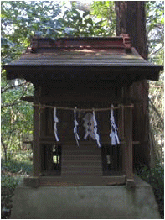 |
 |
| 鎧稲荷神社 |
八幡神社奥社 |
寛政10年造立の石祠 |
|
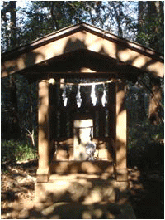 |
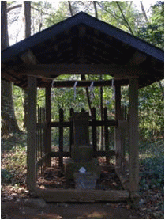 |
鳩峯八幡神社本殿裏に 新田義貞が戦勝を祈願して創建した鎧稲荷神社 八幡神社奥社 寛政10年(1798年)造立の石祠 寛政12年(1800年)造立の神号碑(愛宕山大神) 寛政9年(1797年)造立の石祠 がある。 |
| 神号碑(愛宕山大神) |
寛政9年造立の石祠 |
|
| 鳩峯八幡神社・久米水天宮:所沢市久米2432 |
|
 |
 |
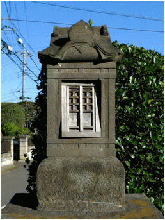 |
| 道標 / 百八十八箇所供養塔 / 馬頭観音 |
馬頭観音 |
稲荷の祠 |
|
| 鳩峰八幡神社の鳥居まで戻り、北へ坂を下る。突き当たりを左折すると十字路があり、北西側の角に造立年不明の道標 / 明和3年(1766年)造立の百八十八箇所供養塔
/ 天保8年(1837年)造立の道標を兼ねた馬頭観音が並んでいる。道標には“北 所沢金山ニ至ル 荒幡ヲ経テ貯水池ニ至ル”と彫られている。馬頭観音は右側面に“右方
山口 八王子みち”左側面に“左方 江戸みち”と彫られている。南西側に造立年不明の稲荷の祠がある。 |
|
 |
 |
十字路を南へ進むと、3方向に分かれる道がある。中央を進み坂を登ると、左手に前峰山・大聖寺[単立]がある。3方向に分かれるところまで戻り、鋭角に左折して西へ進む。5分ほどすると、左手に天明13年(1783年)造立の三夜侍供養塔がある。 |
| 大聖寺 |
三夜侍供養塔 |
|
| 大聖寺:所沢市久米2293-12 |
|
 |
 |
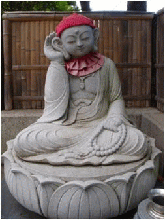 |
| 光蔵寺山門 |
光蔵寺本堂 |
聞くぞう地蔵 |
|
| 道なりに直進すると二車線道路と合流する。南へ進むと右手に、寛和年間(985年~986年)創建の荒幡山・光蔵寺[真言宗豊山派]がある。山門を潜ると、右手に平成19年(2007年)造立の聞くぞう地蔵がある。 |
|
| 光蔵寺:所沢市荒幡499 |
|
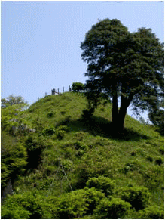 |
 |
 |
| 荒幡富士 |
浅間神社 |
浅間神社拝殿 |
|
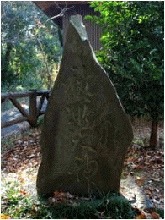 |
 |
 |
| 神号碑 |
日侍供養塔 |
観世音 |
|
| 光蔵寺手前の小道を道なりに西へ進む。ゴルフ場のフェンスに沿って坂を登ると、右手に荒幡富士と明治14年(1881年)創建の浅間神社がある。松尾神社の地に浅間神社を移し、
三島神社 / 氷川神社 / 神明神社 / 松尾神社を合祀する。鳥居の左手に、造立年不明の神号碑(袚所大神)がある。社殿の南側に、明和6年(1769年)造立の日侍供養塔と元禄6年(1693年)造立の観世音がある。日待供養塔には弁財天が彫られている。 |
|
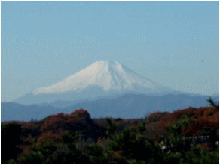 |
 |
荒幡富士(標高119m)は、浅間神社にあった富士塚を15年掛けて移転構築したもの。山頂に明治32年(1899年)造立の石祠がある。晴れた日には富士山を望むことができる。 |
| 荒幡富士からの富士山 |
石祠 |
|
 |
 |
 |
| 神号碑(猿田彦)と祠 |
石祠 |
神号碑(天衣織姫大神) |
|
 |
 |
 |
| 神号碑(天地八百万大神) |
神号碑(松尾大神) |
神号碑(稲荷大神) |
|
| 荒幡富士の登り口に、造立年不明の神号碑(猿田彦) / 祠 / 文化8年(1818年)造立の石祠がある。猿田彦の石仏がある。荒幡富士の斜面には数多くの石碑が点在する。裾野や登山道から、造立年不明の神号碑(天衣織姫大神)
/ 造立年不明の神号碑(天地八百万大神) / 造立年不明の神号碑(松尾大神) / 造立年不明の神号碑(稲荷大神)が見える。 |
|
| 浅間神社:所沢市荒幡748 |
|
 |
 |
 |
| 地蔵 |
地蔵 |
庚申塔 |
|
 |
浅間神社から西へ道なりに下る、右手に田端霊園がある。入口右手に、造立年不明の地蔵 / 造立年不明の地蔵 / 元禄10年(1697年)造立の庚申塔が並んでいる。田端霊園から西へ進む。Y字路を右へ進むと、ほぼ正面に大正14年(1925年)造立の馬頭観音と明治29年(1896年)造立の石橋供養塔が並んでいる。 |
| 馬頭観音と石橋供養塔 |
|
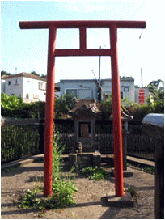 |
 |
 |
| 弁財天 |
本覚院本堂 |
六地蔵 |
|
| 浅間神社から北へ坂を下ると、右手に康暦2年(1380年)創建の月桂山喜福寺・本覚院[真言宗豊山派]がある。本尊は不動明王。入口右手の池に 明和7年(1770年)造立の弁財天石祠がある。墓地への坂の途中に平成12年(2000年)造立の六地蔵がある。 |
|
 |
 |
 |
| 地蔵 |
馬頭観音 |
馬頭観音(日待講中) |
|
| 参道右手に造立年不明の地蔵 / 享保3年(1803年)造立の馬頭観音、左手に文政3年(1820年)造立の馬頭観音(日待講中)がある。 |
|
 |
 |
 |
| 観音 |
宝篋印塔 |
不動明王 |
|
 |
 |
 |
| 地蔵(日待供養) |
馬頭観音(百番供養) |
念仏供養塔 |
|
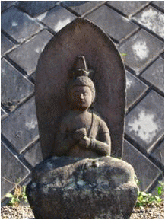 |
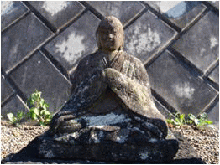 |
 |
| 大日如来 |
大師 |
庚申塔 |
|
| 本堂の南側に平成12年(2000年)造立の観音 / 寛政10年(1798年)造立の宝篋印塔 / 造立年不明の不動明王 / 正徳2年(1712年)造立の地蔵(日待供養)
/ 天明5年(1785年)造立の馬頭観音(百番供養) / 享保4年(1719年)造立の念仏供養塔 / 大日如来 / 大師 / 貞享5年(1688年)造立の庚申塔
がある。 |
|
| 本覚院:所沢市荒幡653 |
|
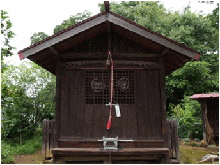 |
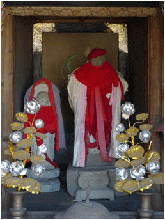 |
 |
| 関地蔵堂 |
堂内の地蔵 |
大正10年造立の地蔵 |
|
| Y字路を左に進む。しばらくすると左手に関地蔵堂がある。堂内に昭和53年(1978年)造立の地蔵[左]と正徳3年(1713年)造立の地蔵[右]、境内左手に大正10年(1921年)造立の地蔵がある。 |
|
| 関地蔵堂:所沢市荒幡268 |
|
| 柳瀬川を歩行者専用の橋で渡る。すぐに右折して突き当たりを道なりに左へ進む。西武狭山線を越えて西へ進むと55号線と交差、左折して南西へ進む。下山口駅入口交差点を左折すると下山口駅がある。 |
|
 |