| 所沢寺社撮影散歩 |
|
| 西武池袋線・狭山ヶ丘駅〜堀之内〜林〜西武池袋線・西所沢駅 |
|
| 狭山ケ丘駅 |
→ |
愛宕神社 |
→ |
中氷川神社 |
→ |
金仙寺 |
→ |
山之神神社 |
→ |
聴松軒 |
→ |
堂坂阿弥陀堂 |
→ |
糀谷八幡神社 |
→ |
願誓寺 |
→ |
松林寺 |
→ |
林神社 |
→ |
八坂神社 |
→ |
狭山ケ丘駅 |
|
|
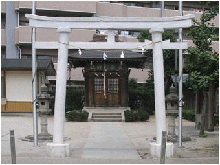 |
 |
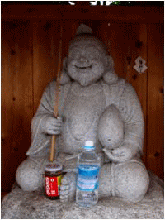 |
| 愛宕神社 |
恵比寿 |
|
 |
 |
 |
| 昭和17年造立の地蔵 |
享保4年造立の地蔵 |
馬頭観音 |
|
| 西武池袋線・狭山ヶ丘駅西口より線路沿いに南東に進むと、左手に愛宕神社がある。狭山ヶ丘1丁目交差点を右折して、県道223号線を南西へ進む。国道463号線バイパスの西狭山ヶ丘1丁目交差点を越えると、右手の祠に恵比寿がある。5分ほどすると、三ヶ島小学校前交差点の南西側に堂がある。
昭和17年(1942年)造立の地蔵 / 享保4年(1719年)造立の地蔵(念仏供養) / 寛政6年(1794年)造立の馬頭観音がある。 |
|
| 愛宕神社:所沢市東狭山ヶ丘1-2993-23 |
|
| 地名の由来:三ヶ島(みかじま) |
| 3つの小集落があり、それを島に見立てて付けられたと云われている。中世末期の古文書や金石文(きんせきぶん)に、三ヶ島が登場している。金石文は、刀剣などの金属や石碑・墓碑などに刻まれた文章。 |
|
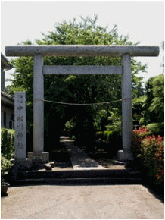 |
 |
 |
| 中氷川神社鳥居 |
中氷川神社拝殿 |
中氷川神社神楽殿 |
|
 |
 |
 |
| 稲荷神社と神明社 |
八坂神社 |
山王社 |
|
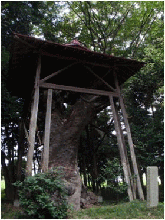 |
 |
 |
| 神木 |
中氷川神社鳥居(南西側) |
庚申塔 |
|
|
三ヶ島農協前交差点を右折して、県道179号線を西へ進む。Y字路を左へ進むと、中氷川神社の鳥居がある。江戸時代には長宮明神と称していた。平安時代に編纂された延喜式神名帳に記載されている神社と云われている。大宮・武蔵国一宮氷川神社と奥多摩・奥氷川神社の中間にあることから、中氷川神社になったと云われている。所沢市山口にも中氷川神社がある。社殿は江戸中期の建立と云われている。社殿の右手に、稲荷神社と神明社
/ 八坂神社 / 山王社がある。奥に柵に囲われた神木がある。この欅は幹回りが約8mの巨木であったが、枯れてしまい根元の部分が保存されている。昔は流鏑馬(やぶさめ)が行われていた参道は、石畳が敷かれている。両側は桜並木となっている。南西側の鳥居から出ると、左手に文化9年(1812年)造立の庚申塔がある。
|
|
| 中氷川神社:所沢市三ケ島5-1691 |
|
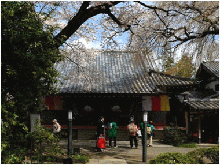 |
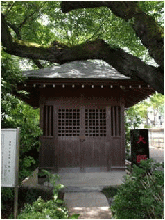 |
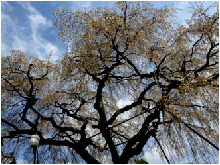 |
| 金仙寺本堂 |
大師堂 |
しだれ桜 |
|
 |
 |
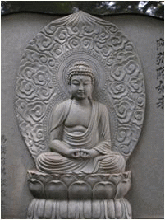 |
| 六地蔵 |
地蔵 |
|
|
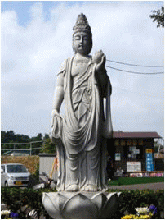 |
中氷川神社の西側から左折して坂を下り、突き当りを右折する。さらに右折して坂道を登ると、平安時代(794年〜1185年頃)創建の別所山西光院・金仙寺[真言宗豊山派]がある。天正18年(1590年)現在地に移転する。本堂左手に、樹齢約140年と云われるしだれ桜がある。八十八ヶ所66番札所になっている大師堂には、昭和9年(1934年)造立の弘法大師と千手観音がある。境内に、平成10年(1998年)造立の六地蔵や平成10年(1998年)造立の聖観音などがある。 |
| 聖観音 |
|
| 金仙寺:所沢市堀之内343 |
|
 |
 |
| 石仏群 |
六地蔵塔 |
|
 |
 |
 |
| 六十六部供養塔 |
寛政6年造立の馬頭観音 |
庚申塔 |
|
 |
 |
 |
| 地蔵 |
光明真言供養塔 |
天保15年造立の馬頭観音 |
|
 |
 |
 |
| 安永8年造立の大乗妙典六十六部供養塔 |
石橋六ヶ所供養塔 |
安永3年造立の大乗妙典六十六部供養塔 |
|
| 本堂への石段を登らずに、坂道を登り切ると左手に石仏石塔群がある。左から、明治5年(1872年)造立の六地蔵塔 / 文化元年(1804年)造立の六十六部供養塔
/ 寛政6年(1794年)造立の馬頭観音 / 宝暦13年(1763年)造立の庚申塔 / 享保4年(1719年)造立の地蔵 / 天保3年(1832年)造立の光明真言供養塔
/ 天保15年(1844年)造立の馬頭観音 / 安永8年(1779年)造立の大乗妙典六十六部供養塔 / 明治27年(1894年)造立の石橋六ヶ所供養塔
/ 安永3年(1774年)造立の大乗妙典六十六部供養塔と並んでいる。 |
|
 |
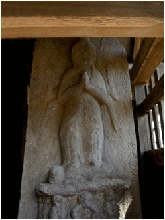 |
石仏石塔群から南へ、道なりに尾根沿いの道を西へ進む。すぐ右手の墓地の角に元禄6年(1693年)造立の庚申塔がある。 |
| 庚申塔 |
|
 |
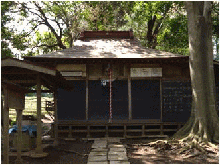 |
|
| 山之神神社鳥居 |
山之神神社社殿 |
|
|
尾根沿いの道を進む。すぐに小路を右へ下る。突き当りを左折すると、“トトロの森13号地”標識がある。すぐ左手に文政11年(1828年)創建と云われる山之神神社の鳥居があり、つづら折りの山道を登ると社殿がある。社殿裏に樹高15m
/ 幹周り4.1mのヤマザクラがある。社殿裏から道なりに進むと、尾根沿いの道に出られる。場所は解りづらい。
|
|
| 山之神神社:所沢市堀之内462 |
|
 |
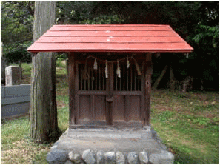 |
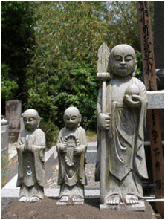 |
| 聴松軒馬頭観音堂 |
祠 |
地蔵 |
|
 |
 |
 |
| 了念仏法師 |
馬鳴尊者 |
不動明王 |
|
 |
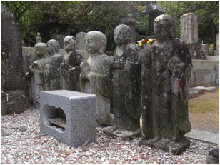 |
 |
| 大日如来 |
六地蔵 |
灯籠兼供養塔 |
|
| 金仙寺まで戻り、中氷川神社から続く道を南へ進む。左手に聴松軒のへの案内看板がある。左折すると突き当たりに聴松軒[真言宗豊山派]がある。青梅・金剛寺から勧請されたと云われ、狭山三十三観音31番札所になっている。馬頭観音堂の右手に、弁財天などを祀る祠がある。2007年5月に訪れた時は石仏が点在していたが、2009年9月には一画にまとめられていた。六地蔵は、修理され新しい地蔵が加わっている。左側に
/ 地蔵 / 墓石 / 造立年不明の了念仏法師、正面に享保19年(1734年)造立の馬鳴(めみょう)尊者 / 宝永8年(1711年)造立の不動明王 / 宝永7年(1710年)造立の大日如来、右手に造立年不明の六地蔵 / 造立年不明の供養塔(光明真言千四百万遍・六字名号三億遍)を兼ねた灯籠がある。 |
|
| 聴松軒:所沢市堀之内46 |
|
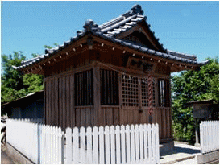 |
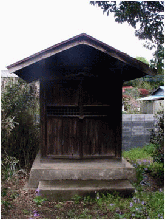 |
中氷川神社まで戻り、県道179号線を西へ進む。東側にある台バス停から南へ進む。道なりにU字に進路を変えたところに、御霊(ごりょう)権現がある。県道179号線を西へ進むと、西側にも台バス停がある。次の交差点を右折して北へ進む。左手に墓地があり、左側にある小道の突き当たりに、高根薬師堂先がある。狭山三十七薬師14番札所になっている。 |
| 御霊権現 |
高根薬師堂 |
|
| 高根薬師堂:所沢市糀谷171 |
| 御霊権現:所沢市堀の内540 |
|
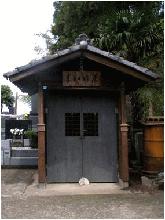 |
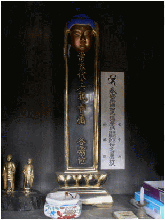 |
 |
| 堂坂阿弥陀堂 |
宝暦5年造立の地蔵 |
|
 |
 |
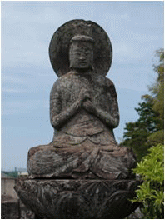 |
| 享保2年造立の地蔵 |
六地蔵幢 |
大日如来 |
|
 |
 |
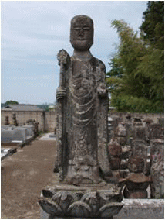 |
| 安政4年造立の地蔵 |
阿弥陀三尊板碑 |
弘化4年造立の地蔵 |
|
| 県道179号線を西へ、糀谷バス停があるところを左折して道なりに進む。Y字路を左折して坂を登ると、願誓寺墓地入口に薬師如来と書かれた堂坂阿弥陀堂がある。狭山三十七薬師13番札所になっている。奥に宝暦5年(1755年)造立の地蔵(六十六部日本廻国)
/ 享保2年(1717年)造立の地蔵 / 天保13年(1842年)造立の六地蔵 / 寛政5年(1793年)造立の大日如来(坂東・西国・秩父霊場供養塔)
/ 墓石 / 安政4年(1857年)造立の地蔵 / 造立年不明の阿弥陀三尊板碑 / 弘化4年(1847年)造立の地蔵が並んでいる。 |
|
| 堂坂阿弥陀堂:所沢市糀谷121 |
|
 |
 |
 |
| 糀谷八幡神社 |
糀谷八幡神社社殿 |
山神社 / 浅間神社 / 八雲神社 |
|
 |
堂坂阿弥陀堂から道なりに南へ10分ほど進むと、右手に江戸時代(1603年〜1867年)初期創建の糀谷八幡神社がある。9月29日に行われていた流鏑馬神事は、養蚕農家の蚕が当たる様にと行われていたもの。現在は29日に近い日曜日に行われている。 |
| 金刀比羅神社 / 愛宕神社 / 三峯神社 |
|
| 糀谷八幡神社:所沢市糀谷78 |
|
|
|
| [寄り道] |
|
 |
 |
県道179号線まで戻り、左折して西へ進む。入間市に入って最初の信号が萩原交差点で、南西側の角に地蔵がある。萩原交差点を左折して南へ進むと、西勝院や“さいたま緑の森博物館”へ至る。 |
|
|
|
 |
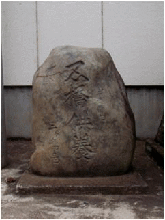 |
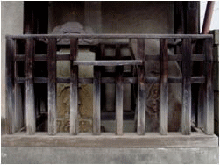 |
| 万延元年造立の庚申塔 |
石橋供養塔 |
庚申塔 |
|
| 県道179号線を東へ進む。三ヶ島農協前交差点を左折して、浅間山通りを北へ進む。5分ほどすると右手に嘉永2年(1849年)造立の石橋供養塔 / 灯篭 / 万延元年(1866年)造立の庚申塔 、小道を挟んで堂に安永4年(1775年)造立の庚申塔(左) / 嘉永3年(1850年)造立の庚申塔(右・自然石)がある。 |
|
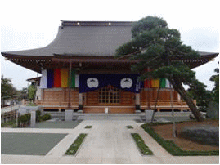 |
浅間山通りを北へ10分ほど進むと、左手に願誓寺への案内看板がある。左折すると左手に願誓寺[真宗大谷派]がある。 |
| 願誓寺本堂 |
|
| 願誓寺:所沢市糀谷415 |
|
 |
 |
 |
|
元禄10年造立の庚申塔
|
元禄14年造立の庚申塔 |
元禄3年造立の庚申塔 |
|
 |
 |
 |
| 万延元年造立の庚申塔 |
馬頭観音 |
光明真言供養塔 |
|
| 願誓寺から浅間山通りに戻る。北へ進むとすぐ右手のブロック塀に、石仏群がある。奥左手より、元禄10年(1697年)造立の庚申塔 / 元禄14年(1701年)造立の庚申塔
/ 元禄3年(1690年)造立の庚申塔 / 万延元年(1860年)造立の道標を兼ねた庚申塔、手前左手より寛政5年(1793年)造立の馬頭観音
/ 元禄16年(1703年)造立の光明真言供養塔と並んでいる。万延元年(1860年)造立の道標を兼ねた庚申塔には、“北 扇町屋はんのう 西 箱根崎
五日市 東 川越 所沢 南 みかしま 府中”と彫られている。 |
|
 |
浅間山通りを北へ進む。林交差点を左折して西へ進むと、右手に文久3年(1863年)造立の庚申塔がある。 |
| 庚申塔 |
|
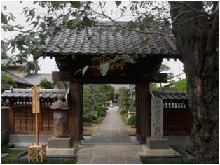 |
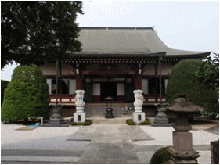 |
 |
| 松林寺山門 |
松林寺本堂 |
薬師六角堂 |
|
 |
 |
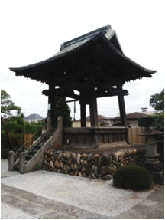 |
| 閻魔堂 |
閻魔
|
鐘楼 |
|
| 林交差点まで戻り、浅間山通りを北へ進む。右手に承応2年(1653年)創建の吟竜山・松林寺[曹洞宗]がある。 武蔵野三十三観音15番札所 / 狭山三十三観音30番札所になっている。本尊は釈迦牟尼仏、札所本尊は千手観音。林一丁目の林神社付近にあった狭山三十七薬師15番札所の神興寺は松林寺に合併される。狭山三十七薬師の薬師は不明になっている。境内に平成3年(1991年)再建された薬師六角堂や閻魔堂がある。 |
|
 |
 |
 |
| 六地蔵幢 |
結界石 |
参道 |
|
 |
 |
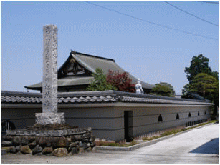 |
| 吽形力士 |
阿形金剛 |
浅間山通り側の参道 |
|
| 山門前左側に文政2年(1819年)造立の六地蔵幢、右側に明和6年(1769年)造立の結界石(大乗妙典六十六部供養)がある。山門を潜ると、平成5年(1993年年)造立の吽形力士(左)と阿形金剛(右)がある。浅間山通り側にも参道がある。 |
|
 |
 |
 |
| 宝篋印塔 |
大日如来 |
一葉観音 |
|
 |
 |
 |
| 観音 |
十三重の塔 |
玄奘三蔵 |
|
 |
 |
 |
|
六地蔵 |
庚申塔 |
|
 |
 |
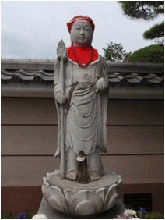 |
| 聖観音 |
享保18年造立の地蔵 |
昭和50年造立の地蔵 |
|
| 境内右手の鐘楼前に、寛政11年(1799年)造立の宝篋印塔(妙法蓮華経) / 嘉永3年(1850年)造立の大日如来、 境内左手に、一葉観音 /
十三重の塔 / 青銅造りの玄奘三蔵などがある。薬師六角堂の裏手に六地蔵、浅間山通り側の参道側に文政3年(1820年)造立の庚申塔 / 寛政9年(1797年)造立の聖観音
/ 享保18年(1733年)造立の地蔵 / 昭和50年(1975年)造立の地蔵がある。 |
|
| 松林寺:所沢市林2-147 |
|
 |
 |
 |
| 石橋供養塔 |
百万遍供養塔 |
地蔵 |
|
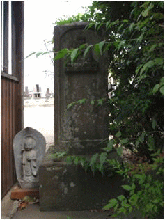 |
松林寺から浅間山通りを斜めに横断して西へ進む。突き当たりを右折すると、右手に石仏群がある。左から、天保3年(1832年)造立の石橋供養塔 / 文政3年(1820年)造立の百万遍供養塔 / 宝暦2年(1752年)造立の地蔵 / 安永3年(1774年)造立の大師(四国八十八ヶ所□二世安楽)と並んでいる。 |
| 大師 |
|
 |
 |
 |
| 林神社 |
林神社社殿 |
境内社 |
|
| 直進して林川を越える。突き当りを左折すると、すぐ右手に天正年間(1575年〜1585年)創建の林神社がある。明治40年(1907年)に十代社から改称する。7月第4土曜日・日曜日に行われる天王祭は、林神社〜八坂神社〜林と巡行する。 |
|
| 林神社:所沢市林1-383 |
|
 |
 |
林神社の参道の途中にある十字路を左折して北へ進む。林きた交差点から延びる比較的広い道を横断、道なりに進む。Y字路を北西へ進むと、左手の茶畑越しに稲荷神社の鳥居が見える。鬱蒼とした木々に囲まれている。入間市との境に近い。 |
| 稲荷神社鳥居 |
稲荷神社社殿 |
|
| 稲荷神社:所沢市林1丁目 |
|
 |
 |
林きた交差点から延びる道を右折して東へ進む。林きた交差点を左折して北へ進むと、Y字路に昭和56年(1981年)造立の獣魂碑と文化年間(1804年〜1817年)造立の馬頭観音が並んでいる。 |
| 獣魂碑 |
馬頭観音 |
|
 |
 |
浅間山通りを林交差点まで戻る。左折して東へ進む。3本目の小道を左折すると、右手に八坂神社がある。7月第4土・日曜日に行われる天王様は、林神社〜八坂神社〜林と巡行する。 |
| 八坂神社鳥居 |
八坂神社社殿 |
|
| 八坂神社・所沢市林2-462 |
|
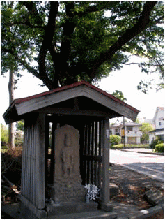 |
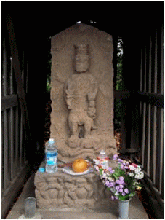 |
 |
| 林追分庚申塔 |
地蔵 |
|
| 通りに戻り、東へ進む。林小前交差点の点前にY字路があり、寛政4年(1792年)造立の道標を兼ねた林追分庚申塔がある。台座の右側面に“右 江戸道”左側面に 左
川越海道 新川岸”と彫られている。Y字路を右方向に進むとすぐに、五差路の林小学校前交差点がある。北東方向へしばらく進むと、和ヶ原2丁目交差点で国道463号線バイパスと交差する。そのまま直進する。しばらくすると西武池袋線の線路の少し手前の右手に、平成2年(1990年)造立の地蔵がある。踏切手前を右折して線路沿いに進むと西武池袋線・狭山ヶ丘駅に至る。 |
|
|
 |