| 所沢寺社撮影散歩 |
|
| 西武池袋線・狭山ヶ丘駅〜狭山湖外周道路〜西武狭山線・西武球場前駅 |
|
| 狭山ケ丘駅 |
→ |
愛宕神社 |
→ |
常楽院 |
→ |
八幡神社 |
→ |
狭山湖外周道路 |
→ |
金乗院 |
→ |
不動寺 |
→ |
西武球場前駅 |
|
|
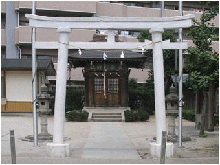 |
 |
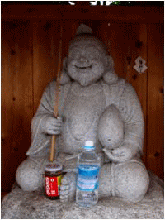 |
| 愛宕神社 |
恵比寿 |
|
 |
 |
 |
| 昭和17年造立の地蔵 |
享保4年造立の地蔵 |
馬頭観音 |
|
| 西武池袋線・狭山ヶ丘駅西口より線路沿いに南東に進むと、左手に愛宕神社がある。狭山ヶ丘1丁目交差点を右折して、県道223号線を南西へ進む。国道463号線バイパスの西狭山ヶ丘1丁目交差点を越えると、右手の祠に恵比寿がある。5分ほどすると、三ヶ島小学校前交差点の南西側に堂がある。 昭和17年(1942年)造立の地蔵 / 享保4年(1719年)造立の地蔵(念仏供養) / 寛政6年(1794年)造立の馬頭観音がある。 |
|
| 愛宕神社:所沢市東狭山ヶ丘1-2993-23 |
|
| 地名の由来:三ヶ島(みかじま) |
| この地には当初3つの小集落があり、それを島に見立てて付けられたと云われている。中世末期の古文書や金石文(きんせきぶん)に、三ヶ島が登場している。金石文は、刀剣などの金属や石碑・墓碑などに刻まれた文章のことをいう。 |
|
 |
 |
 |
| 常楽院本堂 |
白玉石権現堂 |
弁財天堂 |
|
 |
三ヶ島農協前交差点を左折して、県道179号線を東へ進む。早稲田大学入口交差点の南東側に、和銅年間(708〜715年)創建の長坂山薬王寺・常楽院[真言宗豊山派]がある。本尊は不動明王、武蔵村山市の真福寺の末寺。狭山三七薬師17番札所になっている。境内を進むと右手に本堂、左手の丘に白玉石権現堂
/ 弁財天堂 / 薬師堂がある。 |
| 薬師堂 |
|
 |
 |
 |
| 弘法大師一千百年御遠忌記念碑 |
造立年不明の馬頭観音 |
庚申塔 |
|
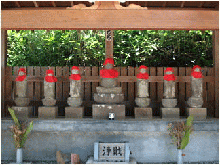 |
 |
境内に入ると、右手に昭和9年(1934年)造立の弘法大師一千百年御遠忌記念碑、左手に造立年不明の馬頭観音と慶応2年(1869年)造立の庚申塔がある。さらに進むと左手に寛延4年(1751年)造立の六地蔵、中央に寛延4年(1751年)造立の大日如来がある。 |
| 六地蔵・大日如来 |
大日如来 |
|
 |
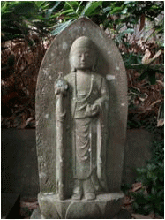 |
本堂正面の丘に、天明2年(1782年)造立の馬頭観音と延宝4年(1676年)造立の愛宕地蔵がある。 |
| 天明2年造立の馬頭観音 |
愛宕地蔵 |
|
 |
 |
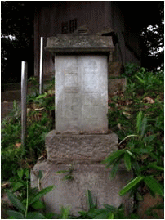 |
| 経典書写供養塔 |
造立年不明の石祠 |
造立年不明の石祠 |
|
 |
 |
 |
| 造立年不明の石祠 |
造立年不明の石祠 |
造立年不明の石祠 |
|
|
白玉石権現堂への石段を登ると、右手に文化5年(1808年)造立の経典書写供養塔や造立年不明の石祠が5基並んでいる。
|
|
| 常楽院:所沢市三ヶ島2-667 |
|
 |
常楽院から県道179号線を東へ進む。早稲田大学入口交差点と大日堂交差点の中間にある最初の十字路を右折する。南へ進むと左手に明治24年(1891年)造立の馬頭観音がある。 |
| 馬頭観音 |
|
 |
 |
 |
| 天保4年造立の庚申塔 |
享和2年造立の庚申塔 |
享和2年造立の地蔵 |
|
 |
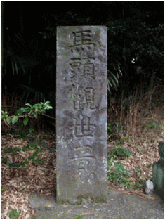 |
 |
| 文化2年造立の馬頭観音 |
文政3年造立の馬頭観音 |
安永5年造立の地蔵 |
|
|
常楽院の東側の道を南東へ進む。5分ほどすると、左手の角に天保4年(1833年)造立の庚申塔がある。右側面に“石橋供養塔”と彫られている。左折してしばらく進み、突き当りを右折する。さらに右折すると右手に享和2年(1802年)造立の庚申塔と享和2年(1802年)造立の地蔵がある。直進して進むと、右手に文化2年(1805年)造立の馬頭観音がある。道標を兼ねており、右側面に“右
川越 扇町谷”左側面に“飯能 左 青梅ぢ”と彫られている。道なりに進むと、道は南へ進路を変える。十字路を直進すると、突き当りに文政3年(1820年)造立の馬頭観音と安永5年(1776年)造立の地蔵がある。馬頭観音は道標を兼ねており、左側面に“東ハ所沢”正面に“きた道
はんのふ”右側面に“西ハ山口道”と彫られている。
|
|
 |
 |
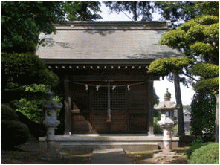 |
| 八幡神社 |
八幡神社 |
湯殿神社 |
|
 |
 |
 |
| 八雲神社 |
西参道 |
庚申塔 |
|
| 左折して5分ほどすると、突き当りに八幡神社がある。拝殿の左手に湯殿神社と八雲神社がある。西参道の階段を降りると、鳥居の左側に天保12年(1841年)造立の庚申塔(石橋供養塔)がある。道標も兼ねており、正面に“扇町谷
川越”右側面に“八王子 山口”と彫られている。 |
|
| 八幡神社:所沢市三ケ島1-212 |
|
 |
 |
西参道から北西へ進み、八幡神社前交差点を右折する。5分ほどすると、右手に箙(えびら)の梅がある。箙は矢を入れて背負う武具の一つで、正平7年(1352年)小手指ヶ原の戦いで足利軍の一隊が梅の枝を箙に差して戦ったと云われている。“箙の梅”はそのなごりを留めるため、東川沿いにあった梅樹の1本を移植したものである。八幡神社前交差点方向に、しばらく道なりに南西へ進む。10分ほどすると右手に社がある。 |
| 箙の梅 |
社 |
|
 |
 |
 |
| 聖観音 |
勝軍地蔵 |
|
| 狭山湖外周道路に突き当り、右折して北西へ進む。墓地の前に享保6年(1721年)造立の聖観音がある。台座に六十六部供養と彫られている。狭山湖外周道路を戻り、道なりに進む。途中に根古屋城跡への道があるが、閉鎖されており立ち入ることはできない。三角路の真ん中に、安永4年(1775年)造立の勝軍地蔵がある。道標を兼ねており、左側面に“左ハ山口道”右側面に“右ハ村山道”と彫られている。 |
|
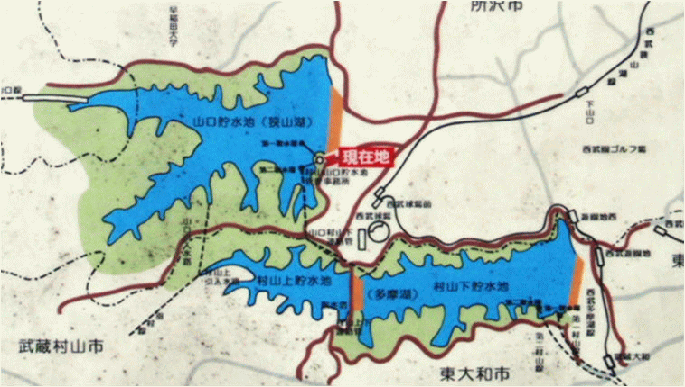 |
| 狭山湖堰堤南側の案内板 |
|
| 昭和9年(1934年)に完成した山口貯水池(狭山湖)は、東京都の水源となっている。湖底に沈んだ佛蔵院 / 青照寺 / 天満天神社は移転、七社神社は山口・中氷川神社に合社される。 |
|
 |
 |
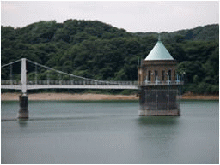 |
| 山口貯水池堤体 |
山口貯水池(北東側) |
第一取水塔 |
|
| 三角路を右方向へ、狭山湖外周道路を東へ進む。狭山自然公園から散策路を南へ、狭山湖堰堤を進む。右手に第一取水塔が見えてくる。狭山自然公園を出てしばらくすると、左手に不動寺の桜井門がある。三差路を左折すると、左手に金乗院の千体観音堂山門がある。不動寺、金乗院いずれも裏側になる。 |
|
|
|
| [寄り道]玉湖神社 |
|
 |
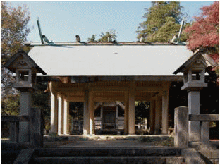 |
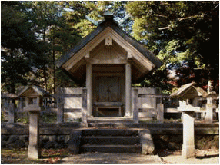 |
| 玉湖神社 |
|
| 三差路を右折して西へ進むと、左手に昭和9年(1934年)に創建された玉湖(たまのうみ)神社がある。山口貯水池(狭山湖)と村山貯水池(多摩湖)に挟まれた武蔵大和市側にある。自治体である東京都の所有が問題となり、昭和42年(1967年)に“御霊遷し”が行われた。 |
|
|
|
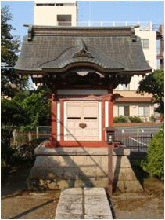 |
 |
 |
| 弁天堂 |
仁王門 |
閻魔堂 |
|
 |
 |
 |
| 六地蔵 |
新田義貞公霊馬堂 |
|
|
不動寺の桜井門右手の坂を下ると、弘仁年間(810年〜824年)創建の吾庵山・金乗院[真言宗豊山派]の正面に出る。山口観音の名で知られている。本尊は行基作と云われる秘仏の千手観音。狭山三十三観音1番札所
/ 武蔵野三十三観音13番札所 / 多摩新四国八十八ヶ所52番・65番札所・67番札所・77番札所・79番札所 / 武蔵野七福神(布袋尊)になっている。道をはさんで、江戸中期に建立された仁王門の反対側に弁天堂がある。仁王門を潜ると、左手に閻魔堂がある。石段の手前左右に、享保3年(1718年)造立の六地蔵がある。石段を登ると、左手に手水舎、右手に新田義貞公霊馬堂がある。
|
|
 |
 |
 |
| 安永9年(1780年)地蔵 |
正徳3年(1713年)地蔵 |
文化7年(1810年)六地蔵幢 |
|
 |
 |
 |
| 元禄14年(1701年)地蔵 |
布袋尊 |
奥多摩新四国八十八ヶ所52番 |
|
 |
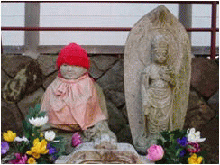 |
 |
| 奥多摩新四国八十八ヶ所67番 |
奥多摩新四国八十八ヶ所65番 |
奥多摩新四国八十八ヶ所77番 |
|
| 手水舎側に、安永9年(1780年)造立の地蔵 / 正徳3年(1713年)造立の地蔵 / 文化7年(1810年)造立の六地蔵幢 / 元禄14年(1701年)造立の地蔵などが並んでいる。新田義貞公霊馬堂の右手には、布袋尊
や昭和9年(1934年)に開創された奥多摩新四国八十八ヶ所などが並んでいる。奥多摩新四国八十八ヶ所は、52番(大山寺)弘法大師と十一面観音 /
67番(小松尾寺)弘法大師と十一面観音 / 65番(三角寺)弘法大師と聖観音 / 77番(道隆寺)弘法大師と薬師如来になっている。鐘楼付近に79番弘法大師と十一面観音がある。 |
|
 |
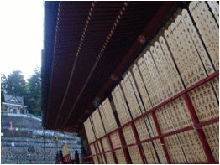 |
 |
| 本堂 |
本堂 |
マニ車 |
|
 |
 |
 |
| 地蔵堂と七福神堂 |
天女稲荷神社 |
住吉神社(勢至堂) |
|
| 石段を登ると、宝暦年間(1751〜1764年)建立の本堂がある。本堂の天井には、墨絵の“鳴き竜”が描かれている。本堂の回廊にはマニ車があり、願い事を念じて祈願の鐘を廻しながら本堂を一周すると叶うと云われている。本堂の左手に、高野山の引導地蔵を紹来した“ぽっくりさん”の地蔵堂と七福神堂がある。左後方には、大田道灌の家来が奉納した天女稲荷神社と文化3年(1806年)創建の住吉神社(勢至堂)がある。 |
|
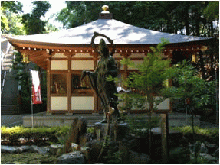 |
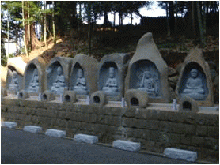 |
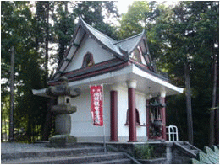 |
| 大日堂 |
石仏群 |
観音堂 |
|
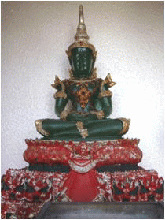 |
 |
 |
| 観音堂 |
五重塔(千体観音堂) |
千体観音堂山門 |
|
|
本堂から右手方向へ進むと大日堂、その左手に石仏群がある。五重塔(千体観音堂)方向へ登ると、途中にも観音堂がある。五重塔(千体観音堂)の後ろ側に、トンネルで回れる奥の院に四国三十三ヶ所観音本尊写の石仏が33基ある。
|
|
| 金乗院:所沢市上山口2203 |
|
 |
| 入口の境内案内板 |
|
|
金乗院の仁王門から北東に、西武球場駅方向へ進む。5分ほどすると、左手に昭和50年(1975年)創建の狭山山・不動寺[天台宗]がある。狭山不動の名で知られている。本尊は不動明王。昭和26年(1951年)西武鉄道によりユネスコ村が開園、文化財保護の目的で各地の由緒ある建物を移築したのが始まりである。ユネスコ村は平成2年(1990年)閉園になっている。
|
|
 |
 |
 |
| 勅額門 |
御成門 |
丁子門 |
|
| 東京・芝増上寺にあった、勅額門(ちょくがくもん) / 御成門 / 丁子門(ちょうじもん)は、重文。勅額門と御成門は、台徳院(徳川秀忠)廟に寛永9年(1632年)徳川家光によって建立されたもの。丁子門は、崇源院(徳川秀忠夫人)霊牌所通用門として寛永9年(1632年)徳川家光によって建立されたもの。淀君(茶々)と京極高次夫人(初)は、徳川秀忠夫人(江)の姉にあたる。 |
|
 |
 |
 |
| 総門 |
本堂 |
本堂右手の石燈籠 |
|
| 勅額門から御成門へと石段を登る。左へ進むと右手に総門がある。総門は、元長州藩主毛利家の江戸屋敷に建立された門。総門を潜ると本堂があり、石燈籠が並ぶ。以前の本堂は京都・東本願寺から移築された七間堂だったが、平成13年(2001年)に不審火によって全焼する。石燈籠は台徳院霊廟から移設されたものである。 |
|
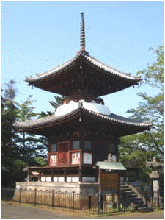 |
 |
 |
| 第一多宝塔 |
灯籠 |
第二多宝塔 |
|
| 本堂右手に、大阪府高槻市梶原・畠山神社から移築した第一多宝塔がある。弘治元年(1555年)美濃国丹波守が建立したと云われている。傍らに灯籠がある。総門を出て桜井門への途中に、第二多宝塔がある。永享7年(1435年)兵庫県東條町・椅鹿寺に、播磨国守護・赤松満男教康が建立したもの。 |
|
 |
 |
 |
| 康信寺 |
大黒堂 |
羅漢堂山門 |
|
 |
 |
|
| 羅漢堂 |
桜井門 |
|
|
| 第二多宝塔の左手に康信寺、右手に大黒堂がある。康信寺は、西武グループ創設者の堤康次郎が、孔子・孟子・子思子を安置した孔子廟。大黒堂は奈良・極楽寺に建立された柿本人麿の歌塚堂で、当時の歌人達が歌会を開いた堂であると云われている。本尊は東叡山寛永寺山内の見明院の大黒天。大黒堂の右手の階段をのぼると、羅漢堂山門がある。海外貿易で天下の糸平と云われた生糸商人、虎の門・田中平八郎宅の門。羅漢堂は、明治28年(1895年)井上馨が屋敷内に建立したもの。唐金灯籠は、台徳院廟に全国の大名から献納された。羅漢堂の左手にある桜井門は、奈良県十津川の桜井寺の山門。 |
|
 |
 |
 |
| 書院晴明閣 |
弁天堂 |
鐘楼 |
|
本堂裏手の坂をのぼると、右手に昭和52年(1977年)建立の書院清明閣がある。左方向に
弁天堂がある。彦根市吉沢町・清涼寺に、井伊直孝の息女が父の追善菩提のため建立した清涼寺経蔵。万治2年(1659年)〜元禄6年(1693年)間の建立と云われている。弁財天は、上野・東叡山寛永寺の現龍院弁財天。すぐに鐘楼がある。奈良・興福寺より京都・高田寺に移築された鐘楼。 |
|
 |
 |
 |
| 弁天堂〜鐘楼間の石仏 |
|
| 弁天堂〜鐘楼間は、石仏が多い。境内にある23基の石仏は、東京芝プリンスホテルの傾斜地にあったもの。 |
|
| 不動寺:所沢市上山口2214 |
|
| 勅額門を出て北東へ進むと、西武球場前駅が見えて来る。 |
|
|
 |