| 所沢寺社撮影散歩 |
|
| 西武池袋線・狭山ヶ丘駅〜三ヶ島〜西武池袋線/狭山線・西所沢駅 |
|
| 狭山ケ丘駅 |
→ |
愛宕神社 |
→ |
妙善院 |
→ |
慈眼庵 |
→ |
宝玉院 |
→ |
三ケ島稲荷神社 |
→ |
実在寺別院 |
→ |
旧青梅街道 |
→ |
西所沢駅 |
|
|
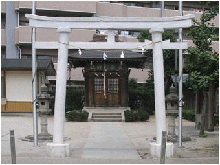 |
 |
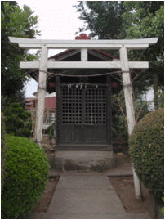 |
| 愛宕神社 |
金山神社 |
|
| 西武池袋線・狭山ヶ丘駅西口より線路沿いに南東に進むと、左手に愛宕神社がある。狭山ヶ丘1丁目交差点を右折して、県道223号線を南西へ進む。463号線の西狭山ヶ丘1丁目交差点を越える。しばらくすると左手に三ヶ島中学校があり、三ヶ島中学校前交差点を左折する。次の交差点を左折すると、左手に金山神社がある。 |
|
| 愛宕神社:所沢市東狭山ヶ丘1-2993-23 |
| 金山神社:所沢市三ケ島1402 |
|
| 地名の由来:三ヶ島(みかじま) |
| 3つの小集落があり、それを島に見立てて付けられたと云われている。中世末期の古文書や金石文(きんせきぶん)に、三ヶ島が登場している。金石文は、刀剣などの金属や石碑・墓碑などに刻まれた文章。 |
|
 |
 |
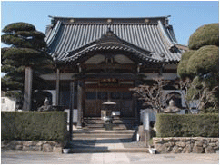 |
| 妙善院山門 |
妙善院仁王門 |
妙善院本堂 |
|
 |
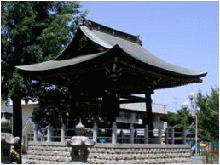 |
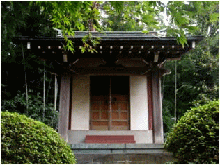 |
| 妙善院寺務所 |
鐘楼 |
金毘羅大権現 |
|
| 三ヶ島幼稚園の手前を左折すると、天正4年(1576年)創建の光輪山三ヶ島寺・妙善院[曹洞宗]がある。狭山三十三観音33番札所 / 武蔵野三十三観音14番札所になっている。 |
|
 |
 |
 |
| 地蔵 |
結界石 |
三山供養塔 |
|
| 階段を登ると山門手前の左手に享保13年(1728年)造立の地蔵、右手に寛政9年(1797年)造立の結界石がある。仁王門を潜る手前右手に、慶応3年(1868年)造立の三山供養塔がある。 |
|
 |
 |
 |
| 昭和51年造立の地蔵 |
十三重塔 |
慈母観音 |
|
 |
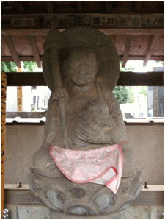 |
 |
| 弘化2年造立の地蔵 |
天保9年造立の地蔵 |
嘉永3年造立の地蔵 |
|
| 仁王門を潜ると正面に本堂、右手に寺務所がある。本堂までの左手に金毘羅大権現 / 無縁仏の中央に昭和51年(1976年)造立の地蔵 / 昭和53年(1978年)造立の十三重塔がある。右手に昭和62年(1987年)造立の慈母観音と鐘楼がある。その先左手の堂に、弘化2年(1845年)造立の地蔵
/ 天保9年(1838)造立の地蔵 / 嘉永3年(1850年)造立の地蔵と並んでいる。 |
|
| 妙善院:所沢市三ヶ島3-1410 |
|
 |
妙善院から東へ進み十字路を右折すると、左手の三角地帯に明治3年(1870年)造立の馬頭観音がある。右側面に石橋再建供養塔と彫られている。 |
| 馬頭観音 |
|
 |
 |
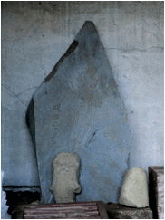 |
| 目印の大木 |
仁平地蔵 |
地蔵(線刻) |
|
| 馬頭観音のある三角地帯から北東へ進む。この道は463号線の若狭3交差点に至る道である。5分ほどすると、左手の畑に大きな木が見てくる。左折して農道を進むと、大きな木の下に貞享3年(1686年)造立の地蔵
/ 祠に明治30年(1897年)造立の地蔵(線刻)がある。昔この辺りで戦があり、供養のために村田仁兵衛(仁平)が造立したと云われている。仁平地蔵と呼ばれ、愛宕山大権現と彫られている。地蔵(線刻)は明治30年(1897年)に赤痢が流行したときに造立されたもの。 |
|
 |
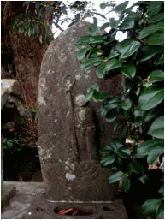 |
 |
| 慈眼庵 |
慈眼庵・地蔵 |
昭和17年造立の地蔵 |
|
 |
 |
 |
| 享保4年造立の地蔵 |
馬頭観音 |
宝玉院 |
|
 |
 |
 |
| 宝玉院多摩新四国八十八ヶ所 |
クロスエの家 |
クロスエの家 |
|
| 妙善院から金山神社方向に戻り、交差点を直進する。しばらく道なりに進むと、右手に慈眼庵[曹洞宗]がある。狭山三十三観音32番札所になっている。札所本尊は聖観音。堂は昭和6年(1931年)に建立されたもの。境内に延宝8年(1680年)造立の地蔵
/ 造立年不明の石祠(稲荷神社)がある。慈眼庵を右折して北西へ進み、県道223号線を右折して北東へ進む。三ヶ島小学校前交差点の南西側に堂がある。
昭和17年(1942年)造立の地蔵 / 享保4年(1719年)造立の地蔵(念仏供養) / 寛政6年(1794年)造立の馬頭観音がある。慈眼庵まで戻り、南西方向に直進する。道は東へ進路が変わり、左手に寛永年間(1624年〜1644年)創建の稲荷山・宝玉院[真言宗豊山派]がある。多摩新四国八十八ヶ所47番札所になっている。昭和9年(1934年)造立の大日如来と阿弥陀如来、手前左に造立年不明の地蔵がある。東へ進むと左手に旧和田家住宅(クロスエの家)、敷地内に社がある。平成25年(2013年)主屋・製茶工場・土蔵の3棟が、国登録有形文化財になる。 |
|
| 慈眼庵:所沢市三ヶ島5-820 |
| 宝玉院:所沢市三ヶ島3-1158 |
| 旧和田家住宅:所沢市三ヶ島3-1169-1 |
|
 |
 |
 |
| 馬頭観音 |
三ヶ島稲荷神社 |
三ヶ島稲荷神社 |
|
 |
 |
 |
| 地蔵 |
庚申塔 |
供養塔 |
|
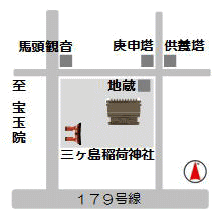 |
東へ進み変則十字路を右折する。左手に文政11年(1828年)造立の馬頭観音がある。道標を兼ねており、左側面に“西 青梅道 北 扇町谷”右側面に“東
所沢 江戸道 南 山口道”と彫られている。すぐ左手に三ヶ島稲荷神社がある。明治の神仏分離のとき廃寺となった、湯殿山大権現を祀っていた照明院(大日堂)と湯殿神社の跡地に移転する。直進すると大日堂交差点で、名前のみ残る。大日堂の大日如来は宝玉院に移されている。三ヶ島稲荷神社の右手東側の道を北へ進む。十字路の南西側(三ヶ島稲荷神社境内)に享保4年(1719年)造立の地蔵
/ 北西側に弘化3年(1846年)造立の庚申塔 / 北東側に文化4年(1807年)造立の供養塔(三山供養 / 百番供養 / 石橋供養)がある。供養塔の上部に見えるのは、大日如来。 |
| 三ヶ島稲荷神社界隈 |
|
| 三ヶ島稲荷神社:所沢市三ケ島3-885-1 |
|
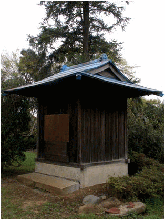 |
 |
 |
| 内出薬師堂 |
地蔵 |
|
| しばらく道なりに茶畑を北へ進むと、左手に内出薬師堂がある。狭山三十七薬師18番札所になっている。所属する妙善院は、曹洞宗。右手の墓地に、左側:享保4年(1719年)造立の地蔵(念仏供養)
/ 右側:明治5年(1872年)造立の地蔵がある。 |
|
| 内出薬師堂:所沢市三ヶ島3-1135 |
|
 |
 |
 |
| 馬頭観音 |
石橋再建供養塔 |
不動橋石橋供養塔 |
|
| 十字路まで戻り直進、県道179号線を左折して東へ進む。狭山湖入口交差点を左折して、狭山湖道を北へ進む。下田橋を渡ってすぐ左手に文政7年(1824年)造立の馬頭観音と天保6年(1835年)造立の石橋再建供養塔がある。馬頭観音は道標を兼ねており、右側面に“北
川こえ 西 青梅 南 やまくち”と彫られている。石橋再建供養塔は土に埋まり、垣根にも隠れて良く見えない。狭山湖道を北へ10分ほど進むと、所沢中央消防署西分署の先左手に文化5年(1808年)造立の不動橋石橋供養塔がある。不動橋石橋供養塔は、刻像された不動明王の下に“石橋供養塔”と彫られている。 |
|
 |
 |
 |
| 百番供養塔 |
石橋供養塔 |
実在寺別院 |
|
| 狭山湖道を北へ5分ほど進むと、若狭3丁目交差点で国道463号線バイパスと交差する。右折して国道463号線バイパスを東へ進む。10分ほどすると次の誓詞橋交差点の南東側に、案内看板や天明6年(1786年)造立の百番供養塔と石橋供養塔が並んでいる。 誓詞橋交差点から15分ほどすると小手指ヶ原交差点の北西側に実在寺別院[本門仏立宗]がある。
川越市富士見町・実在寺の小手指別院で、本門佛立宗の本山は京都市上京区にある宥清寺。 |
|
| 実在寺別院:所沢市北野新町1-12 |
|
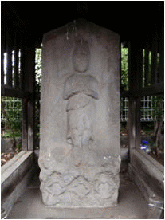 |
 |
小手指ヶ原交差点を左折する。すぐに左斜め方向の小道を進むと、右手に宝暦3年(1753年)造立の庚申塔と造立年不明の馬頭観音がある。馬頭観音は道標を兼ねており、“東
江戸道 南 八王子 西 青梅道 北 川越道”と彫られている。 |
| 庚申塔 |
馬頭観音 |
|
 |
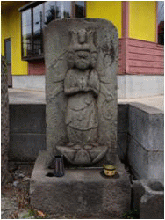 |
小手指ヶ原交差点から国道463号線バイパスを東へ、すぐに左斜め方向の小道が旧青梅街道になる。5分ほどすると、西武池袋線・小手指駅からの道路と交差する。直進して5分ほどすると十字路の北西側に、寛政5年(1793年)造立の石橋供養塔と安永6年(1777年)造立の馬頭観音がある。馬頭観音は道標を兼ねており、“右
川越道 左 青梅三ヶ嶋道”と彫られている。十字路を左折すると、旧青梅街道と交差する。 |
| 石橋供養塔 |
馬頭観音 |
|
| 旧青梅街道は西武池袋線・小手指駅からの道路と交差するところを直進しないで、斜め左手方向に進む。西武池袋線の踏切を斜めに渡る。車道は踏切を渡ってから回り込む様になる。10分ほどすると、国道463号線バイパスと宮本町交差点の南側で交差する。直進すると、すぐに峰の坂交差点の手前で国道463号線に合流する。国道463号線バイパスまで戻り、南へ進む。東川を渡り五差路の金山町交差点を南西に進む。踏切の手前を右折すると西武池袋線・西所沢駅に至る。 |
|
 |