| 所沢寺社石仏撮影散歩 |
|
| JR武蔵野線・新座駅〜JR武蔵野線・東所沢駅 |
|
| 新座駅 |
→ |
天神社 |
→ |
藤森稲荷神社 |
→ |
東光寺 |
→ |
塚越地蔵 |
→ |
城公民館 |
→ |
城山神社 |
→ |
放光地蔵 |
→ |
下組八幡稲荷神社 |
→ |
氷川神社 |
→ |
東福寺 |
→ |
遠照寺 |
→ |
東所沢駅 |
|
|
 |
 |
 |
| 天神社 |
天神社社殿 |
天神社境内社・納札所 |
|
| JR武蔵野線・新座駅より北へ、T字路を左折する。国道254号線を右折して北へ進む。柳瀬川を渡り、英インターを左折して国道463号線を南西へ進む。坂之下交差点を左折して南へ進むと、すぐ右手に天神社がある。左手に、境内社の御嶽神社
/ 氷川神社 / 熊野神社が並んでいる。 |
|
| 天神社:所沢市坂之下64 |
|
 |
 |
 |
| 庚申塔 |
藤森稲荷神社 |
|
| 小川沿いに進むと、左手の駐車場に架かる橋のたもとに、昭和32年(1957年)造立の庚申塔がある。県道179号線と合流する手前のY字路を右折すると、左手に藤森稲荷神社がある。 |
|
| 藤森稲荷神社:所沢市坂之下173 |
|
 |
 |
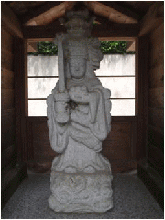 |
| 東光寺山門 |
東光寺本堂 |
白山妙理大権現 |
|
 |
 |
 |
| 子育地蔵 |
庚申塔 |
|
| すぐ右手に文明年間(1469年〜1486年)創建と云われる医王山・東光寺[曹洞宗]がある。本尊は薬師如来。久米・永源寺の末寺で、正平11年(1356年)に築城された滝の城(本郷城)鬼門の鎮めとして創建される。裏山に金毘羅堂がある。本堂への階段手前の左手に、白山妙理大権現がある。階段を登ると本堂の手前左手に天保12年(1841年)造立の子育地蔵、右手に安政6年(1859年)造立の庚申塔がある。 |
|
 |
 |
 |
| 石仏群 |
馬頭観音 |
馬頭観音 |
|
 |
 |
 |
| 普門供養塔 |
地蔵 |
石碑 |
|
 |
 |
 |
| 宝歴10年(1760年)造立の地蔵 |
大乗妙碑 |
地蔵 |
|
 |
 |
 |
| 六地蔵 |
大乗妙典写経供養塔 |
六地蔵 |
|
| 本堂左手の墓地入口に石仏群がある。右から奥へ、文化12年(1815年)造立の馬頭観音 / 安政5年(1858年)造立の馬頭観音 / 文化12年(1815年)造立の普門供養塔
/ 延亨2年(1745年)造立の地蔵 / 石碑 / 宝歴10年(1760年)造立の地蔵 / 安永年間(1764年〜1780年)造立の大乗妙碑
/ 地蔵 / 六地蔵(3基) / 正徳3年(1713年)造立の大乗妙典写経供養塔 / 六地蔵(3基)と並んでいる。文化12年造立の普門供養塔と延亨2年(1745年)造立の地蔵の間にも石塔があるが、墓石の様で画像は未掲載。 |
|
 |
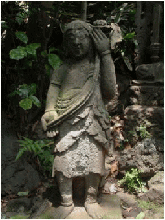 |
 |
| 不動明王 |
童子 |
童子 |
|
| 裏山の右手に不動明王と童子2基がある。 |
|
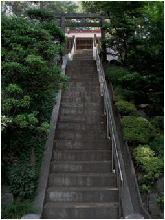 |
 |
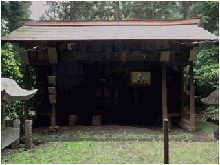 |
| 金毘羅堂石段 |
金毘羅堂 |
絵馬堂 |
|
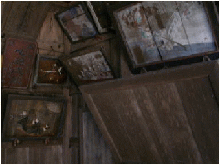 |
 |
 |
| 絵馬堂 |
絵馬堂 |
祠 |
|
 |
本堂の左手奥の石段を登ると金毘羅堂、左手に絵馬堂がある。金比羅堂には金毘羅大王が祀られている。金毘羅大王は、インドのガンジス川に棲む鰐を神格化した仏法守護神である十二神将の一将。宮毘羅(くびら)大将とも呼ばれる。海神や水神として、海上安全 / 海難救助 / 雨乞い / 風除けとして祈願をされる。絵馬堂には、木製のプロペラや絵馬が掛けられている。金毘羅山道を下ると途中に、祠
/ 地蔵と天保12年(1841年)造立の百番供養塔が並んでいる。 |
| 百番供養塔と地蔵 |
|
| 東光寺:所沢市坂之下383 |
|
 |
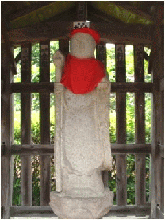 |
東光寺の先を右折して坂を登り、T字路を左折する。五差路の交差点の右手に、享保18年(1733年)造立の塚越地蔵がある。道標として尼僧が造立したと云われている。台座の正面に“左
ちくまざわみち 中 とめみち 右 かめやすみち”と彫られている。 |
| 塚越地蔵 |
|
 |
 |
 |
| 庚申塔 |
六地蔵 |
|
 |
 |
 |
| 大乗妙典六十六部供養塔 |
大乗妙典六十六部供養塔 |
大乗妙典六十六部供養塔 |
|
 |
五差路の交差点を左折、県道179号線を右折して西へ進む。関越自動車道を越え、五差路の交差点から30分ほどで城交差点の右手に城公民館がある。城公民館前に宝永2年(1705年)造立の庚申塔、城公民館の裏手が墓地で、入口の左右に宝暦3年(1753年) 造立の六地蔵が3体づつある。すぐ左手に安永2年(1773年)造立の大乗妙典六十六部供養塔
/ 明和2年(1765年)造立の大乗妙典六十六部供養塔 / 明和4年(1767年)造立の大乗妙典六十六部供養塔が並んでいる。奥にも石仏群が見える。 |
| 奥の石仏群 |
|
 |
城交差点を左折して南東へ進む。左手に滝の城址入口がある。城址の縄張り図があり、左折して道なりに進む。遊歩道で滝の城址公園を巡ることができる。滝の城(本郷城)は、正平11年(1356年)大石重定によって築城される。豊臣秀吉による小田原城攻めで、八王子城の支城であった滝の城も攻撃される。天正18年(1590年)の北条氏滅亡後に徳川家康が関東に入府すると、滝の城は廃城となる。滝の城本丸跡に滝の城址碑がある。 |
| 滝の城址碑 |
|
 |
 |
 |
| 城山神社社殿 |
稲荷神社 |
稲荷神社 |
|
 |
滝の城本丸跡に愛宕神社が創建される。承歴年間(1077年〜1081年)創建の熊野神社 / 城内の鎮守として天正年間(1573年〜1593年)創建の天神社
/ 城の鬼門除けとして天正年間(1573年〜1593年)創建の八幡神社 / 稲荷神社2社を明治41年(1908年)愛宕神社に合祀、城山神社に改称する。高台の物見台跡に稲荷神社が3社ある。 |
| 稲荷神社 |
|
| 城山神社:所沢市城537 |
|
 |
 |
滝の城址入口まで戻り、坂を下る。ここからは先は昼間でも暗い。左手に寛政11年(1799年)造立の馬頭観音と“血の出る松の跡”がある。豊臣秀吉による小田原城攻めで、支城であった滝の城も攻撃された。討ち殺された城兵の血を吸った松に傷をつけると、赤色の樹液が出たことから“血の出る松”と云われる様になる。“血の出る松”は既に枯れ、石碑が立っている。 |
| 馬頭観音 |
血の出る松の跡 |
|
 |
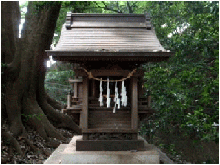 |
さらに下ると右手に鳥居、狭い参道を進むと稲荷神社がある。 |
| 稲荷神社鳥居 |
稲荷神社社殿 |
|
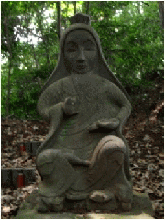 |
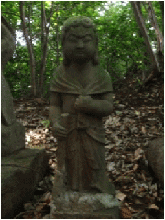 |
 |
| 役行者 |
童子 |
不動明王 |
|
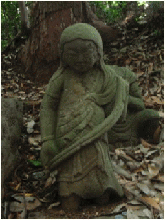 |
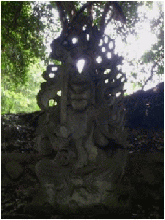 |
 |
| 童子 |
不動明王 |
蔵王権現 |
|
| 稲荷神社反対側の左手にある暗い木立ちの階段を登る。左手に進むと、嘉永3年(1850年)造立の役行者 / 弘化3年(1846年)造立の童子 /
弘化3年(1846年)造立の不動明王 / 弘化3年(1846年)造立の童子と並んでいる。直進すると不動明王がある。右手に進むと、弘化2年(1845年)造立の蔵王権現がある。 |
|
 |
 |
坂をさらに下ると、左手に城山神社の鳥居がある。石段を登る手前左手に、堀の跡がある。 |
| 城山神社鳥居 |
堀の跡 |
|
 |
城山神社の鳥居から坂を下ると、右手に大きな楠木がある。根元の石垣に囲まれたところが、滝の城・霧吹きの井戸跡である。弘化3年(1846年)造立の大峯大権現が埋もれる様に立っている。左側面に鎮守八幡宮、右側面に成田山不動尊と彫られている。 |
| 大峯大権現 |
|
 |
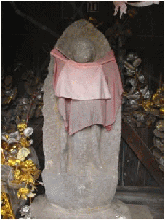 |
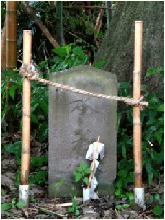 |
| 正徳元年(1711年)造立の放光地蔵 |
明治9年(1876年)造立の水神 |
|
| 城山神社の鳥居から坂を下り、道なりに進みJR武蔵野線を潜る。すぐ右折して南西へ進むと、左手に正徳元年(1711年)造立の放光地蔵がある。いぼとり地蔵と云われている。堂の左手に、昭和60年(1985年)に造立された放光地蔵由来之碑がある。縁日は9月14日。すぐ右手に明治9年(1876年)造立の水神がある。小さく木々に隠れており、気を付けないと見逃す。 |
|
 |
 |
水神から10分ほどで変則四差路があり、左折すると左手に下組八幡稲荷神社がある。 |
| 下組八幡稲荷神社 |
|
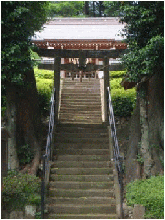 |
 |
 |
| 氷川神社 |
氷川神社社殿 |
氷川神社境内社 |
|
|
変則四差路まで戻り、左折して南西へ進む。10分ほどすると案内看板があり、右折すると氷川神社がある。明治41年(1908年)八雲神社の地に、本郷原・神明社
/ 八幡社 / 本郷中央・氷川神社を合祀する。本郷原・神明社境内にあった稲荷神社を八幡社跡地に移転、下組稲荷神社になる。昭和50年(1975年)社殿改築のとき、下組八幡稲荷神社に改称される。 |
|
| 下組八幡稲荷神社:所沢市本郷434 |
| 氷川神社:所沢市本郷676 |
|
 |
 |
 |
| 東福寺山門 |
東福寺本堂 |
成田山不動堂 |
|
 |
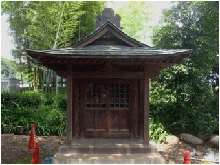 |
 |
| 乳不動堂 |
薬師堂 |
鐘楼 |
|
| 氷川神社から5分ほどすると、右手に水木山・東福寺[真言宗豊山派]がある。青梅・金剛寺の末寺。本尊は、鎌倉末期1300年代の作と云われる木造阿弥陀如来。本堂右手に旧阿弥陀堂だった成田山不動堂
/ 乳不動堂 / 薬師堂がある。薬師堂には、明治4年(1871年)造立の薬師如来がある。如乳不動は、出産のあと乳の出が良くなる様に祈願する。裏山には大日如来
/ 不動明王 / 三十六童子や平成14年(2002年)造立の守護観音がある。 |
|
 |
 |
 |
| 六地蔵 |
百番四国供養塔 |
馬頭観音 |
|
 |
 |
 |
| 馬頭観音 |
庚申塔 |
馬頭観音 |
|
 |
山門手前の参道には、左右に石仏が並んでいる。
左側は手前から奥へ
文化3年(1806年)造立の六地蔵(3基) / 文久2年(1862年)造立の百番四国供養塔 / 安永4年(1775年)造立の馬頭観音 / 天保14年(1843年)造立の馬頭観音
/ 弘化3年(1846年)造立の庚申塔 / 嘉永2年(1849年)造立の馬頭観音 / 昭和13年(1938年)再建の馬頭観音
昭和13年(1938年)再建の馬頭観音は、北側の竹林から移されている。 |
| 馬頭観音 |
|
 |
 |
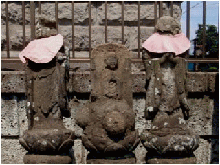 |
| 地蔵 |
地蔵 |
六地蔵 |
|
 |
 |
 |
| 出羽三山供養塔 |
馬頭観音 |
馬頭観音 |
|
右側は手前から奥へ
享保3年(1718年)造立の地蔵 / 正徳3年(1713年)造立の地蔵 / 文化3年(1806年)造立の六地蔵(3基) / 天保2年(1831年)造立の出羽三山供養塔
/ 馬頭観音 / 馬頭観音 |
|
 |
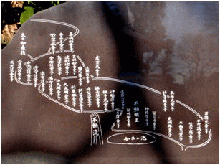 |
 |
| 不動明王 |
裏山の石仏配置図 |
不動明王 |
|
 |
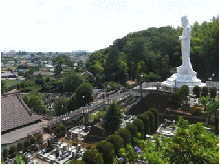 |
不動堂の階段手前の左手に、明治12年(1879年)造立の不動明王がある。乳不動堂の右手から裏山を登る。明治初期に造立の三十六童子に換わり、平成11年(1999年)造立の三十六童子がいたるところに置かれている。
途中に平成10年(1998年)造立の不動明王、登り切った頂きに明治10年(1877年)造立の大日如来がある。平成14年(2002年)造立の守護観音、眼下に本堂や町並が見える。 |
| 大日如来 |
守護観音 |
|
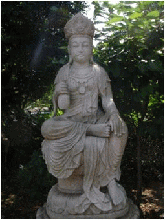 |
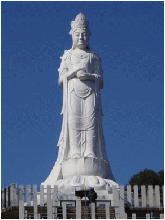 |
 |
|
守護観音 |
石塔群 |
|
 |
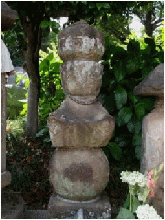 |
 |
| 六地蔵幢 |
五輪塔 |
庚申塔 |
|
 |
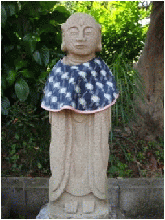 |
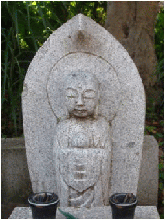 |
| 無縫塔 |
地蔵 |
地蔵 |
|
| 本堂左手に石仏、奥に守護観音がある。左手に進むと、天和3年(1683年)造立の六地蔵幢 / 五輪塔 / 天和3年(1683年)造立の庚申塔 /
無縫塔 / 地蔵 / 地蔵と並んでいる。 |
|
| 東福寺:所沢市本郷764 |
|
 |
東福寺から道なりに南西へ進む。左手の手作りパン店の先にある変則十字路を右折して北へ進む。坂を登るとすぐ左手に寛政12年(1800年)造立の庚申塔がある。土砂が流れやすいところで、埋もれていた時期もあった様である。 |
| 庚申塔 |
|
 |
北へ進み、179号線を左折して西へ進む。東所沢駅入口交差点の南東側に、白布山・遠照寺(おんしょうじ)[浄土真宗]がある。東所沢駅入口交差点を北へ進むと、JR武蔵野線・東所沢駅に至る。 |
| 遠照寺 |
|
| 遠照寺:所沢市本郷1091-9 |
|
 |