| 寝台列車 |
|
 |
 |
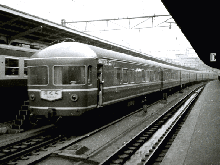 |
| EF60 510 |
カニ22 |
ナハフ20 |
|
| 昭和38年(1963年)〜昭和41年(1966年)の運行区間 |
| あさかぜ |
|
東京⇔博多 |
|
|
| さくら |
|
東京⇔長崎 / 博多 |
|
昭和40年(1965年)10月からは東京⇔長崎 / 佐世保 |
| はやぶさ |
|
東京⇔西鹿児島 |
|
昭和40年(1965年)10月からは東京⇔西鹿児島 / 博多 |
| 富士 |
|
東京⇔大分 / 下関 |
|
昭和40年(1965年)10月からは東京⇔西鹿児島 / 下関 |
| みづほ |
|
東京⇔熊本 / 大分 |
|
昭和39年(1964年)10月からは東京⇔熊本 / 博多 |
| はくつる |
|
上野⇔青森 |
|
|
|
|
| 東京駅〜西鹿児島駅の寝台特急・はやぶさは1515.3km / 東京駅〜西鹿児島駅を日豊本線経由で結んでいた寝台特急・富士は1574.2kmの最長運行距離であった。 |
|
 |
 |
 |
| EF60 あさかぜ |
20系 あさかぜ |
20系 あさかぜ |
|
 |
 |
 |
| EF60 はやぶさ |
20系 はやぶさ |
20系 はやぶさ |
|
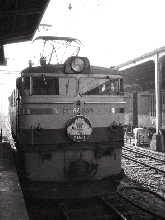 |
 |
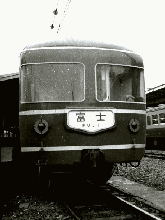 |
| EF60 富士 |
荷物電車 / 20系 富士 |
20系 富士 |
|
 |
 |
 |
| 20系 富士 |
EF60 みづほ |
20系 みづほ |
|
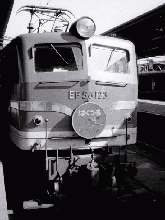 |
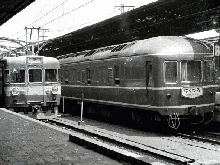 |
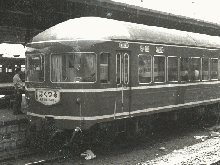 |
| EF58 はくつる |
交直流電車 / 20系 はくつる |
20系 はくつる |
|
| 20系以降の寝台特急牽引機関車 |
|
 |
 |
 |
| EF81 133 北斗星 上野駅 |
ED79 19 北斗星 函館駅 |
DD51 1107 北斗星 函館駅 |
|
|
北斗星は、昭和63年(1988年)〜平成27年(2015年)上野駅〜札幌駅に運行されていた寝台特急列車。上野駅〜札幌駅を1214.7kmを結んでいた。
|
|
 |
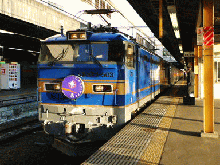 |
カシオペアは、平成11年(1999年)から上野駅〜札幌駅に運行開始した臨時寝台特急列車。平成28年(2016年)3月の北海道新幹線開業に伴い、青函トンネル内の架線電圧が変更となる。牽引電気機関車の問題から廃止になる予定になっている。
|
| EF81 99 カシオペア 上野駅 |
EF510 503 カシオペア 宇都宮駅 |
|
 |
 |
あけぼの は、昭和45年(1970年)〜平成26年(2014年)上野駅〜青森駅に運行されていた寝台特急列車。東北本線〜高崎線〜上越線〜信越本線〜羽越本線〜奥羽本線を経由していた。
|
| EF64 1051 あけぼの 赤羽駅 |
EF64 37 あけぼの 日暮里駅 |
|
 |
 |
北陸は、昭和22年(1947年)上野駅〜金沢駅・新潟駅間を運行していた夜行急行列車が始まり。昭和50年(1975年)寝台特急に格上げされ、余剰となっていた20系客車が使用された。昭和53年(1978年)14系客車に変更された。平成22年(2010年)運行終了となる。東北本線〜高崎線〜上越線〜信越本線〜北陸本線を経由していた。
|
| EF64 1052 北陸 上野駅 |
EF64 1052 北陸 日暮里駅 |
|
 |
トワイライトエクスプレスは、平成元年(1989年)7月に大阪駅〜札幌駅間を結ぶ団体専用列車として運行したのが始まり。12月からは週4日発着の臨時列車として運行される。東海道本線〜湖西線〜北陸本線〜信越本線〜羽越本線〜奥羽本線〜津軽線〜海峡線〜江差線〜函館本線〜室蘭本線〜千歳線を経由していた。平成27年(2015年)運行終了となる。ツアー専用列車は、平成28年(2016年)3月の北海道新幹線開業まで運行される予定になっている。大阪発札幌行きは1495.7kmを約22時間
/ 札幌発大阪行きは1508.5kmを約22時間50分で運行していた。
|
| EF81 114 大阪駅 |
|
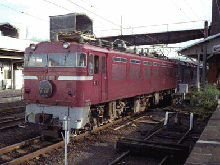 |
なは は、昭和43年(1968年)大阪駅〜西鹿児島駅間に運行を開始した昼行特急列車が始まり。キハ82系ディーゼル車両が使用された。 昭和48年(1973年)485系電車となる。昭和50年(1975年)山陽新幹線が全通により夜行寝台特急列車となり、583系電車寝台に変更される。運行は、新大阪駅〜西鹿児島駅間になる。昭和59年(1984年)24系寝台客車に変更される。平成16年(2004年)九州新幹線・新八代駅〜鹿児島中央駅間の部分開業に伴い、京都駅〜熊本駅間になる。平成20年(2008年)運行終了となる。
|
| ED76 86 なは 熊本駅 |
|
 |
581系は昭和42年(967年)に座席・寝台両用電車として運用が始まった寝台特急列車。月光型と呼ばれた。60Hz専用電動車を連結したのが581系、50Hz/60Hz両用の電動車を連結したのが583系。
|
| 九州鉄道記念館 |
|
 |
 |
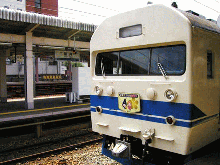 |
| 1997年 早岐駅 |
2002年 米原駅 |
2002年 福井駅
|
|
|
寝台特急の運用から外れ、普通車に改造された。3〜4両編成で使用するために制御車が不足、中間車の運転台取付改造も行われた。非貫通切妻構造であるが、寝台列車特有の屋根構造になっている。その形状から“食パン電車”などと呼ばれた。昭和59年(1984年)から順次、交流専用の715系は長崎本線・佐世保線
/ 交流専用の寒冷地対応車715系は東北本線 /交流直流両用の419系は北陸本線 で使用された。佐世保線や北陸本線で普通車に改造された715系や419系に乗車すると、面影が残る天井を思わず見上げていた。
|
|
 |
急行“きたぐに”は、昭和22年(1947年)から大阪駅・青森駅間で運行されたのが始まり。昭和60年(1985年)583系が投入され、電車化される。平成24年(2012年)定期列車としての運転が終了する。画像は 京都駅留置線。
|
| 2000年 急行 きたぐに |
|
 |